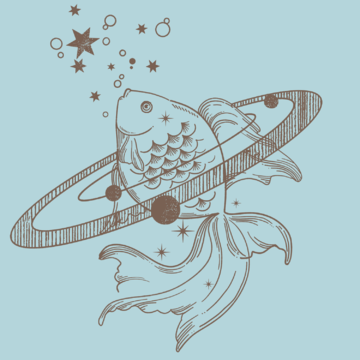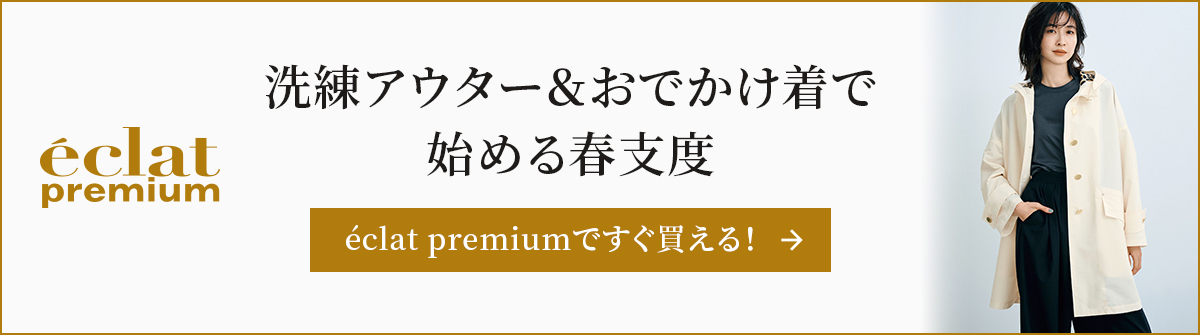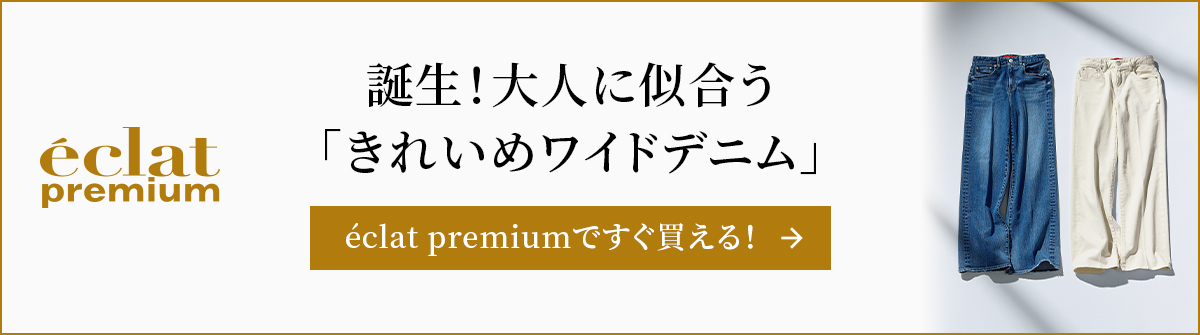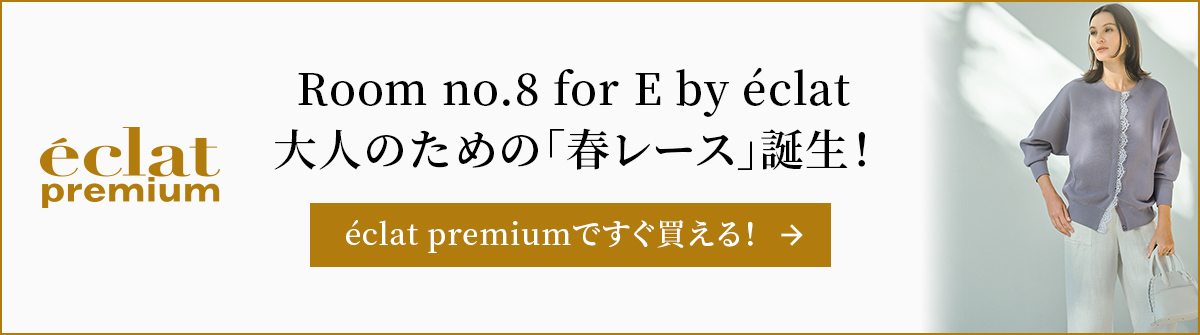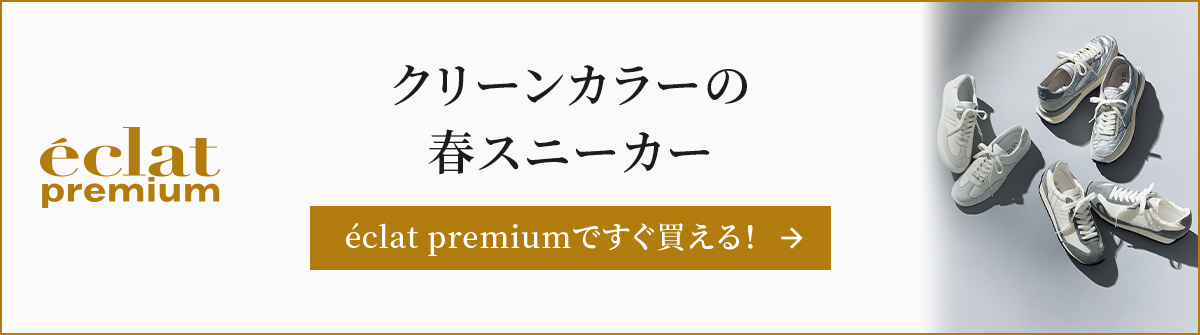愛する者を失いながらも、なぜ人は生きるのか。戦国末期の石見(いわみ)銀山を舞台にひとりの女性の不屈の生を描ききった『しろがねの葉』で、新・直木賞作家となった千早茜さん。作家としての成長のため、これまで一作ごとに自身の中で課題を設定して小説を書いてきたという。
人間とは? その問いへの答えを、物語の中に探しにいくんです

「時代小説に挑戦するとか、連作を試してみるとか。この15年間、どんどん違うものを書いていこうというスタンスで取り組んできたので、基本的に続編はやらないポリシーだったんですが……」
受賞後第一作として刊行された『赤い月の香り』は、3年前に発表した『透明な夜の香り』の後を継ぐ長編小説。香りを題材に人の心の不思議に迫る作品であえて禁を破った理由をたずねると、「コロナ禍の閉塞感の中、香りを扱うことで自分でも癒されたと感じていました。読者のかたがたもきっとそうだったんじゃないかな? と思って」という答えが返ってきた。
物語のキーパーソンは、人の記憶や体験にまつわるあらゆる匂いを香りとして具現化する天才調香師・小川朔(さく)。彼のもとには日々、さまざまな依頼人が訪れる。忘れられない場所の匂い。愛する人の匂い。時には嗅覚を失った人までもが、それでも渇望する匂いを彼に訴える。誰もがその身に世界にひとつの体臭をまとっていて、それを求めることは唯一無二の欲望だと語る朔。依頼人たちの思いを探り、その深層に見出したものを彼は香りに結実させていく。
前作が「透明」なのに対し、今作のモチーフカラーは「赤」。血や暴力性をうかがわせる色だけに、欲望の中でも特に、加害性をはらんだ執着がクローズアップされる。自身も香りには敏感だという千早さんならではの緻密でリアルな人間心理へのアプローチは、謎解きのようにマジカルだ。
「恋愛や親子関係のように、関係が濃くなればなるほど、加害性は出やすくなると思うんです。嫉妬や独占欲から相手を傷つけてしまうことが、私はとても怖くて。正しい執着、間違いのない執着ってなんだろう?ということを、朔と一緒に探ってみたかった」
作中、流麗かつ鮮烈に描写される香りの数々。それらを想像しながら、自分は今、どんな匂いを発しているのか、そして、本当は何を求めているのか──と、いつしか思いを馳せてしまう。「そう、人って、わからないものですよね」と、千早さんもうなずく。
「よく『小説を書いているんだから人のことがよくわかるんでしょう?』といわれるけれど、むしろ、全然逆。私の中には人間という存在に対する問いが常にあって、人間について想像することでしか答えを見つけられない。小説を書きながら、私はそれを物語の中に探しにいくんだと思います」
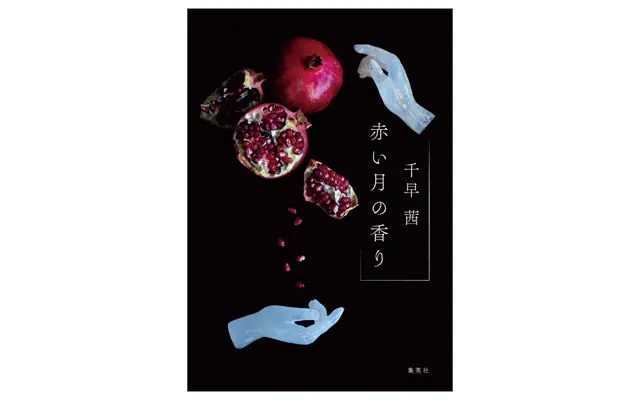
『赤い月の香り』
「君からは怒りの匂いもする」。謎めいた調香師・朔の言葉に誘われ、古い洋館で働き始めた青年・満。奇妙に静謐(せいひつ)な時を過ごす中、彼はやがて心の中に眠らせた赤色の記憶を呼び覚ます……。シリーズ前作の『透明な夜の香り』は文庫版が発売中。芳醇な香りに包まれる極上の物語体験を。集英社 ¥1,760