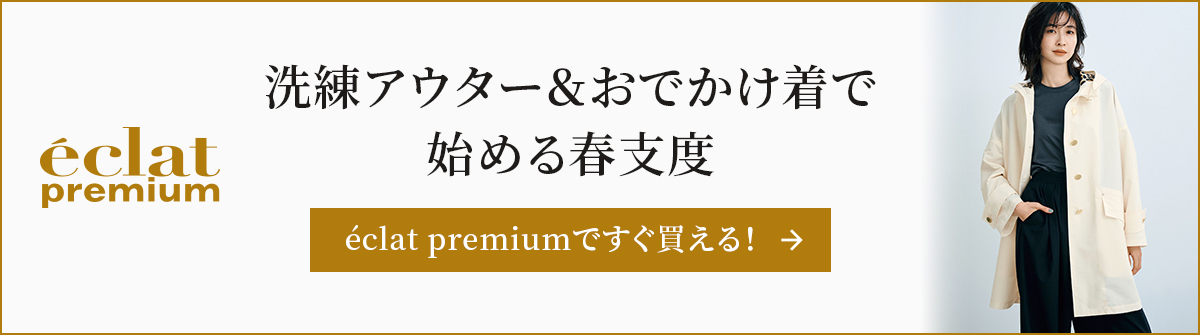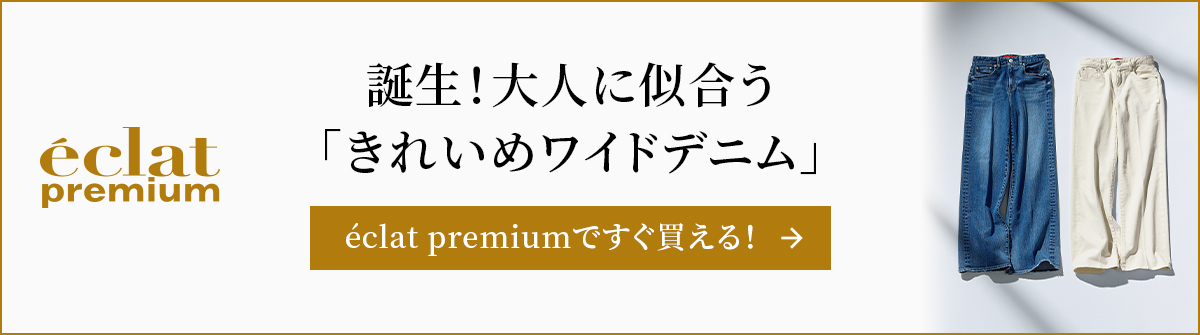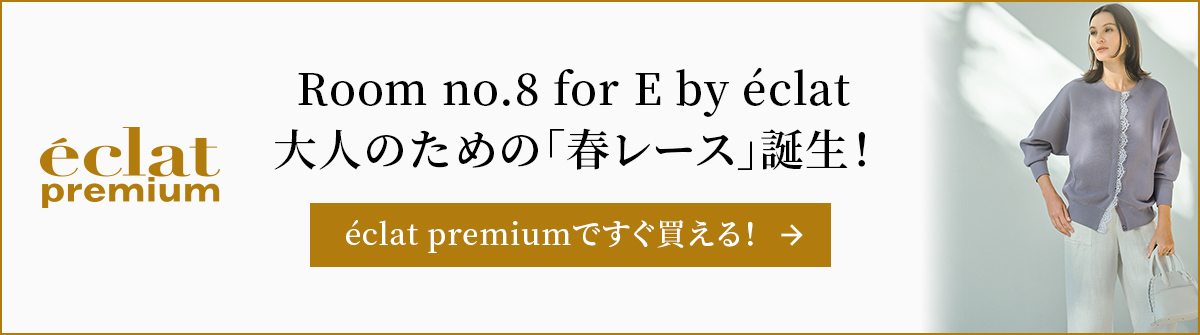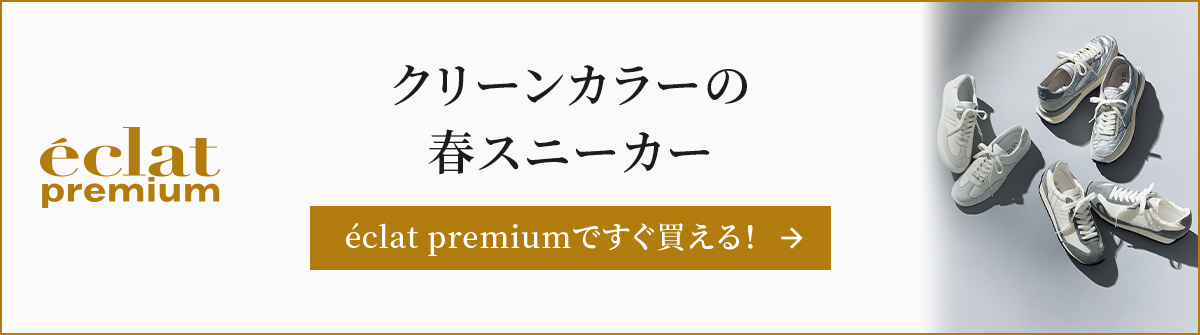多民族国家の生きた声を掬う在豪作家・岩城けいさん。既刊『Masato』『Matt』につらなる、「アンドウマサト三部作」最終章『M』について話を伺った。
「ふつう」は強い言葉。 ふつう=多数派だから偉いわけではないんです

オーストラリに移住して30年。多民族の国で家族と暮らしながら小説を書いてきた岩城けいさんが最新作『M』で描いたのは“大切な人を知り自分を知ること”。主人公は12歳のとき父の転勤でオーストラリアに移住し、現在はメルボルンのシェアハウスで暮らす大学生・マサト。彼はいまだに“日本人”としか見られず、自らのアイデンティティについて悩んでいたが、アルメニアにルーツがある大学生・アビーと出会い、彼女もアイデンティティの問題を抱えていることを知る。
「息子の友だちにアルメニア人の女の子がいて、アビーの悩みは息子とその女の子の会話から聞こえてきたことがヒントになっています。アビーは見た目は白人ですが、親から“少数民族の子孫を残すために結婚はアルメニア人と”といわれていて、“変わった国の子ではなくふつうの国のふつうの子になってみたかった”と思っている。彼女の気持ちを書くのに“ふつう”という言葉を使ったのは、“ふつう”という言葉の力や強さが以前から気になっていたから。どんな国に生まれても人はみんな違うのがあたりまえなのに、多くの人が“自分はふつう”とか“ふつうが一番偉い”などと考えがち。たぶん安心を求めてのことだと思いますが、日本でもオーストラリアでも見られる傾向です」
やがてマサトもアビーも卒業後の進路を考える時期を迎える。マサトはハイスクール時代から興味をもっていた演劇ではなく、得意なことを生かして就職しようとしていたが、アビーを通して「劇」のおもしろさに再び目覚めて……。ふたりがお互いの存在や進路についてどう思い、どんな選択をするのかは読んで確かめていただきたいが、『M』を書き終えた今、岩城さんが改めて考えているのは言葉の問題だという。
「オーストラリアに長く住んでいるマサトとアビーは英語が母語ですが、彼らの親の母語は日本語でありロシア語。言葉は人をつなぐといいますが、マサトとアビーは人を隔てもするのが言葉だと感じています。だから親に対して複雑な思いがあって……。そこには私の実感が反映されていますが、私自身は“母語はひとつではない”という感覚。具体的にいうと夫や子供たちとの会話は日本語で、情報として入ってくるのはほぼ英語。頭の中は日本語でも英語でもない感じで、小説を読んだり書いたりするのは日本語。それが私のベースなので、日本もオーストラリアも俯瞰で見ている気がします。そんな私が言葉について感じていることが次の小説のテーマになりそう。言葉は私がデビュー作でも取り上げた原点ともいえる問題なので、考えることがたくさんあると思います」


『M』
大学生のマサトは偶然知り合ったアビーに誘われて人形劇と出会い、彼女にも人形劇にも興味をもつ。日本のカルチャーがメジャーになってマサトが感じたこと、見た目は白人だが少数民族出身のアビーの悩みなど、若者の繊細な心情が伝わってくる小説。集英社¥1,815
▼こちらの記事もチェック!