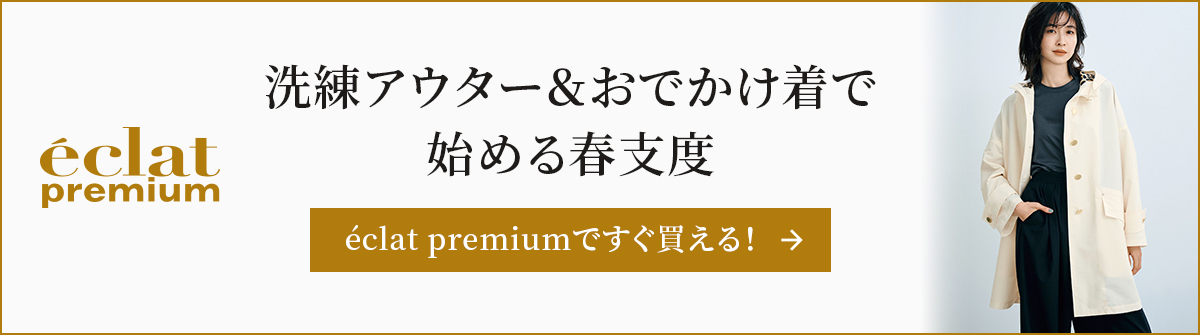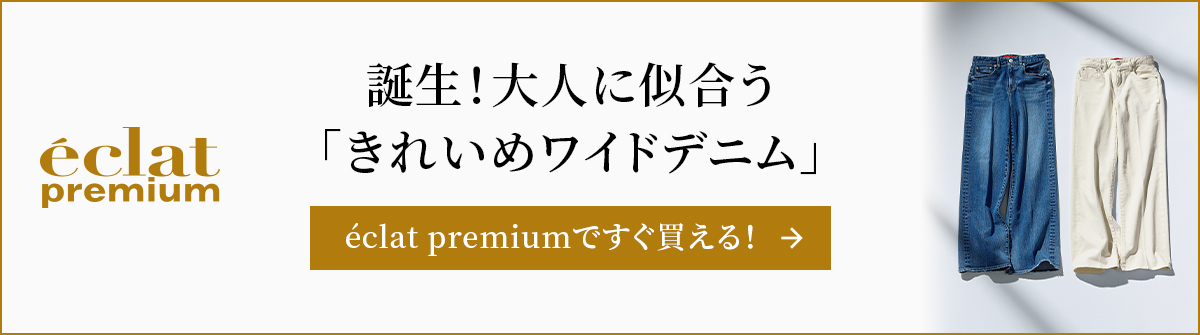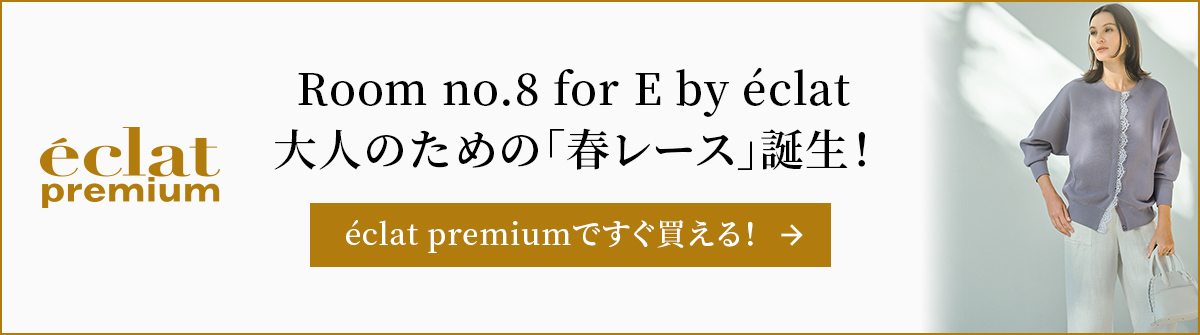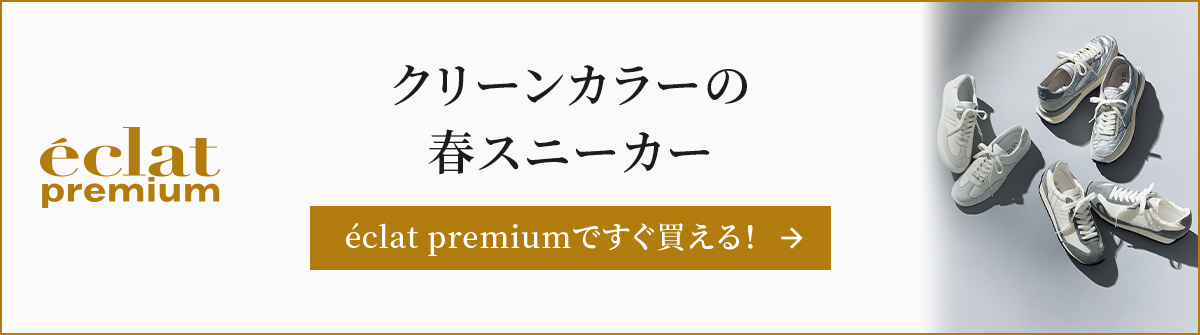強くしなやかで、どこまでも自由──。数々のテレビドラマで魅力あふれる女性像を提示してきた大石静さんもまた、独自の才能を開花させ、より奔放に今を生きて描き続ける人。50代からの人生を、私たちはどうサバイブすべきか? 前中後編の中編では、人生の転機を迎えるきっかけとなった出来事について語ってもらった。
どん底から人気脚本家へ。人生を変える波に乗った日
生まれは東京、神田駿河台。NHKの連続テレビ小説『オードリー』(’00〜’01年放送)さながらに、実母のかわりに旅館を経営する養母に育てられた大石さんは、幼いころから旅館に出入りする作家や学者たちの様子を眺めていた。その当時から、「なぜ自分は生まれてきたんだろう」という疑問にとらわれていたという。
「自分の気持ちに関係なく生まれ、家も選べず、朝起きると『ああ、また一日生きなくちゃいけない』『生まれなければこんな気持ちにならなくてすんだのに』と。まわりの大人は皆大変そうだったし、母もかわいそうだとは思ったけれど、そのことで被害者意識があったわけでもないんです。なんというか、私の命がいやがっている感じ? 生きるのは悲しい、虚しいものだと、いつもモヤモヤしていて、それでも学校へ行くと、スイッチが入ったかのように元気な子になった。私は皆に嘘をついているんだと思いながら」
『光る君へ』の序盤、自分は実は高貴な姫であるとうそぶいていた少女時代のまひろの姿が、ふと浮かぶ。生まれ出いづる悩みともいうべき複雑な思いを抱いたまま成長した大石さんが長じて最初に目ざしたのは、女優になること。しかしチャンスはなかなかめぐってこず、劇団を立ち上げて劇作の道へ入るも「究極のマイナー」だったと、当時を振り返る。
「まったく認められず、毎日、劇場を掃除して、ゴミを出して、アルバイトをしながら赤字を埋めて……。いったい私はいつこの状況から卒業できるんだろうと思ってましたね」
転機はふいに訪れた。30代半ばに映像業界から声がかかり、書いたテレビドラマが放送された翌日、世界が一変する。
「朝から電話がバンバンかかってきて、『昨日のドラマを見ました。次は一緒にやりましょう』と、まったく知らないプロデューサーたちから……。波が、きた!という感じがしました。これに乗ろう、乗らなきゃダメだという、天の声が聞こえたような気がして。それまでくすぶっていたけれど、初めて人から求められたと思いました。ずいぶん遅かったけど」
そこからは、無我夢中。その人間の過去と現在のすべてを表すセリフ=しゃべり言葉にこだわること。主役も悪役も、人物を立体的に描くこと。起承転結を考えずに、次に見たいシーンだけを追って物語をつくること。ひらめきを大事にすること。ひとつの作品の成功が次の仕事を呼び、オファーは引きも切らなかった。
「これしか食べていく方法がなかったということもあると思います。何をやってもダメだったけど、脚本を書くことで、やっと人に認めてもらえた。だったら、これにしがみついて生きていこう……、そう思った日のことを今も忘れないです。今って皆、ちょっとやってしんどかったらすぐやめちゃうでしょう? だけど、しがみついてみないと真髄は見えないよねって、私は思う。どのジャンルでもそうでしょうけど、打たれ強い人だけがチャンスを得られるし、やりたいこともできるんじゃないかしら。そうして長くやり続けた人だけに、また違う扉も開くんじゃないかなって思うんですよ」

音のない書斎での執筆に付き合うのは14歳の雄猫・アラン。「アラン・ドロンのようにかわいい顔をしているから」と亡き夫が命名した。多くの人物が命を落とす場面を書く際は、線香を焚くことも。
「いつだって、強く生きる人を書いてきた。助けてあげたい人じゃなく、自分の力で突破していく人の姿を」
書いてきたのは、常に「強い女」だったと、大石さん。それはそのまま、目の前にいる本人に重なる。
「人が、いろんな困難に負けないで強く生きる姿が好き。たとえかわいそうな境遇であったとしても、助けてあげたくなるような人ではなく、自分の力で突破していく人を書きたかった」
ハードな執筆も夫の看取りも、自分だけの大切なミッション
力強く前進する女性のドラマを描き続ける生活もまた、想像以上にハードだ。大河ドラマの脚本執筆には、制作統括、演出家たちとの入念な打ち合わせが欠かせない。大石さんが書いた脚本に演出家たちからの要望が入り、修正の討議に5〜6時間。さらに翌週分の脚本をめぐる議論に2〜3時間と、常に8時間を超えるほどの打ち合わせをこなしたうえで、膨大な資料を読みこなし、時代考証による修正にも対応しなければならない。執筆は夜。夕方ごろから気にしつつ「もう逃げられない」と覚悟を決めた深夜から明け方まで、自宅の書斎で粛々と行う。
「大河にかぎらず、ドラマを書くのはいつでも大変。今回はスタッフも平安時代のことを深くは知らないので、全員がすごく勉強しなくてはならない。でも皆、すごく情熱的にやっているし、それは私も負けてはいられないと思います。1000年も前のことって、この作品をやらなければ知らなかったことじゃないですか。そういう意味では、知る喜びに支えられているともいえますね」
人はなぜ生きるのか。少女時代に向き合った疑問は、「今もまだ解決できていない」と大石さんはいう。
「人は意に反して生まれ、意に反して死ぬ虚しい存在だという思いは変わらずにもっています。でも、脚本家になってからは一緒にドラマを作る仲間との連帯があるし、ドラマを作っている間は、虚しさは忘れる瞬間もありますね。今の大河も、『美術部がこんなにがんばってすごいセットを作っているんだ』と思えば、私もがんばろうってなるじゃないですか。役者たちからもスタッフたちからも『大石さんの本はおもしろい』と思われたい。そう思われなければいいものはできません。そのためなら、どんなに苦しくてもやるしかないのです」
(後編へつづく)

▼こちらの記事もチェック!