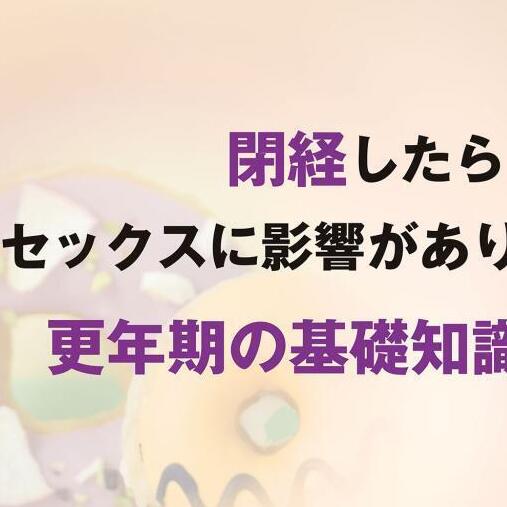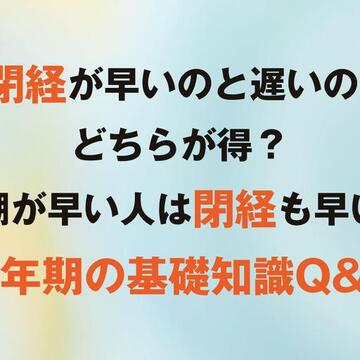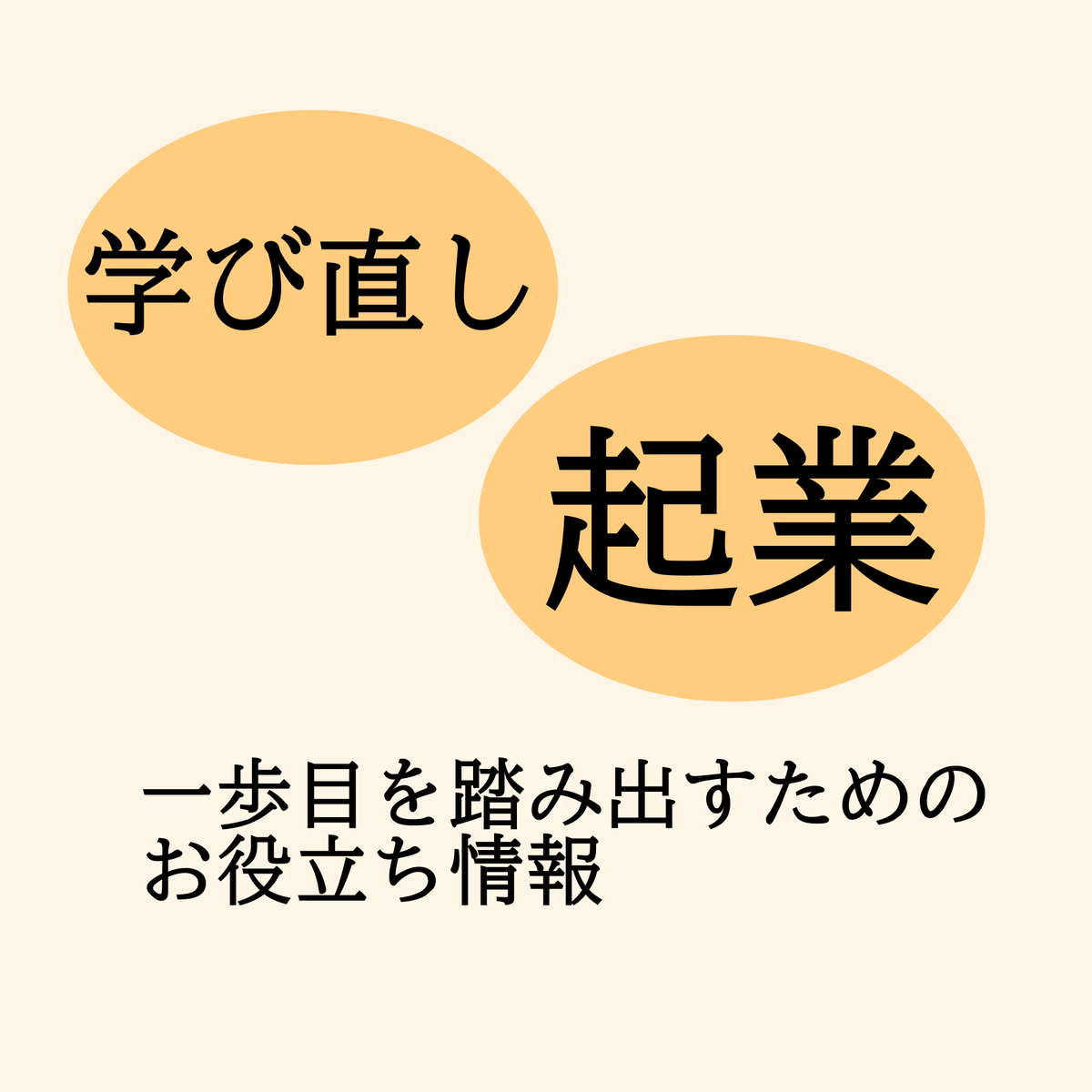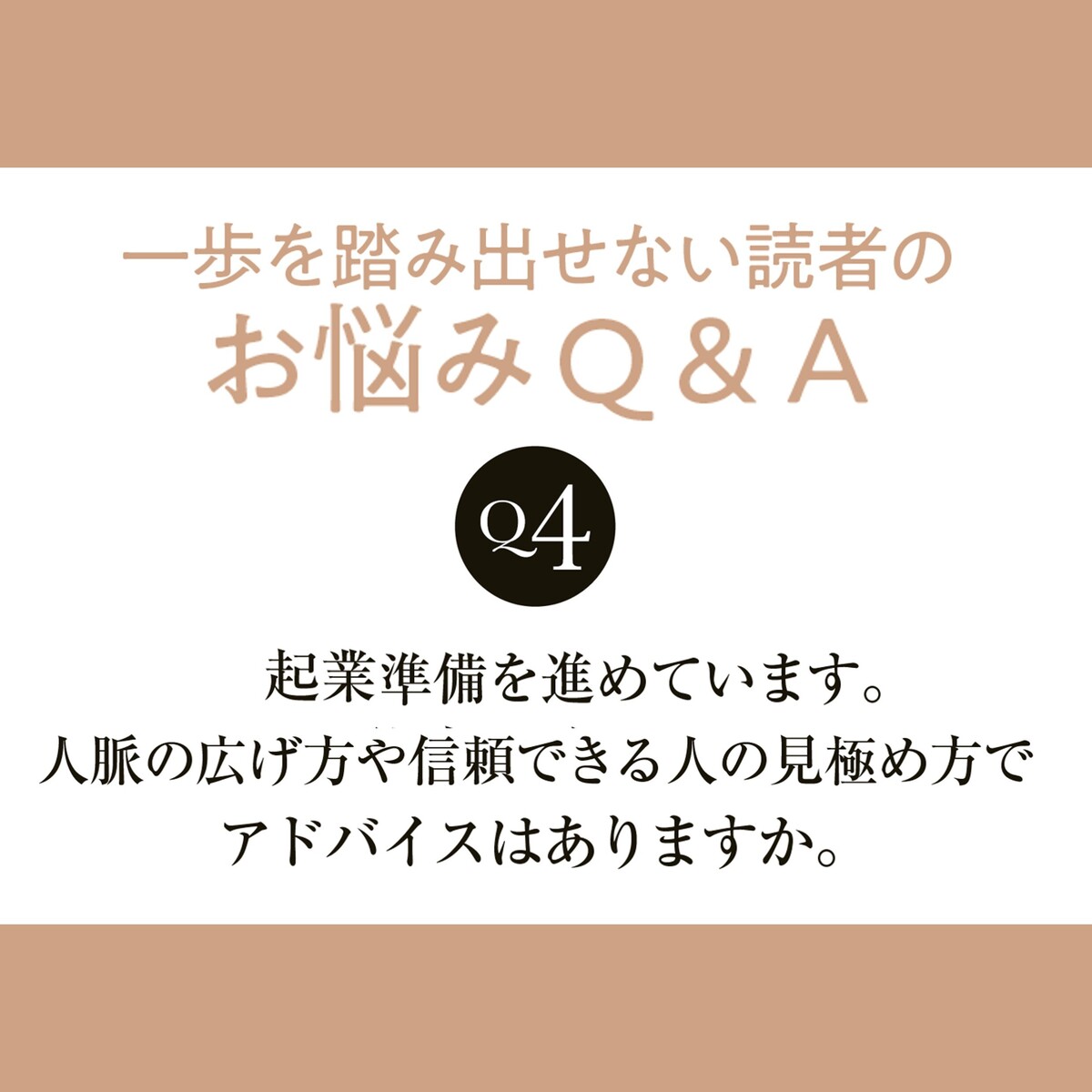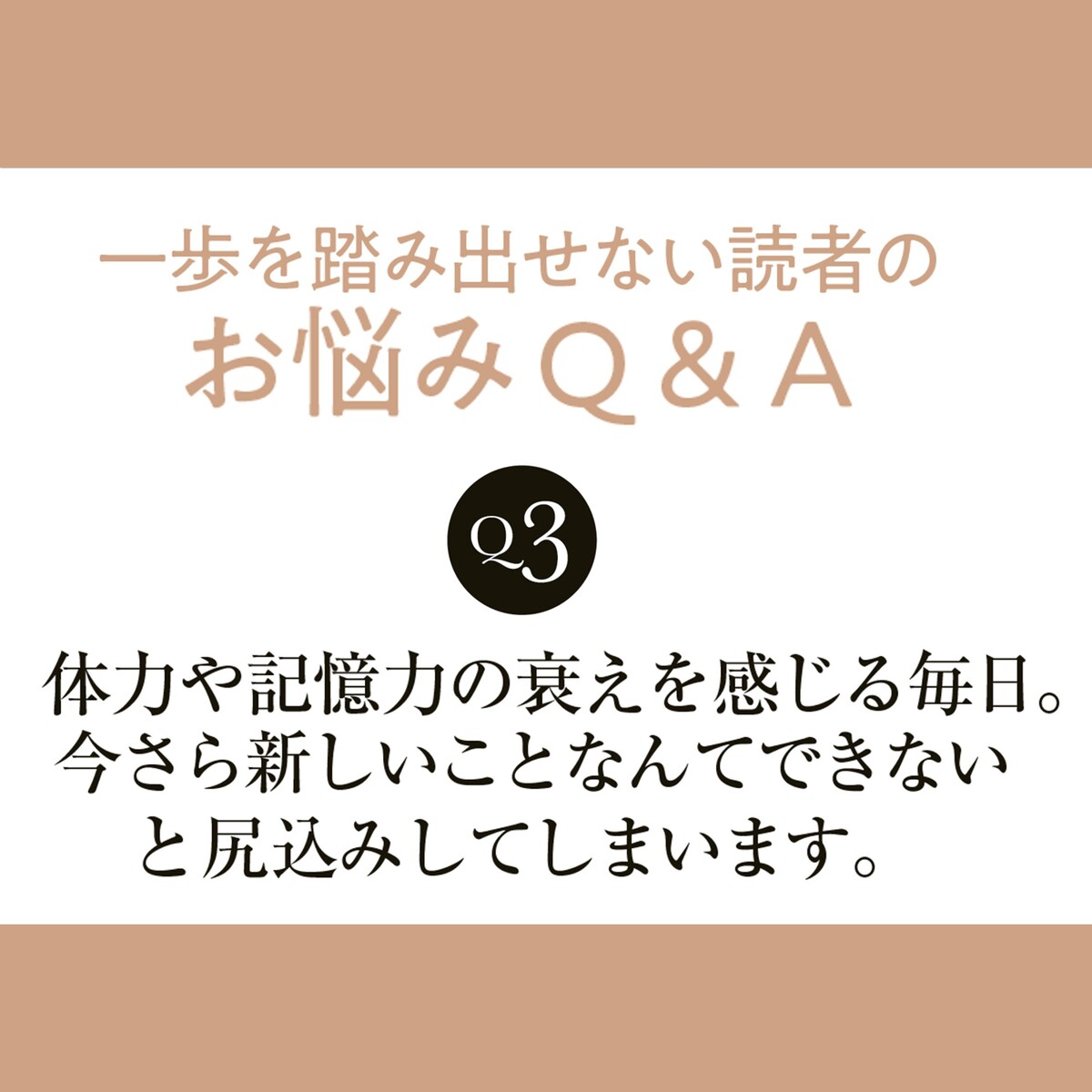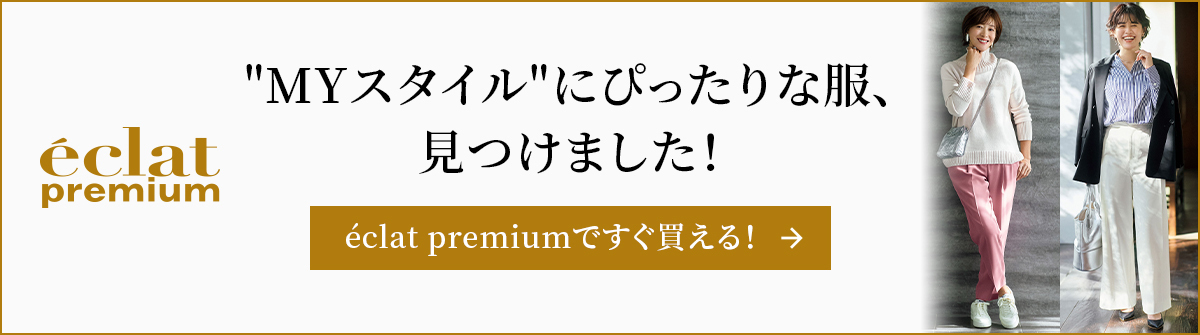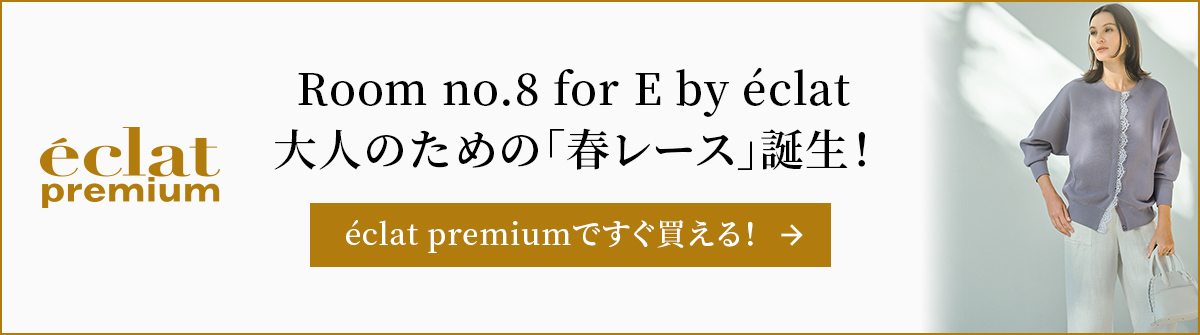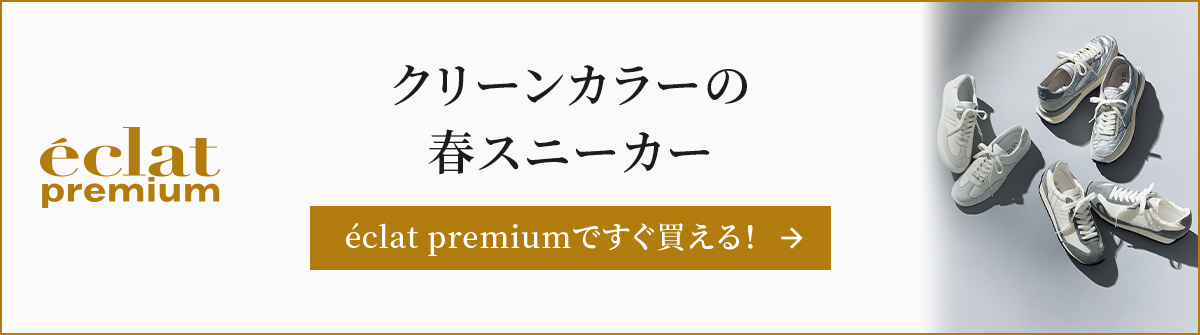知っているようで知らない親の人生。知りたいと思っていても、昔のことを語りたがらない親もいる。辻堂ゆめ『十の輪をくぐる』は、現代と’60年代、2つの時代を舞台にした、互いを知らない母と息子と孫娘の物語だ。
さいとう みなこ●文芸評論家。編集者を経て’94年『妊娠小説』でデビュー。その後、新聞や雑誌での文芸評論や書評などを執筆。『文章読本さん江』『趣味は読書。』『名作うしろ読み』『文庫解説ワンダーランド』『中古典のすすめ』ほか著書多数。近著は『忖度しません』(筑摩書房)。

『十の輪をくぐる』
辻堂ゆめ
小学館 ¥1,700
2019年10月、母の介護を妻に任せっぱなしの泰介は母に年中いらだっていたが、その母が妙なことをいいだした。思えば自分は母のことを何も知らない。幼いころに死んだ父のことも知らない。が、何を聞いても母は「昔のことは忘れた」というばかり。彼女は実は息子にいえない重大な秘密を隠していた。現代と’60年代、2つの時代を舞台にした、互いを知らない母と息子と孫娘の物語。
親の人生のこと、どこまで知っていますか?
親の人生は知っているようで知らない。もっと話を聞いておけばよかったなと思ったときには時すでに遅し。ただ、昔のことを頑として語らない親もいる。辻堂ゆめ『十の輪をくぐる』はそんな親子の物語だ。
佐藤泰介は58歳。大学卒業後、スミダスポーツなる会社で働き、もうじき定年を迎える。少年時代は有望なバレーボールの選手だったが、結局は平凡な人生を歩んでしまった。娘の萌子も高校バレーの選手、それも実業団からスカウトがくるほどの名アタッカーである。だが過去に悔いのある彼は娘の才能を素直に喜べない。
母の佐藤万津子は80歳。最近、認知症の症状が出て、ときどき意味不明なことを口走る。先日も母は妙なことをいいだした。
〈私は……東洋の魔女〉
東洋の魔女って1964年の東京オリンピックで優勝した、あのバレーボールチームのこと?
母は五輪に近いところにいたんじゃないかと妻の由佳子はいう。〈だって……お義母さんって、確か結婚前に紡績工場で働いてたんじゃなかった?〉〈もしかして、日紡貝塚(にちぼうかいづか)だったんじゃない?〉
母がバレーに熱中していたのは事実である。泰介自身、母の特訓と援助でバレーを続け、妻とも大学のバレー部で知りあったのだ。が、母の若いころの話は知らない。
かくして物語は2019年から1958年に一気に飛ぶ。当時、万津子は18歳。愛知県一宮市の紡績工場で働いていた。中学を出ると同時に生まれ故郷の熊本県荒尾市を出て、集団就職でここに来たのだ。彼女の唯一の楽しみは女子バレー部での活動だった。
えっ、じゃあもしかして……。
いいえ、残念でした。結論からいうと、万津子がいた工場は強豪の日紡貝塚ではなく、彼女は選手にもならなかった。しかし物語はこのあと、思いがけない方向に転がって、スポ根小説より深くて辛い人生の深淵に向かっていく。
なにより注目したいのは昭和30年代の時代背景。’64年の東京五輪が戦後復興を象徴する高度成長期の「正の側面」なら、万津子は同じ時代の「負の側面」をひとりで背負ったような女性なのだ。郷里に戻って彼女は炭鉱マンと見合い結婚するのだが、三井三池闘争あり、炭塵(たんじん)爆発事故あり、万津子もその波をもろにかぶる。
平成生まれの作者は歴史小説を書くようなつもりで、この時代の描写に臨んだのかもしれない。要素を盛り込みすぎたかなというウラミは残るものの、万津子が過去を決して語らなかった理由や泰介の切れやすさの原因が徐々に明かされていく過程はサスペンスフルで、ミステリーのよう。〈私は……東洋の魔女〉という謎の言葉の秘めたる意味に、読者は最後、深く納得するだろう。
あわせて読みたい!

『いなくなった私へ』
辻堂ゆめ
宝島社 ¥720
上条梨乃は人気女性シンガー。ある朝、目を覚ますと渋谷の路上で寝ていた。巨大電光掲示板には「上条梨乃さん、昨夜自殺」のテロップ。じゃあ私は誰? よくできた輪廻転生もの。作者は’92年生まれ。「このミステリーがすごい!」大賞で優秀賞を受賞した、’15年のデビュー作。

『私の青春 東洋の魔女と呼ばれて』
谷田絹子
三帆舎 ¥1,300
’20年12月4日に他界された、元五輪選手の青春記。作者は’39年生まれ。中学2年からバレーボールを始め、名門の四天王寺高校卒業後、ニチボー(日紡)貝塚に入部。’62年に世界選手権で優勝したあと、バレーはやめるつもりだったのに…。東洋の魔女の舞台裏が率直に語られる。