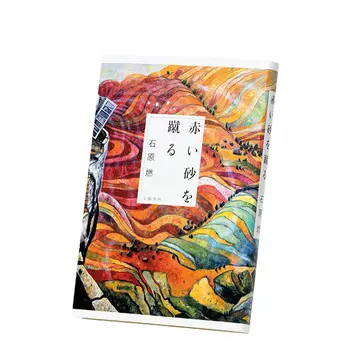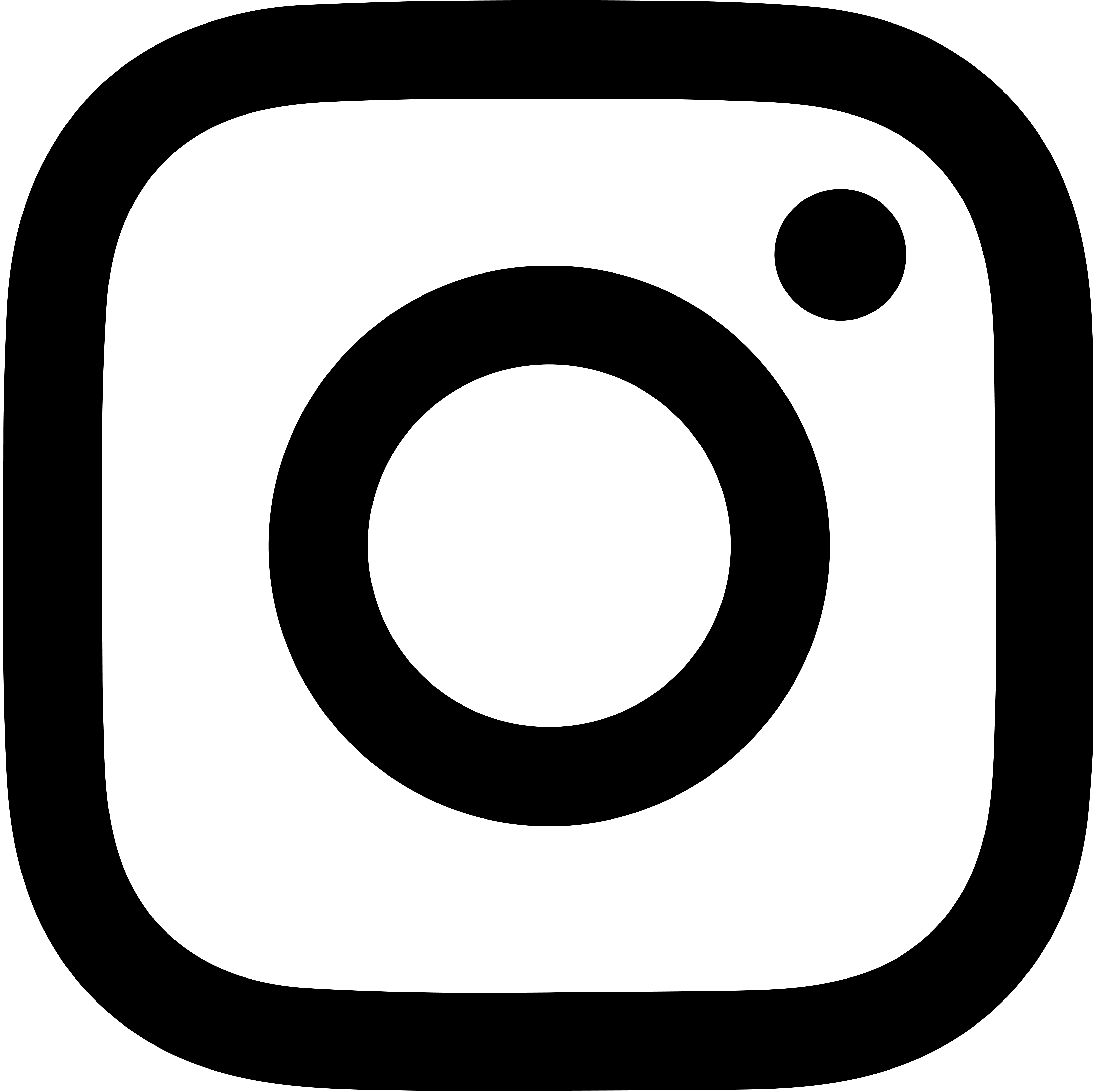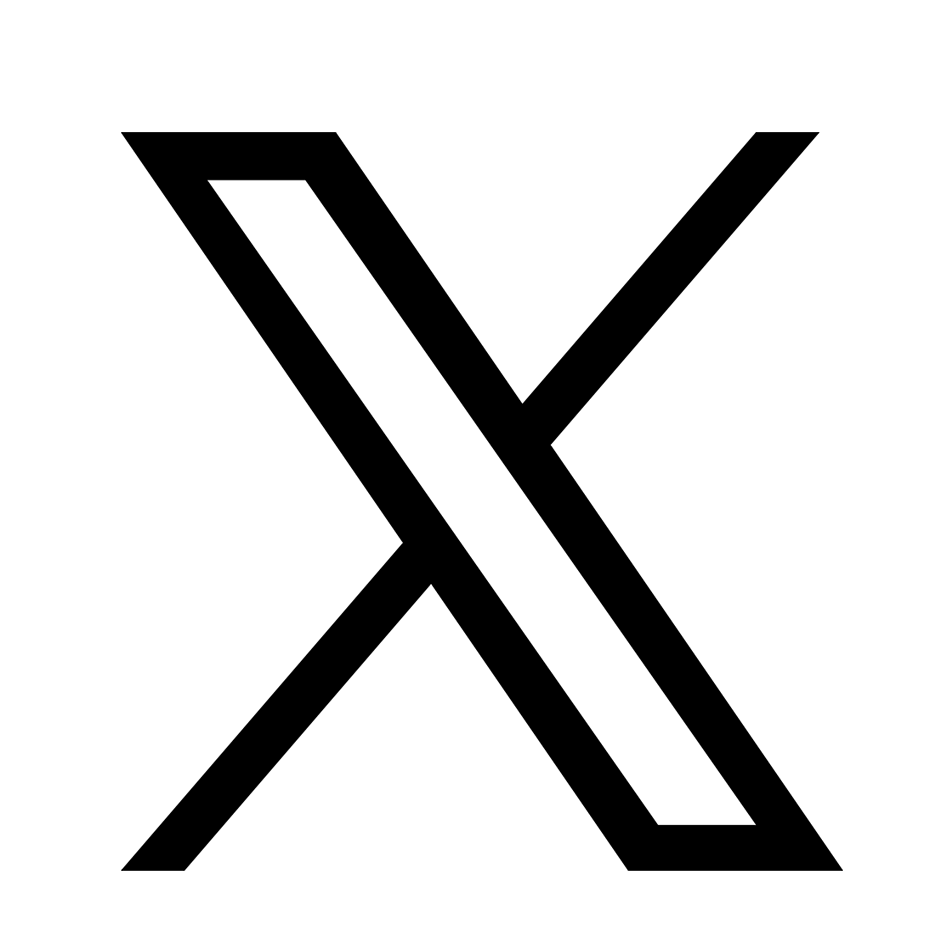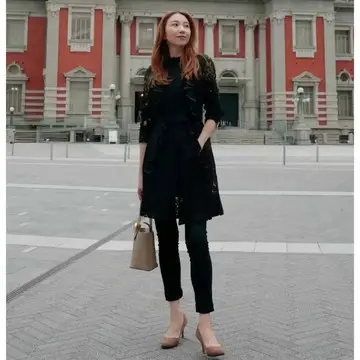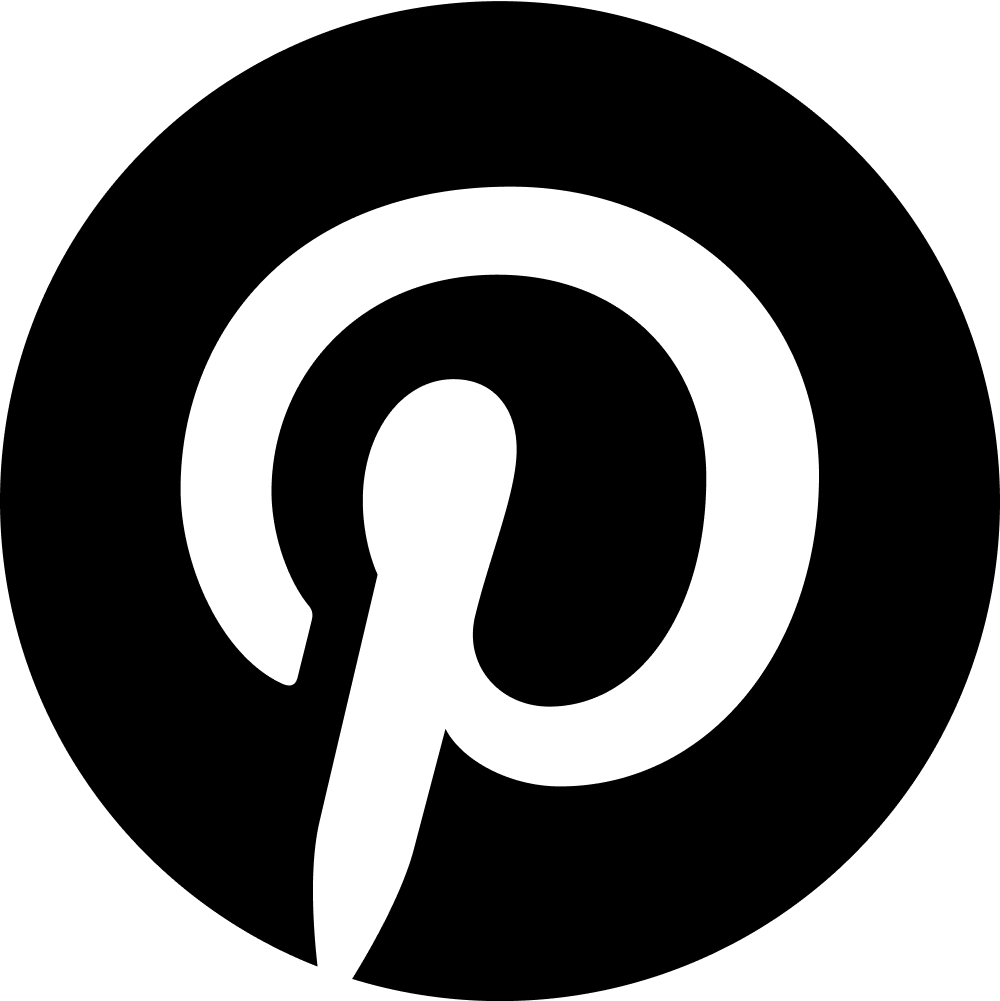魯肉飯、自分で作ったことありますか? 甘辛く煮た豚肉をごはんにのせた台湾風の丼だけど、レシピを見ると、味の決め手は八角か五香粉(ウーシャンフェン)みたい。で、「ルーローファン」というのは中国語風の読み方らしい。
温又柔(おんゆうじゅう)『魯肉飯のさえずり』の場合は台湾風に「ロバプン」と読む。母と娘の物語である。
深山桃嘉(ももか)は台湾人の母と日本人の父の間に生まれた。結婚して現在の姓は柏木。夫の聖司は大学の先輩で、就活に失敗した桃嘉は卒業と同時に結婚してしまったのだ。皆がうらやむ結婚だったが、最近夫は浮気をしているようで……。
そんなところから物語は始まるのだけれど、この夫はデリカシーがないのよね。妻が作った魯肉飯に、こいつはケチをつけるようなやつなのよ。〈こういうの日本人の口には合わないよ〉〈こういうものよりもふつうの料理のほうが俺は好きなんだよね〉。
じゃあ自分の飯は自分で作りなさいよ!と私だったら一喝するが、桃嘉はそういう不穏なことはいわず、〈きっと聖司は八角がだめなのだ〉と考えて、以来一度も魯肉飯は作っていない。
彼女は母に負い目があった。父と結婚して台湾から東京に来た母の雪穂(台湾名は秀雪)も、娘に負い目があった。雪穂は日本語がうまくなかったのである。日本語では自分の感情を十分に表現できない母。そんな母が不満な娘。
小学生のころ、桃嘉は雪穂が作ったおむすびを残して帰ったことがある。〈ママのオムスビ、なぜ食べない? おいしくない?〉と問う母に〈梅干しのおむすびなら、入るかも〉と娘は答えた。母が作ったおむすびの具は、干した豚肉を甘辛く煮つけた台湾の食材・肉燥(バーソー)だったのである。〈梅? どうしてバーソー、ダメ? 桃嘉、ママのつくるもの、きらい。だから食べない。そうなの?〉
温又柔自身も両親は台湾人。3歳から東京で暮らし、台湾語と中国語の交じった言葉で話す家庭で育った。これまでの作品も作者のアイデンティティに根ざしたものだったが、今度は異国で子育てをする母の視点も入って、ぐっと奥行きが出た感じ。
言葉とごはんは生活の根幹。そこで生じた齟齬は家族であってもなかなか埋まらない。それでも桃嘉は母の故郷の台湾で、伯母たちが話す半分意味のわからない言葉をピーチクパーチクという「さえずり」のように心地よく聞く。
〈ママ、日本人じゃない。だから桃嘉いや。でもしょうがない。ママ、台湾人。日本人なれない〉
魯肉飯は母の得意料理で、彼女にとっては「普通の料理」以上に思い入れのある料理だった。果たして母と娘はどんなかたちで和解するのか。そしてデリカシーのない浮気者の夫との関係は!