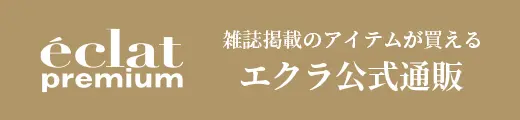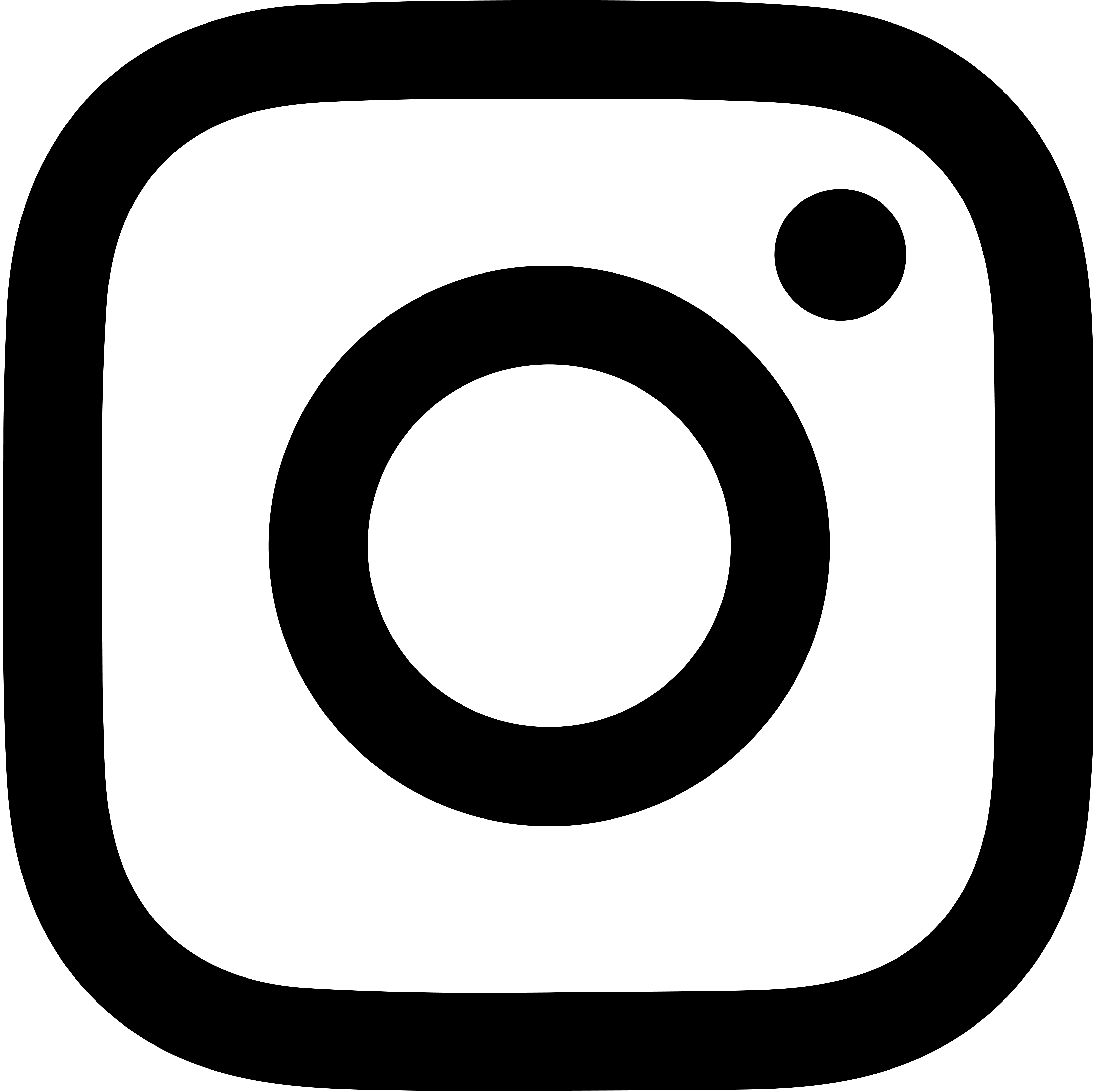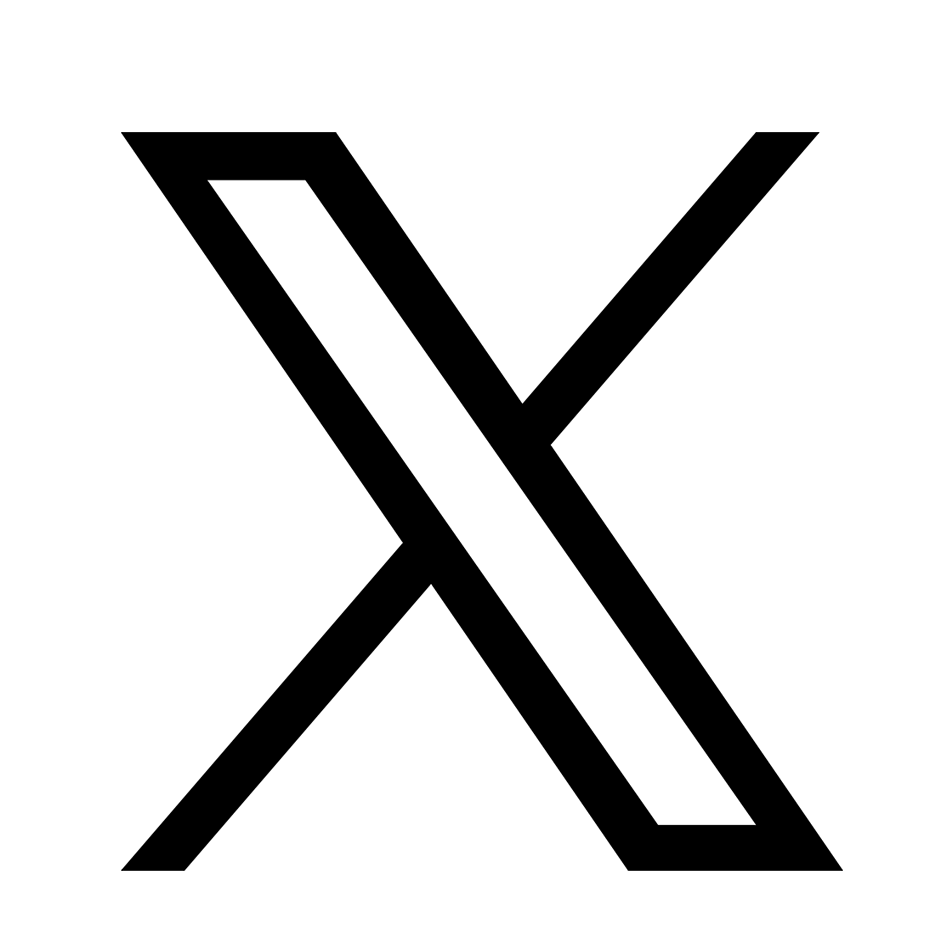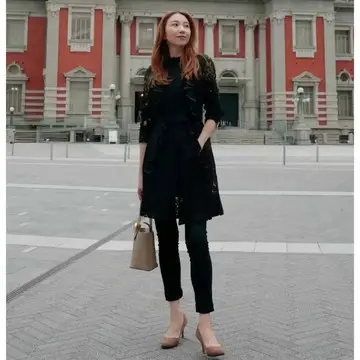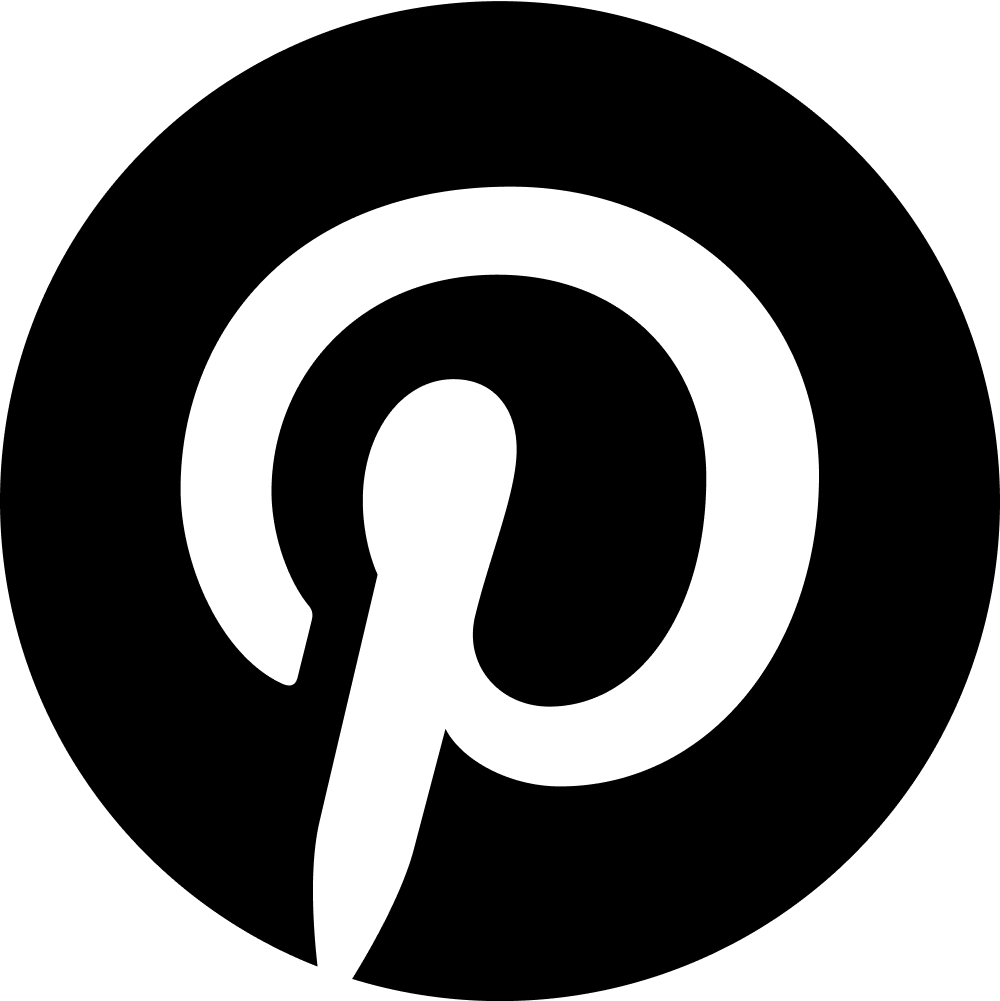こばやし たかのぶ●編集者。1967年福井県生まれ。扶桑社で雑誌『ESSE』『天然生活』などの編集長を歴任、俳優・石田ゆり子の『ハニオ日記』ほか多数の書籍を手がける。2023年、自身と家族の体験を綴った初の著書『妻が余命宣告されたとき、僕は保護犬を飼うことにした』(風鳴舎)が話題に。'24年に退社し編集事務所「yin+yang」を設立。福井新聞「月刊fu」で「犬と猫と人間(僕)の徒然なる日常」を連載中。
猫沢エミさん・小林孝延さんが見つめた、喪失と悲しみの向こう側。「愛した証拠」を抱えて、それでも生きていく
年齢を重ねて経験していく、大切な存在との永遠の別れ。死とは何か、そして生とは――。'25年11月に刊行された『真夜中のパリから夜明けの東京へ』は、パリと東京、1万キロの距離と時差を飛び越え交わした、大人の友人同士の往復書簡。率直な思いを綴り合ったミュージシャンで文筆家の猫沢エミさんと編集者の小林孝延さんが、晩秋の東京で再会した。

大切な相手を、いつかは必ず喪うという宿命
──もともとは雑誌『天然生活』の創刊時、連載執筆者と編集長として出会った猫沢さんと小林さん。時を経て再会したのは2021年の冬。それまでに、小林さんは両親と妻を、再会からほどなくして猫沢さんは愛猫と親友を、それぞれ亡くした。そして始まった、お互いの死生観をめぐる往復書簡。喪失で空いた心の空洞を抱えながら日常を送っていた2人は、お互いの言葉に誘われるように手紙を綴った。
猫沢 小林さんと再会する前に、うちの両親は、ほぼ同時にステージ4のがんであることが判明して立て続けに亡くなりました。猫のイオちゃんは難治性の扁平上皮がんになって1か月半で旅立ってしまいましたが、最期は私が安楽死を選択したんです。さらに、イオちゃんが逝った2日後には、親友も亡くなってしまって。
小林 その頃、僕も、母、父、妻を連続で見送ったタイミングでした。猫沢さんと再会してからは一緒にご飯を食べに行ったりして、仕事や他の話はしたけれど、あえてそこに触れる話はしなかったですよね。
猫沢 うん。疲れきった猫のような二人が、弱々しく笑いながら時間と空間を共有して、やりきれない気持ちを抱えてお酒を飲んでた。友だちだからこそ、逆に話さないで済んだのかもしれない。
小林 今回の本のテーマである、お互いの死生観についても、最初から最後まで手紙の中でだけ。直接話すのは今日がはじめて、というくらいです。
猫沢 往復書簡の最初、死の考察から書き始めた頃は、私、夜中にしか書くことができなかったんですよ。夜中に書き始めて、明け方になる頃までに書き終わる感じ。
小林 僕も、昼間、ノイズのある時間帯には書けなかったので、旅先やキャンプのテントの中から。猫沢さんに手紙を書くのは、自分の心のデリケートな部分にカメラ付きのカテーテルを入れていくような感覚でした。猫沢さんから見ても、きっと僕の本音は見えにくかったでしょうね。
猫沢 自分の感情や気持ちを言語化するのは、やっぱり男性はあまり得意じゃないのかも? でも、『つまぼく』(小林さんの著書『妻が余命宣告されたとき、僕は保護犬を飼うことにした』)を読んだとき、なんて小林さんらしい本だろう!と感じたし、全部を語らないところに余白が生まれて、そこに同じ痛みを経験した読者のかたが集ったんだと思いましたよ。
小林 ありがとうございます。あの本の中には書けなかった部分を、今回、猫沢さんへのお手紙という形を借りて書けたんじゃないかと思っています。後悔や、家族に対して申し訳なかったと思う部分など、猫沢さんになら伝えられるんじゃないかと思いながら。
猫沢 ぶっちゃけ、伴侶を亡くされた小林さんと猫のイオちゃんを見送った自分が、はたして同じ舞台に立てるのか?とも思っていたんです。でも、相手が何にせよ、絶対に失えないはずの存在を、人生の中では誰もが必ず失う宿命を持っていて、それでも生きていかなくちゃいけない……そんなことが、50歳を過ぎるとリアルに多くなってくるんですよね。

悲しみが癒えていくことに、罪悪感を持たないで
──ときには、ストレートな「豪速球」を。ときには、緩いカーブを描くように。生と死を巡る2人の言葉のラリーからは、お互いの心に響くフレーズが数々生まれた。
小林 猫沢さんが書かれた言葉でとくに印象に残っているのは、〈傷も心に空いた穴も、決して癒えたり消えたりはしない。ただ、その跡に新しい何かが芽吹いて緑地化していく〉。実は僕、猫沢さんはイオちゃんを失った喪失の時点から今も動けないでいるのでは?と思っていたんです。でも、猫沢さんにも少しずつ変化が訪れているんだということを知り、すごく希望を感じました。
猫沢 もちろん、今でも日常のふとした瞬間にイオちゃんのことを思い出して、すごく悲しくなったりもします。でも、小林さんがいつか「歳を重ねると辛いことや悲しいことが “切ない”って感情に置き換えられて、だんだん気持ちよくなってくる」って言ってたじゃない? それと同じように、私も「こんなに切なくなれるなんて、すごく豊かな人生だ」と思ったりして……。愛する存在をどんなに頑張って見送ったとしても、「もっとできたんじゃないか?」という悔いは必ず残るもの。だけどそれは、「失えない!」と必死になれるほどの愛情があったからこそ自分に返ってきたものなんだろうなと。
小林 そうですね。そんなふうに思えるようになるまでには、僕も時間がずいぶんかかりました。
猫沢 最初は、辛さが遠ざかって行くことすら辛い。でも、だんだん癒えていくっていうことに対しての罪悪感は持たなくていいんじゃないか、というのも感じました。それは、喪った相手の存在が自分の心の深いところに降りていくという、遺された人の立ち直りの形なんじゃないか?って。

ただ傍にいる。あとは、時間が何とかしてくれる
──静かな時間と空間で、ひととき、心の扉を開いて思いを分かち合える。そんな相手を、どうやったら見つけられるのだろう? 2人の往復書簡を読むと、きっと誰もがそう思うはず。そして、誰かのそんな存在に、自分はどうやったらなれるのだろうか、とも。
猫沢 難しいですよね。今、暮らしているパリでフランス人に「私、こういうことがあって……」と話すと、すぐに「あ、それについての僕の意見はね……」って、めっちゃ被せてくるんだ! だから、最後まで話を聞いてもらうには、お金を払ってカウンセリングに行くしかない(笑)。
小林 ハハハ。日本でもありがちですよ。「そうなんだ。私の場合は……」って、あれ、俺の話どっかに行っちゃった?みたいな。
猫沢 「すごく辛いんでしょ、何でも言って!」なんて言うくせに、私が話している最中にわーっと泣き出して、「私はエミちゃんよりぜんぜんマシだわ」と、スッキリして去っていく人もいましたからねぇ。そういう人を私は「涙どろぼう」って呼んでますけど(笑)。
小林 自分の意見はさておき、まずは聞いてあげることですよね。そんなに簡単に解決できることじゃないから苦しくて、話しているわけですから。
猫沢 ついこの間も20年来の友人夫婦の奥様がお亡くなりになったんですが、残された旦那様に対して私ができることは「いつでも連絡して」と伝えて、それになるべく早くレスポンスをすること。そして、「ひとりじゃないよ」と言い続けることくらいでした。
小林 そう、ただ静かに「傍にいるよ」と伝えること。
猫沢 あとは、時間が何とかしてくれる。つくづく、小林さんと私は、お互いが患者でお互いがカウンセラーという、特殊な関係だったんだなぁと思います。
──2人は昨年、50代からの生き方を考える会員制オンラインサロン「バー猫林」を開設。大人世代を中心とした仲間たちとゆるやかにつながりながら、対話を続けている。
小林 テーマは「50代、60代に向けてどんなイメージを描きながら生きていくか」。たまに会員のかたから質問が来たりして、我々、わりと「やりたいことやっちゃえよ!」みたいな、身も蓋もない答え方をしていますよね。
猫沢 とくに小林さんがね(笑)。私はもともとそういう生き方しかできない人間だけど、小林さんまでいきなり会社辞めちゃって、完全にこっち側の人になっちゃったから。
小林 アドバイスしようにも、すでに「あの人たちに訊いてもね……」みたいな雰囲気に(笑)。でも、この間も、「仕事を辞めて、世界旅行に行きました!」という会員さんがいましたよ。「やっと自分の人生を歩み出せた気がする」という感謝のメッセージつきで。
猫沢 それならよかった。そう、そういうものなんだよね。年齢が上がれば上がるほど、一歩を踏み出す前は当然、リスクのほうをまず計算してしまうけど、やっちまえば意外と何とかなる! 小林さんなんて、ぜんぜん後悔がなさそうだし、生き生きして、お肌までツルツルになってきて。ここから先は、50代からのはっちゃけ書簡でも続けますか?
小林 「飛び出せ五十路」!
猫沢 アハハハ。人生100年時代ですもん。人間、誰もがそうやって今まで生きて死んできたんだから、大丈夫!って思えますよね。
ねこざわ えみ●ミュージシャン、文筆家。1970年福島県生まれ。90年代より音楽活動を開始。2002年に渡仏、帰国後より執筆活動を本格化。近著に『ねこしき 哀しくてもおなかは空くし、明日はちゃんとやってくる』『イオビエ〜イオがくれた幸せへの切符』(TAC出版)、『猫と生きる。-LA VIE AVEC UN CHAT』(扶桑社)、『猫沢家の一族』(集英社)など。’22年より再びパリ在住。超実践型フランス語教室『にゃんフラ』主宰。
こばやし たかのぶ●編集者。1967年福井県生まれ。扶桑社で雑誌『ESSE』『天然生活』などの編集長を歴任、俳優・石田ゆり子の『ハニオ日記』ほか多数の書籍を手がける。2023年、自身と家族の体験を綴った初の著書『妻が余命宣告されたとき、僕は保護犬を飼うことにした』(風鳴舎)が話題に。'24年に退社し編集事務所「yin+yang」を設立。福井新聞「月刊fu」で「犬と猫と人間(僕)の徒然なる日常」を連載中。
こばやし たかのぶ●編集者。1967年福井県生まれ。扶桑社で雑誌『ESSE』『天然生活』などの編集長を歴任、俳優・石田ゆり子の『ハニオ日記』ほか多数の書籍を手がける。2023年、自身と家族の体験を綴った初の著書『妻が余命宣告されたとき、僕は保護犬を飼うことにした』(風鳴舎)が話題に。'24年に退社し編集事務所「yin+yang」を設立。福井新聞「月刊fu」で「犬と猫と人間(僕)の徒然なる日常」を連載中。
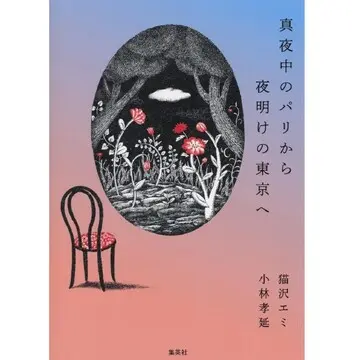
『真夜中のパリから夜明けの東京へ』
書くことによって自分自身を救わなければならなかった――。最愛の伴侶を喪った悲しみを見つめながら、死と生、そのあわいに揺れる希望を模索し綴った2人の魂の軌跡。心を覆う夜の闇に光が差す、そんなフレーズに、きっと出会えるはず。
集英社 ¥1,870
集英社 ¥1,870
合わせて読みたい
-
進化中の「歴史エンタメ」。老後、街づくり、文明の対立……現代に通ずるテーマで魅了!
新たな気づきを得られる没入感間違いなしの「歴史エンタメ」をエクラ編集部がセレクト!今回は現代にも通じる、老後、街づくり、文明の対立をテーマにした作品に注目。
-
『国宝』だけじゃない!江戸の“芝居もの”が静かにアツい【旬の「歴史エンタメ」】
2025年の新語・流行語大賞にトップ10入りを果たした「国宝」。そのほかにも、Netflixで配信中の「イクサガミ」や2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟!』など、歴史エンタメはほかにもたくさん。数ある歴史エンタメの中から、今回はエクラ編集部がピックアップした「江戸の"芝居もの”作品」をご紹介。
-
2026年の大河ドラマで再注目!“豊臣もの”小説を作家・今村翔吾さんがセレクト
’26年の大河ドラマ『豊臣兄弟!』をはじめ、いま話題の歴史エンタメ。今回は、作家・今村翔吾さんが選んだ、新たな気づきを得られる没入間違いなしの作品を紹介。
-
【今50代が読みたい本】読み始めたら止まらない!? 読書時間が充実する本4選
エクラ世代におすすめしたい書籍を厳選! 昭和元年からの100年を駆け足で旅したような、圧倒的感動に包まれる『百年の時効』、生きのびる力を磨く、愉快な科学エッセー『とんでもないサバイバルの科学』など4冊を厳選。
-
綿矢りさの新境地、傑作"GL小説"『激しく煌(きら)めく短い命』【斎藤美奈子のオトナの文藝部】
京都と東京を舞台に描く、綿矢りさの傑作"GL小説"『激しく煌(きら)めく短い命』を紹介。同じく京都を舞台にした綿矢りさ『手のひらの京(みやこ)』、女性同士の恋愛を描いた、中山可穂の先駆的な短編集『花伽藍』もあわせて読みたい。
What's New
-
“女流”の時代を生きた、3人の女性作家を描く『三頭の蝶の道』【斎藤美奈子のオトナの文藝部】
山田詠美の『三頭の蝶の道』を紹介。実在の女性作家をモデルにフィクションも混じえて描いた小説は、読み応えたっぷり。山田詠美『もの想う時、ものを書く』、瀬戸内寂聴『笑って生ききる 寂聴流 悔いのない人生のコツ 増補版』とあわせて読みたい。
カルチャー
2025年12月16日
-
愛国主義、それは自分の国を愛すること、国粋主義、それは他国を憎むことである。ーLe patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres.【フランスの美しい言葉 vol.46】
読むだけで心が軽くなったり、気分がアガったり、ハッとさせられたり。そんな美しいフランスの言葉を毎週月曜日にお届けします。ページ下の音声ボタンをクリックして、ぜひ一緒にフランス語を声に出してみて。
カルチャー
2025年12月15日
-
玄関やリビングに…お客さまを出迎える花の飾り方【花生師・岡本典子さんに教わる"花あしらい”】
年末年始に向けて、ゲストを迎える機会も増えてきたのでは? 今回は人気の花生師・岡本典子さんに、一年の節目にふさわしい花あしらいのコツを伝授していただきました。
カルチャー
2025年12月14日
-
誰もが知る歴史のイメージが変わる!?"あの戦乱”に新解釈【旬の「歴史エンタメ」】
その時代の魅力に現代のセンスが加わり、歴史を新鮮な視点で楽しむエンターテインメントが続々!「歴史エンタメ」が注目されている今、改めて見直したい映画2作品と歴史上の人物を新たな視点で描いた本をご紹介。
カルチャー
2025年12月13日
-
進化中の「歴史エンタメ」。老後、街づくり、文明の対立……現代に通ずるテーマで魅了!
新たな気づきを得られる没入感間違いなしの「歴史エンタメ」をエクラ編集部がセレクト!今回は現代にも通じる、老後、街づくり、文明の対立をテーマにした作品に注目。
カルチャー
2025年12月12日
-
-
-
-
-
-
オフィス内でも温度調整しやすい便利なカーディガンは、カフスつきトップスと重ねてモード感をアップ!気温11℃|12/16(火)【50代の毎日コーデ】
カフスつきプルオーバーにカーディガンを重ね着。カーディガンのずらっと並ぶボタンと、白いロングカフスのディテールが掛け合わさることで、単品で着るよりもさらにモードなシャレ感が生まれる。
Feature
-
読者モデル 華組のZARAコーデ
50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集
-
エクラ公式通販の人気アイテムランキング
もう迷わない!50代が買うべき秋の服
-
読者モデル 華組のユニクロ・GUコーデ
真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集
-
松井陽子の「エクラ ゴルフ部へようこそ!」
松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。
-
一度は泊まりたい!高級ホテル・旅館
日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ
-
大人のためのヘアスタイル・髪型カタログ
髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル
-
クリスマスのお出かけスポットはここ!
映画「ハリー・ポッター」の世界に没入!大人も楽しめるアート体験
-
大人のきれいめデニムを探しているなら
イタリアの感性と日本の職人技の美しき融合、ジーフランコのデニム
-
50代におすすめのトレンドアイテム
人気ファッションアイテムを厳選してご紹介
-
「幹細胞コスメ」大人の最適解とは?
シミ、シワ、たるみ、毛穴悩みに。大人肌のスキンケアの最適解
-
年末年始の華やぎシーンは自信のある髪で!
人気ヘアマスク「Gyutto(ギュット)」で美映え髪に
Ranking
-
50代に人気上昇中!上品な華やかさ「冬のミディアムヘア」51選
冬の空気に似合うのは、品よく華やかで、ほんのり女らしさを感じるミディアムヘア。50代の女性に人気上昇中のスタイルは、髪悩みや顔まわりの悩みをカバーしながら、印象をぐっと明るく見せてくれるスタイル。
-
上品にあか抜ける「50代の黒タートル」冬の洗練スタイル8選
黒タートルは冬の定番アイテム。着こなし次第で品格を引き立て、あか抜けた印象をつくる最強の一枚。色合わせや素材感、アクセサリーの工夫次第で、ぐっと洗練されたスタイルに。
-
【憧れの国内高級ホテル・旅館】一度は泊まりたい!北海道から沖縄まで大人が満足する極上ステイ
50代女性が一度は泊まってみたい、と思う全国の高級旅館・高級ホテル・憧れのリゾートホテルを厳選してお届け。温泉やグルメやエステ、絶景など魅力満載の贅沢な国内旅行が楽しめる。夫婦や気心の知れた女友だち、…
-
【50代のブーツコーデ6選】この冬使える!ショートからロングまでどんなボトムスにもなじむ"万能な黒ブーツ”
寒い冬に欠かせないおしゃれアイテム「ブーツ」。単なる寒さ対策だけでなく、コーディネートのアクセントとしても大活躍!そこで今回はおしゃれなアラフィー読者モデル エクラ華組のブログから、冬のブーツコーデを…
-
【新作韓国ドラマ 2025年12月】「愛の不時着」監督の新作サスペンス、ジュノ(2PM)出演作品も!「Netflix」で観たい2作品
思いもよらない展開や手に汗握るスリリングなストーリー、そして俳優たちの圧倒的な演技力で、常に私たちを魅了する「韓国ドラマ」。今回は、いま話題の2作品をご紹介。年末年始の一気見もおすすめ! いずれも「Net…
Keywords