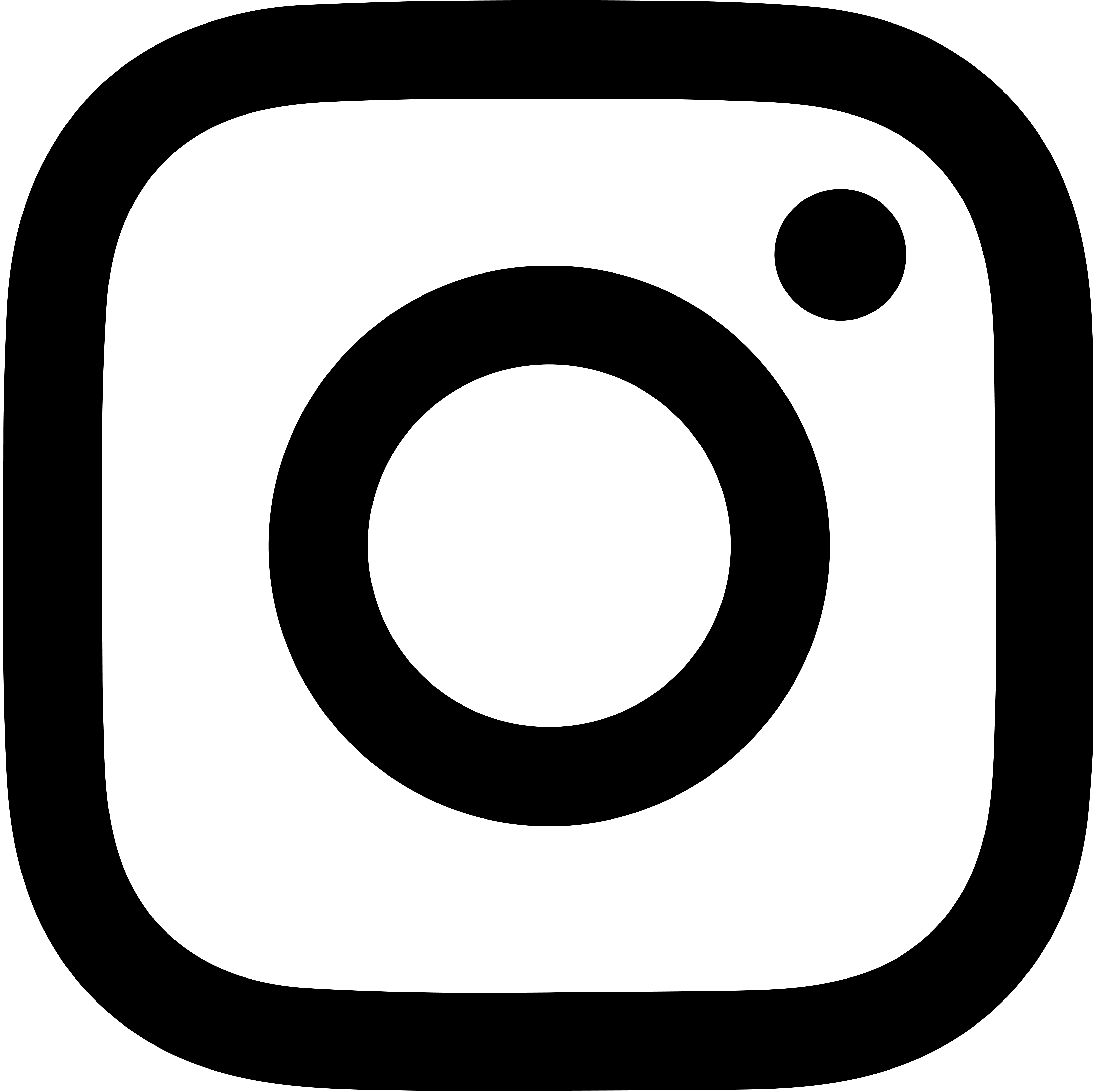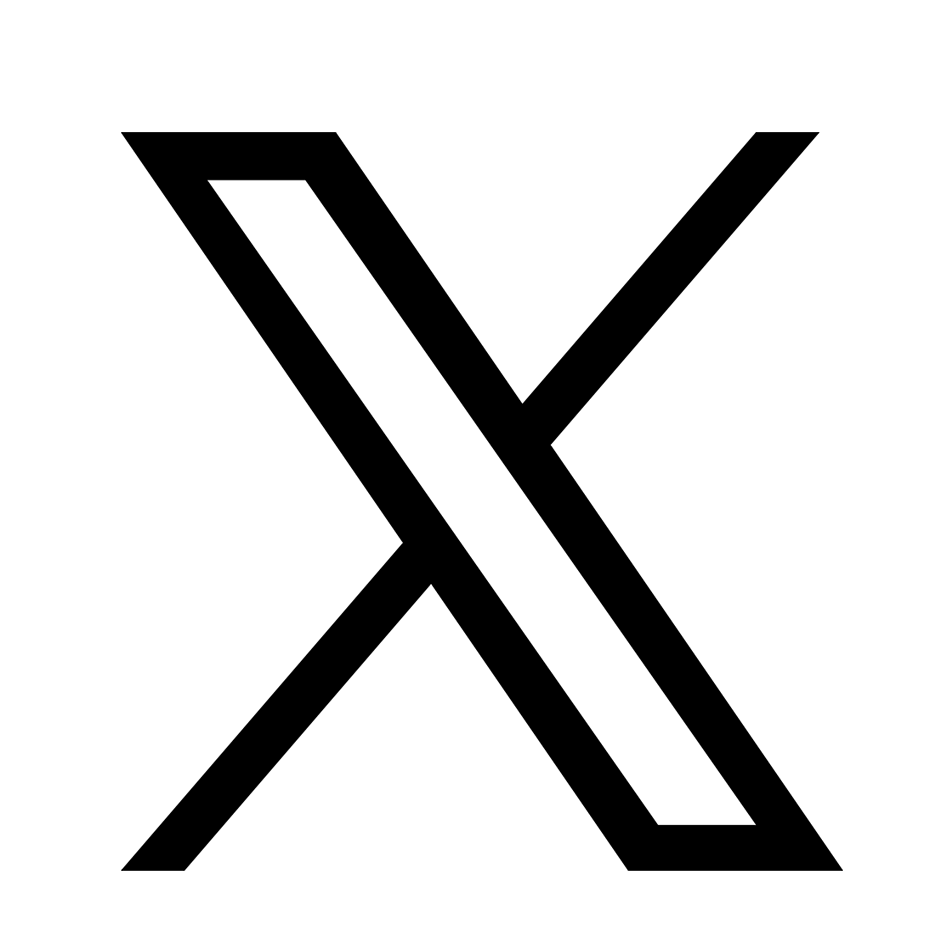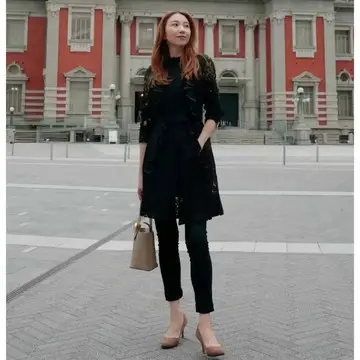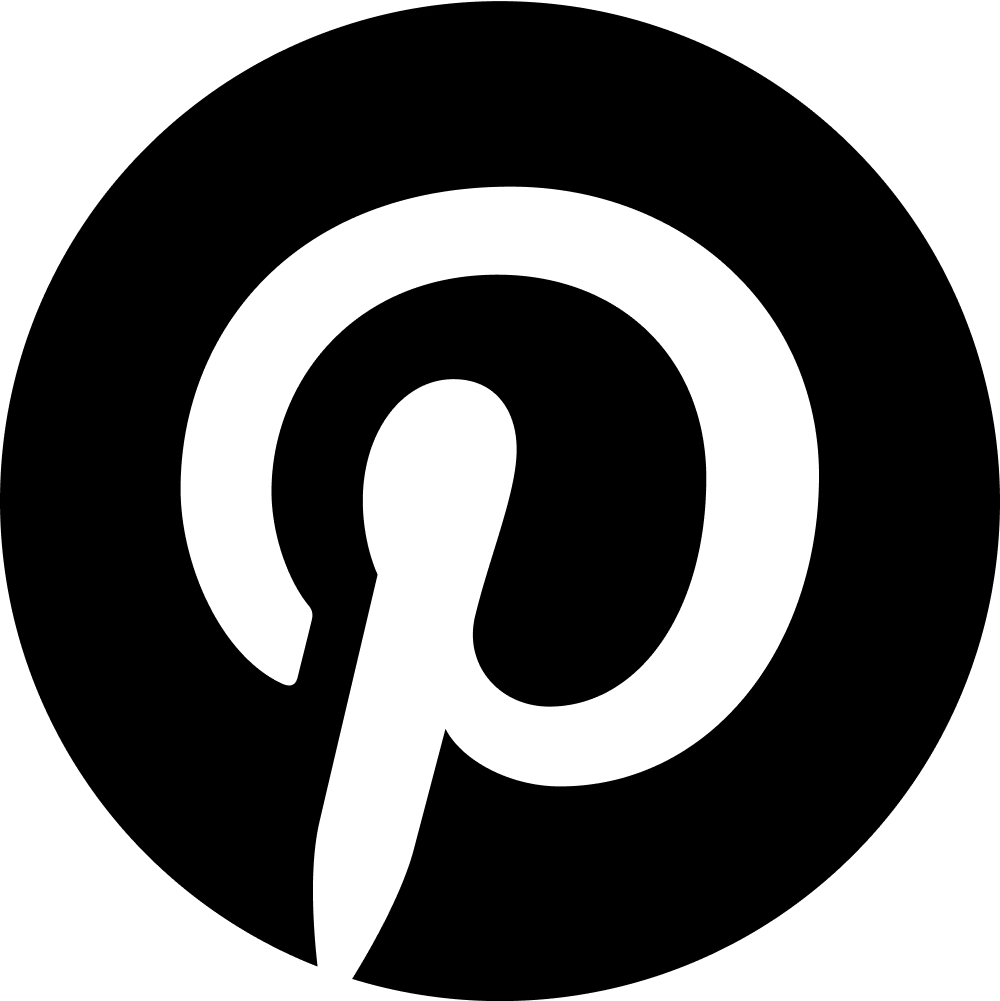ちょうど今、北の丸公園にある東京国立近代美術館・工芸館では、『The 備前 土と炎から生まれる造形美』が開催中です。
備前焼は基本的に無釉の焼締陶で、古くから壺、甕、擂鉢など、日用の雑器が作られてきました。やがてその素朴な表情と薪窯の中で生じる「窯変」の景色が茶人に喜ばれるようになり、桃山時代には数多くの名品が誕生しています。これら茶陶としての注文品は、織部以降の「歪み」を尊ぶ造形感覚に基づくものでした。
現代の作家さんには、それら桃山以前の「古備前」に学ぶ人もあれば、土の美質を生かしたオブジェ的な作品を手がける人もあり、展覧会では備前焼の歴史と多様な現状を知ることができます。
料理の分野で「素材に手を加えすぎず」「素材の持ち味をいかして」などと言いますが、備前焼も、そんなふうに"素材"を尊ぶやきもののひとつ。出来上がりの計算はもちろんしますが、あくまで「窯で土を焼く」という行為の延長上。加飾要素もある程度、窯にまかせます。降りかかった薪の灰がガラス化して黄色く残った「胡麻」、灰などの中に埋もれたせいで還元焼成によって土の色が灰色になる「桟切(さんぎり)」、それらを別の器などで遮ることで生まれる「抜け」、器同士がくっつかないように差しはさんだ藁による線状の赤い呈色「緋襷(ひだすき)」などが、時に人為を超えた幽玄な表情を見せてくれます。
さて、下の画像スライダーには、合計8つの展示作品が出てきます。
その内訳は古備前が4つ、現代作が4つ。どうぞ、備前焼の目利きに挑戦してみてください(※答えは画像の下にありますので、スクロールしすぎないようご注意を)。