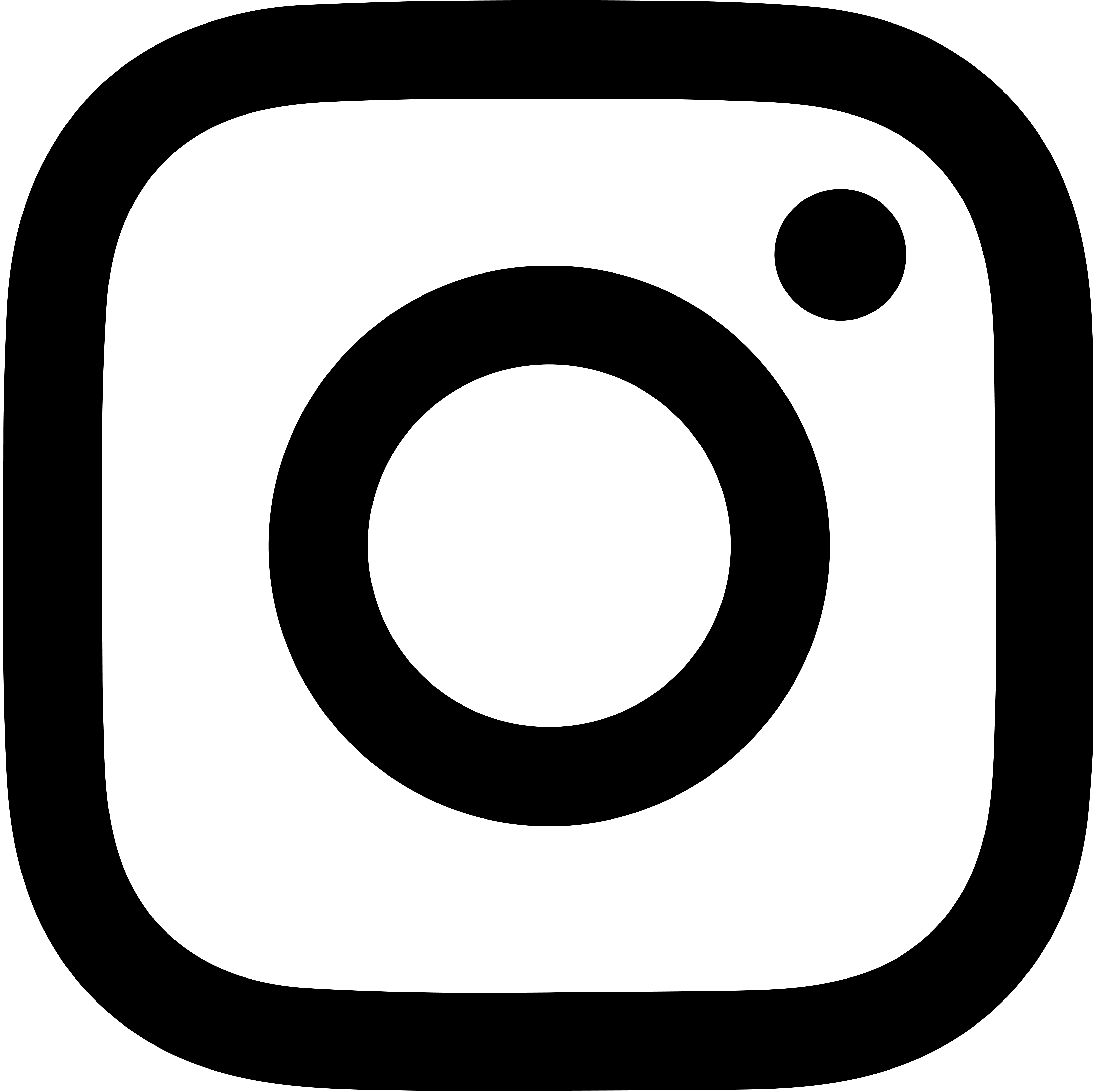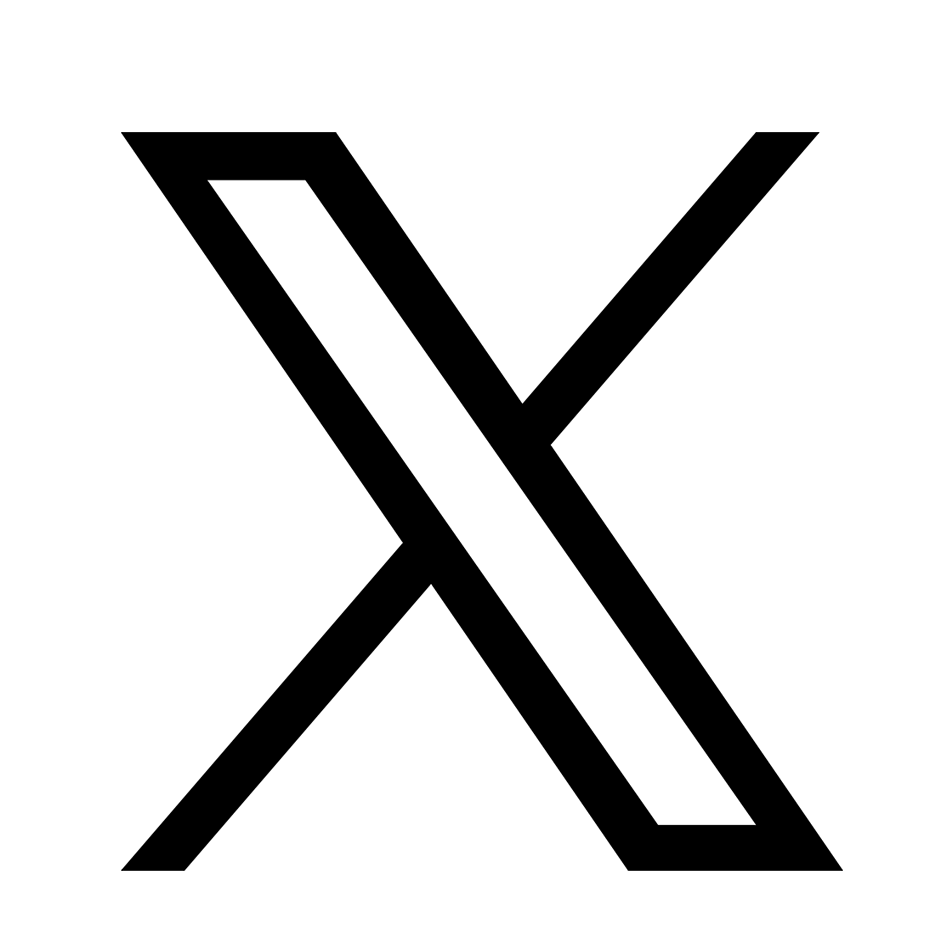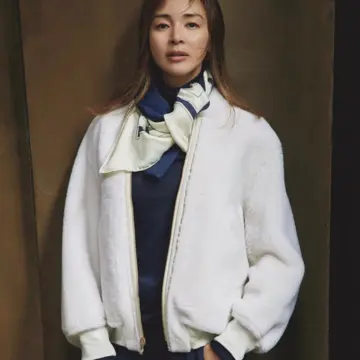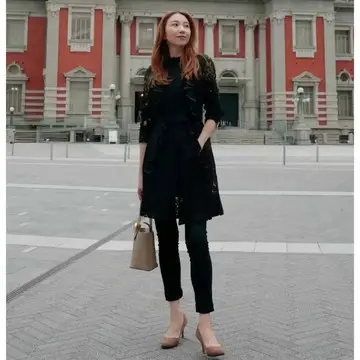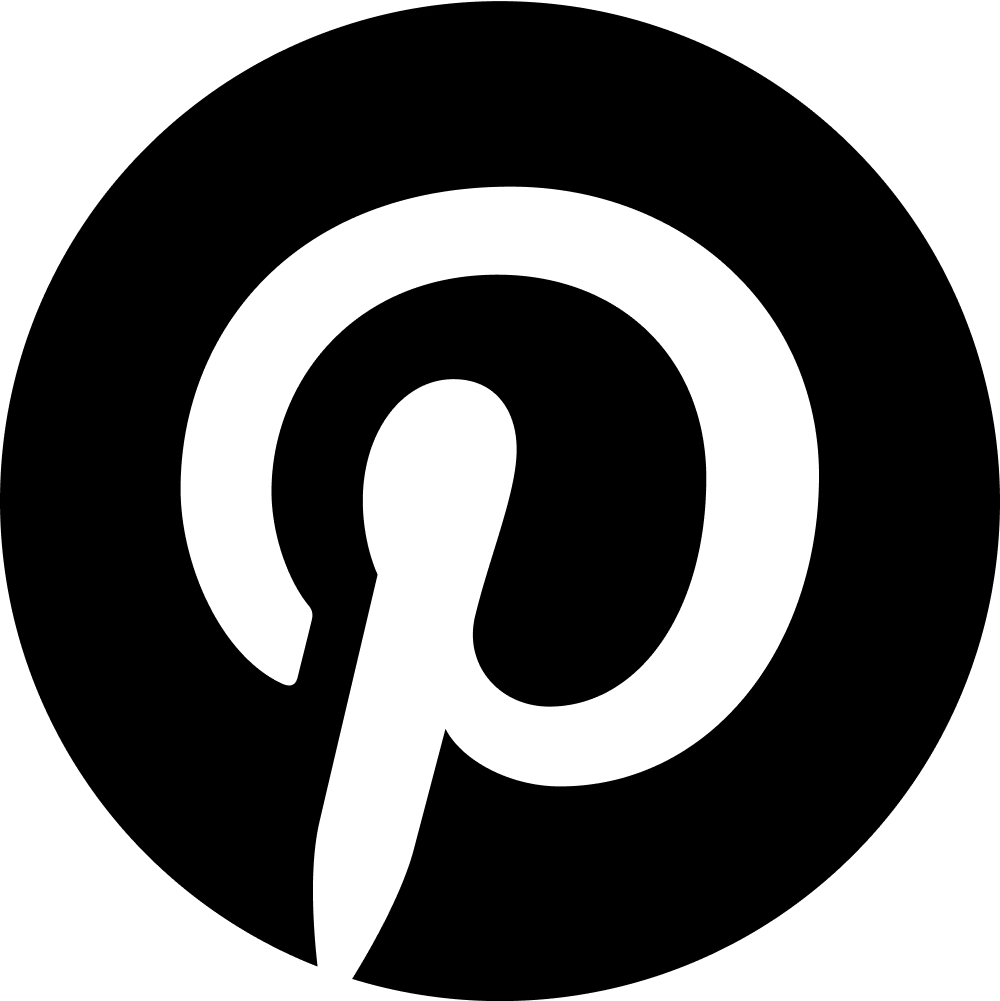東京オリンピック・パラリンピックを控え、なんだか浮き足立っている東京。
だが、その陰ではオリンピックの負の側面ともいうべき報道されない事実も多い。新国立競技場の建設にともなって取り壊され、古くからの住人が強制退去させられた都営霞ヶ丘アパートもそのひとつ。ここは前の東京五輪を控えた’60年代初頭に、古い長屋を壊してつくられた団地だった。
森谷明子『涼子点景1964』の舞台はその都営霞ヶ丘アパート(通称霞ヶ丘団地)の周辺である。時はまさに前の東京五輪が開かれた’64年。焦点となる人物は小野田涼子。’48年生まれ。国立競技場に近い新宿区内の小学校に転入し、学区内の中学に入学するも、卒業を待たずに転出した謎めいた少女である。
物語の発端は、万引きの疑いをかけられた小学4年生の曽根健太が涼子の証言と機転で助けられたことだった。同級生の高橋太郎はその話を聞いて驚く。
〈どこで? どこで涼子お姉さんに会えたの? お姉さん、この辺にいるの? ぼくはもうずっと会えないと思っていたのに!〉
住んでいる場所も、今はどうしているかもわからない涼子。だが健太の兄の幸一は、涼子が同じ中学の同学年だったことを思い出す。弟たちにとっては正義の味方らしい涼子だが、かつての同級生たちの評判は芳しくない。
〈好きじゃなかったのよね、あの子。クラスで浮いてたでしょ〉
涼子に関する謎はその後ますます深まる。幸一が覚えている小野田涼子は、成績は優秀だが給食費や副教本代も払えないような貧しい家庭の子供だったが、最近目撃された涼子は「お嬢様」と呼ばれ、黒塗りの自動車の後部座席に乗っていたという。数年の間にいったい何があったのか。
長編ミステリと謳(うた)われてはいるものの、いわゆるミステリとはひと味もふた味も違っている。
やがて明らかになるのは、涼子が取り壊された霞ヶ丘の長屋の住人だったこと。飲んだくれだった父が失踪し、母も姿を消し、涼子は祖母に引き取られたこと。長屋の跡にできた霞ヶ丘団地には太郎の一家が住んでおり、涼子は鍵っ子の太郎の面倒をみると称してたびたび団地を訪れていたこと。
失踪した涼子の父は誰かに殺されたのではないかという疑惑をちらつかせつつ物語は進行するのだが、それ以上にミステリアスなのは小野田涼子その人だ。貧しい家庭に生まれながらも、時に威勢のいい啖呵(たんか)を切り、時に『小公女』の主人公セーラのように毅然とふるまう少女。土地の売買がからんだ大人たちの思惑、母や祖母にまつわる誰にも明かせない秘密。ラストまで一気読み確実の、良質なエンターテインメント小説だ。