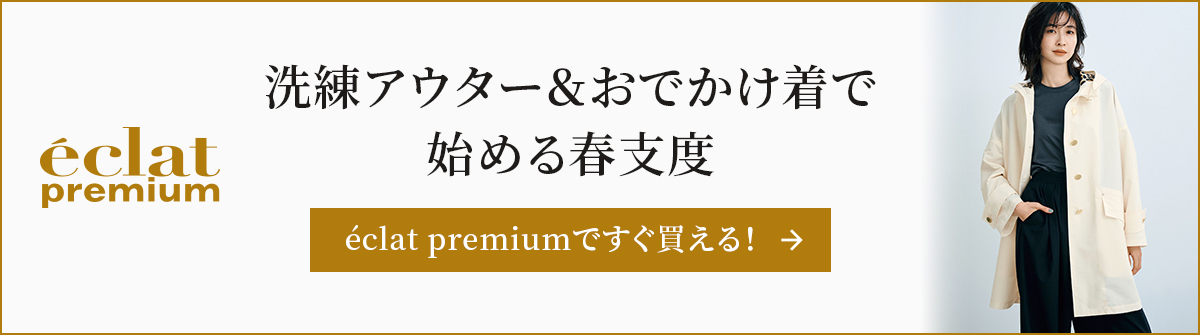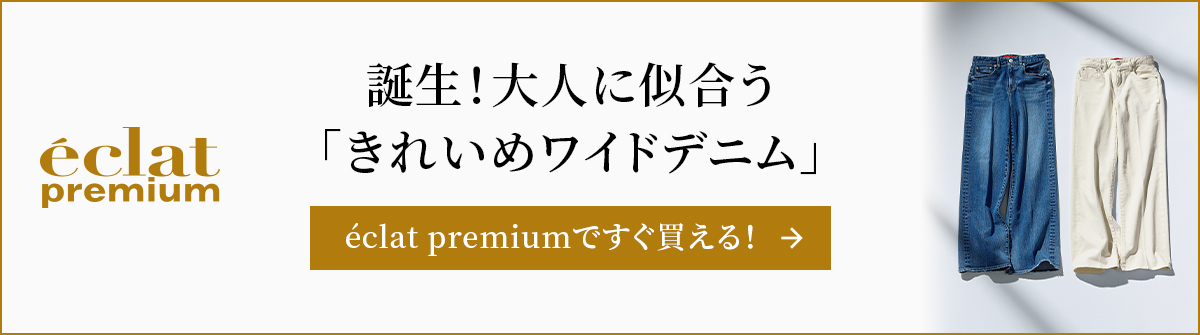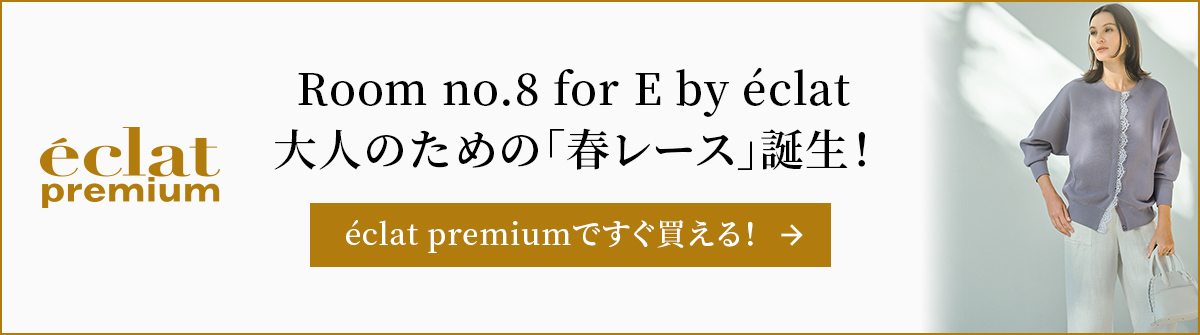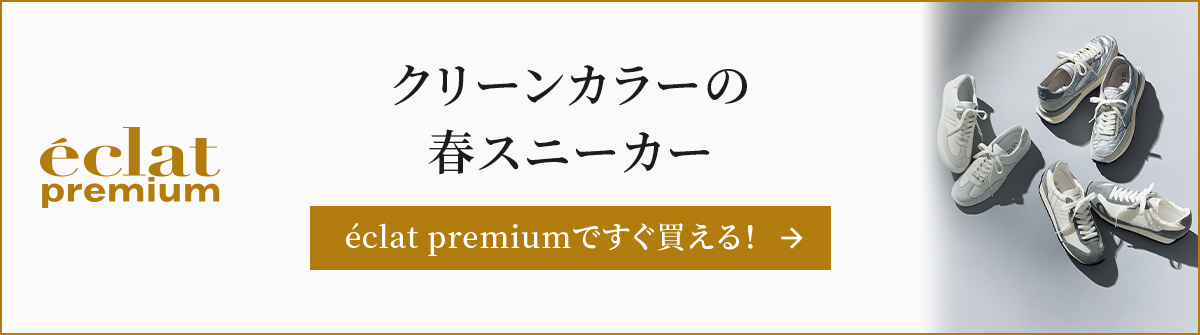しなやかに時を重ね、どこまでも挑戦を続けるエクラな女性たち。役者でありファッションブランドのディレクターでもある板谷由夏さんもそのひとりだ。昨年はホームレス女性を演じ話題となった。自分ではない何者かになること。それは板谷さんに何をもたらしてきたのだろう。前中後編の中編では、“役者”という仕事について伺った。
ノンフィクションで得た経験。役者として伝えられたら
板谷さん自身、’07年から11年間、報道番組『NEWS ZERO』のキャスターという仕事を通して、社会に目を向け続けてきた。
「問題を抱えている人やそれを突破しようとしている人など、とにかくいろいろな人々に会いにいって話を聞きました。今を生きる人々のリアルを、その時期山ほど浴びましたね。ひとりの人間としてすごく勉強になりました。ただその人たちの心の襞(ひだ)にまで分け入ろうとすると、時として自分のメンタルがダイレクトに影響を受けるんです」
ふっとひと呼吸間をおいて、こう続ける。
「東日本大震災で家族を亡くした悲しみの中にいる人にもずっと会い続けました。もうね、自分がどうかなるんじゃないかと思うほど苦しかった。テレビでは当事者が泣いているところだけが切り取られがちだけど、日常生活の中ではごはんを作り、食べ、おいしいねと笑うこともある。だって悲しみを抱えたまま明日も明後日も生きていかなきゃいけないじゃないですか。そういうリアリティのほうが私にはこたえました。脚本では書ききれない部分かもしれない。そのとき思ったんです。このノンフィクションをフィクションの中で大勢の人に伝える、自分のフィルターを通して出す、それが役者である私の仕事かもしれないと。あのときたっくさん浴びたリアリティや出会った人々の思いを、いつかどこかで作品の中に還元できたらと」

ドレス¥409,200・靴(参考商品)/ラルフ ローレン(ラルフ ローレン コレクション) イヤリング¥1,155,000・ブレスレット¥1,320,000 /ブチェラッティ
俳優、女優、役者……、と役を演じる職業を表す言葉のうち、板谷さんは「役者」が一番しっくりくるという。
「その役を演じることが、私の人生に求められた役目なのだと思いたいんですね、きっと。この仕事が向いているかどうかわからないけれどね」
映画『avec mon mari』(監督:大谷健太郎)で役者としてデビューしたのは23歳の時。チームで協力して作品を作る楽しさに夢中になった。『運命じゃない人』(監督:内田けんじ)、『サッドヴァケイション』(監督:青山真治)、『SUNNY 強い気持ち・強い愛』(監督:大根仁)と、その後も40代にかけて精力的に出演した。
「とにかくなんでも演じたいって思っていました。オファーは基本的にくるものは拒まず、ひとつひとつ積み重ねていこうと」
「役者という仕事、楽しいというよりどちらかといえば苦しいかな」
テレビドラマでもさまざまな姿を見せてくれている。あえていえば、雑誌の編集長、医者、弁護士など、その道のプロフェッショナルという役どころの印象が強い。
「役づくりというわけでもないけれど、まわりのいろいろな人を観察するのが好きですね。うわ! 今あの人やっばい転び方したなあとか、この人そこでそういう表情するんだとか、あのお母さん、子供のことこういう叱り方するんだとか。放っておけばいつまでも観察してますね」
人間観察は役者の性(さが)。役者という仕事のおもしろさをどう感じているのだろう。
「うーん、どんな役でもひとつひとつ淡々とやってきたけれど、おもしろいとか楽しいとか思ったことないかも。楽しいかなあ……、いや楽しくはない気がしますねえ。チームで何かを作る一体感は好きですし、いろいろな人と出会えるのも楽しい。でもひとりの女の人生や背景を背負って演じることは……、うん、やはりどちらかというと苦しいかなあ」と苦笑しつつ、こう続ける。
「苦しいから基本的にはその現場が終わると全部忘れちゃうんです。でもずっとあとになってから、演じた役が私にメッセージを送ってくることがあるんです。そうか、あの役ってこういうことだったのか、こういうことがいいたかったのかと。撮影中にリアルタイムに感じろよって思いますが。終わった役は引きずらないほうですが、ずっと付き合い続けているような気持ちになる役もありますね。ほんと、なんだか変な仕事ですよね(笑)」
(後編へつづく)