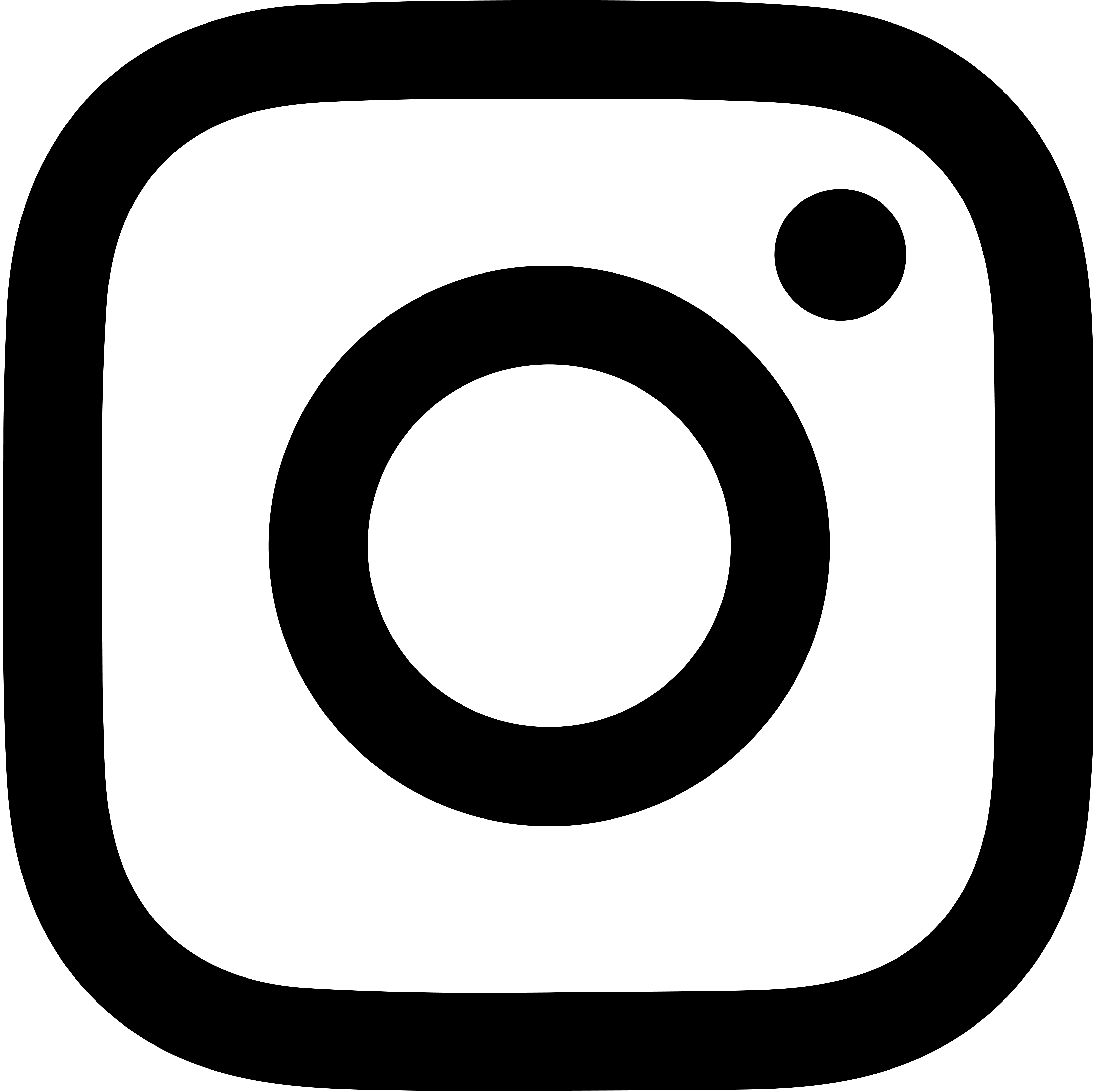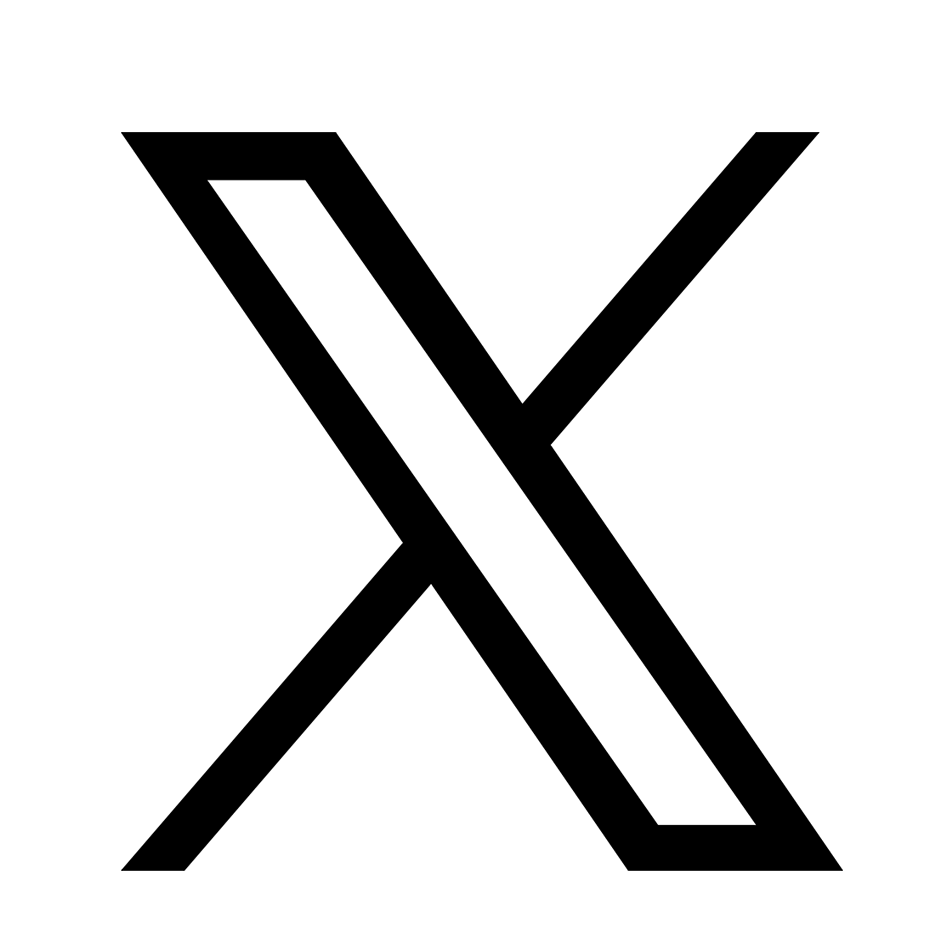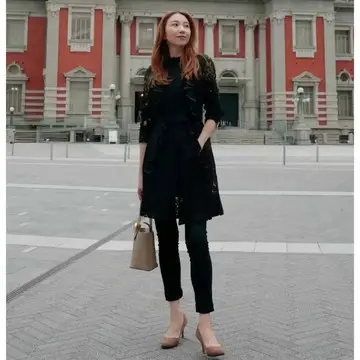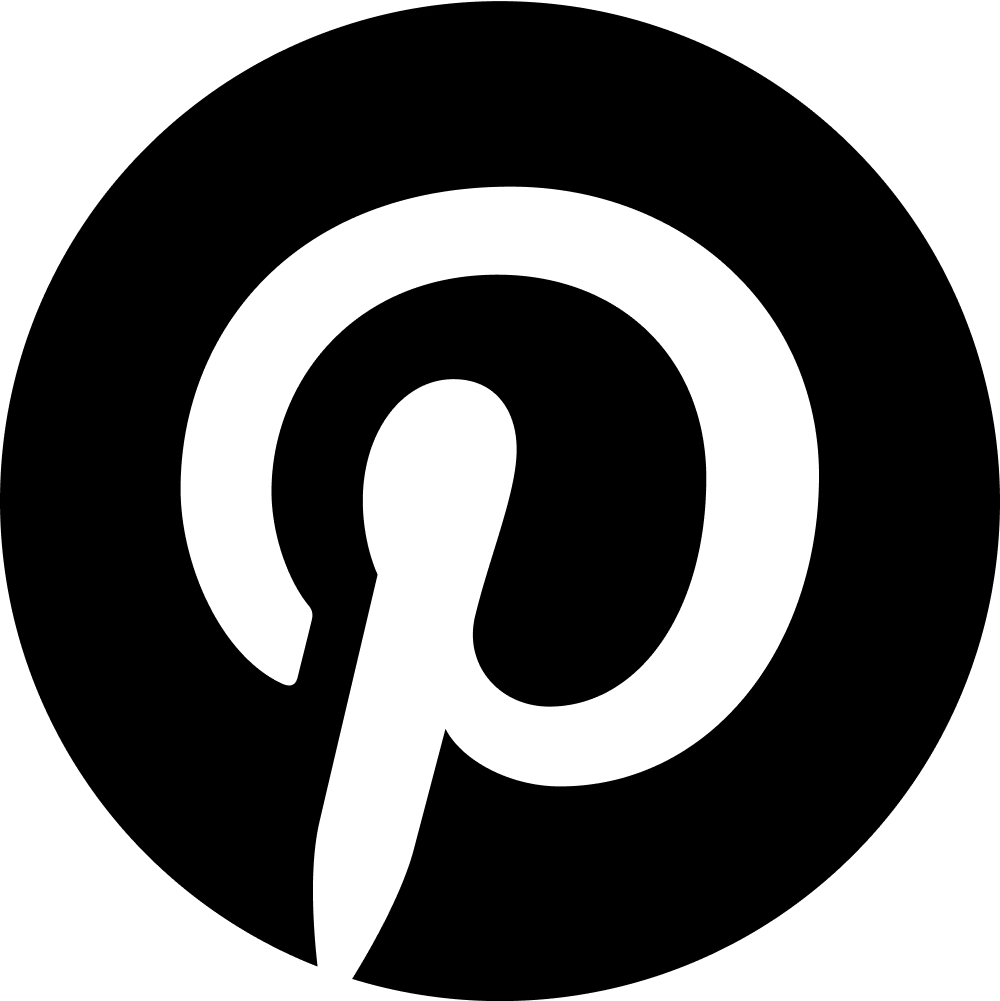仕事や男女関係を“食べ物”を通して鋭く描く
食をテーマにした物語は少なくない。何げない食べ物に癒されるとか、思い出の味から過去を回想するとか、多くは食を肯定的に描いたものだ。
タイトルだけ見ると、高瀬隼子『おいしいごはんが食べられますように』もその種の小説に思えるだろう。ところが話はまるで異なる。極端にいえば、これは皮肉に満ちたアンチグルメ小説。食に対する世間の無条件の礼賛ぶりに背を向けるような作品なのだ。
舞台は食品や飲料のラベルパッケージを製作する会社の埼玉支店。主人公の二谷は入社7年目。30歳手前の男性で、東北の支店から3カ月前に転勤してきた。
二谷は食にとことん無関心な人物で、〈一日三食カップ麺を食べて、それで健康に生きていく食の条件が揃えばいいのに〉と考えている。〈一日一粒で全部の栄養と必要なカロリーが摂取できる錠剤ができるのでもいい。それを飲むだけで健康的に生きられて、食事は嗜好品としてだけ残る。酒や煙草みたいに〉が理想である。
仕事に対する意欲も、恋愛に対する興味も似たりよったりだが、当たり障りのない人生を生きてはきた。物語は二谷とふたりの女性の同僚の関係を中心に展開する。
まず、1歳上の芦川さん。人に会うのが苦手らしく、仕事もさぼりがちだが、なぜか職場では許されている。もうひとりは理由もなく優遇されているその芦川さんが嫌いだと二谷に耳打ちしてきた押尾さん。高校時代はチアリーディング部で活躍したという彼女は仕事に対する意欲も高い。
で、二谷はどうしたか。押尾と意気投合し、会社帰りに居酒屋に立ち寄る飲み友だち的な関係をもちつつ、なりゆきで芦川と付き合いはじめるのである。〈二谷さん、わたしと一緒に、芦川さんにいじわるしませんか〉と押尾に誘われ〈いいね〉と答えたのに。
ここから先がおもしろい。芦川は週末ごとに二谷のマンションを訪れて、いかにも家庭的な手料理をふるまうが、それが二谷にはうっとうしくてしかたがない。芦川が眠ったあと、ひとりでこっそりカップ麵を食べて〈ようやく、晩飯を食べた、という気がした〉という屈折ぶり。しかし芦川の女子力アピールはますますエスカレートし、今度は職場にたびたび手作りの菓子を持参してふるまうようになった。二谷と押尾はウンザリしつつ、当面は調子を合わせるふりをしていたが……。
二谷は一見ダルなキャラだが、恋人の手料理を喜ぶ男よりずっとマシ。〈残業して、二十二時の閉店間際にスーパーに寄って、それから飯を作って食べることが、ほんとうに自分を大切にするってことか〉という問いは鋭い。自分が「世話焼きおばさん」と化していないか反省させられる小説だ。