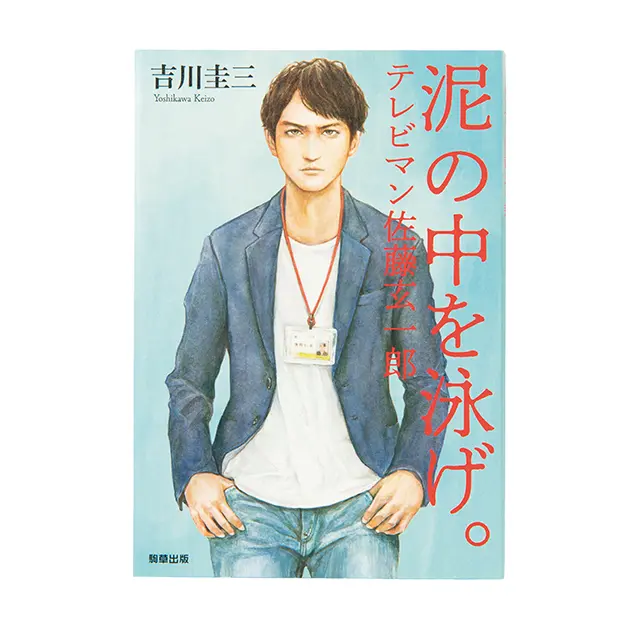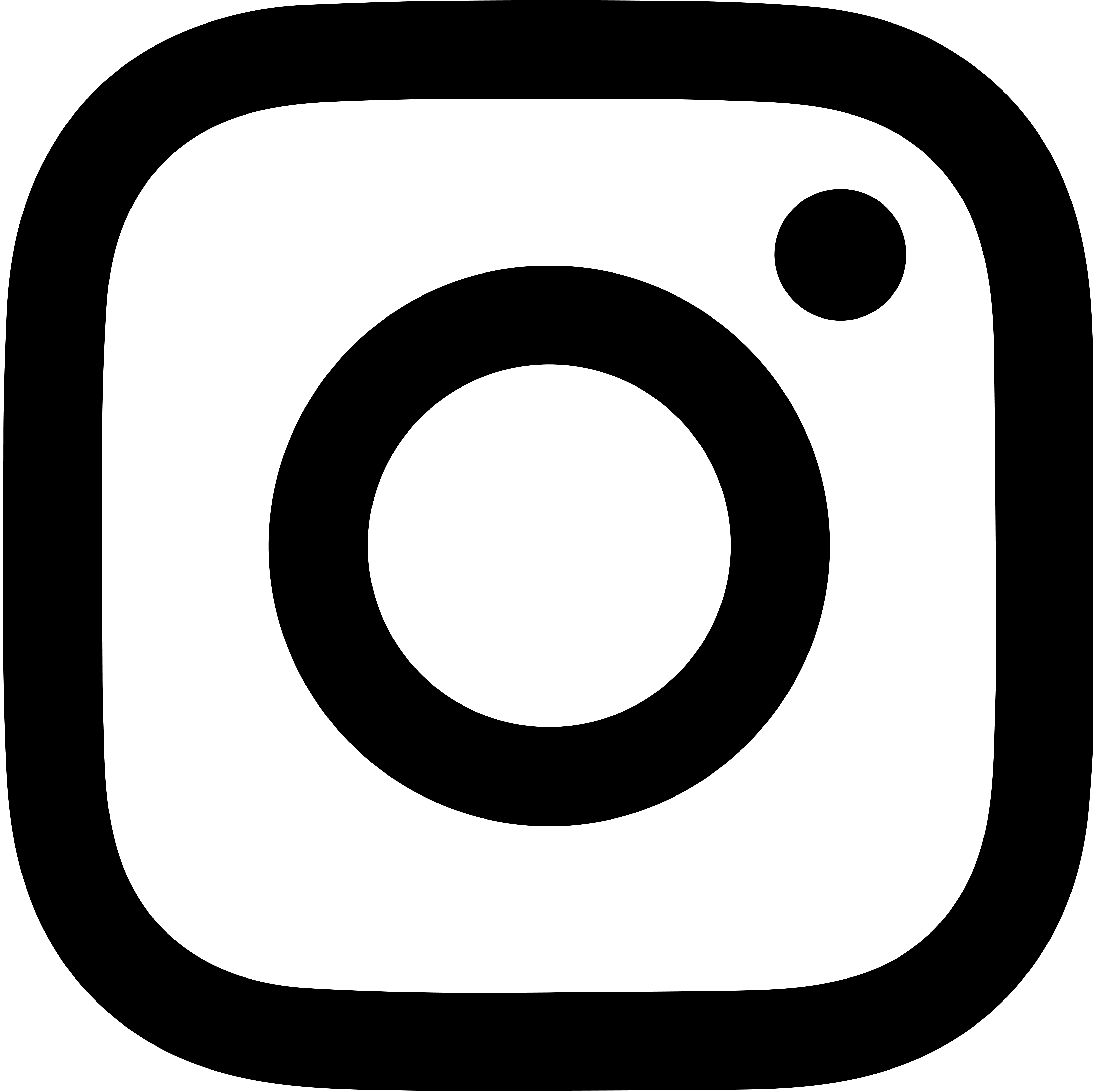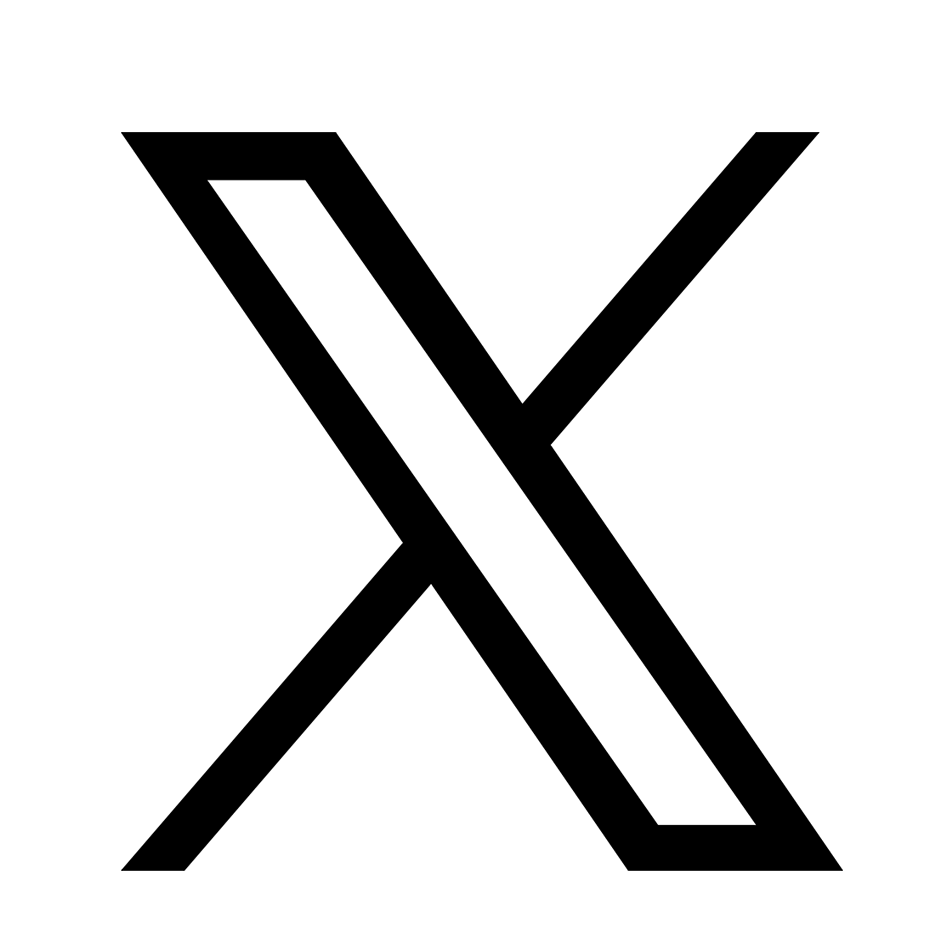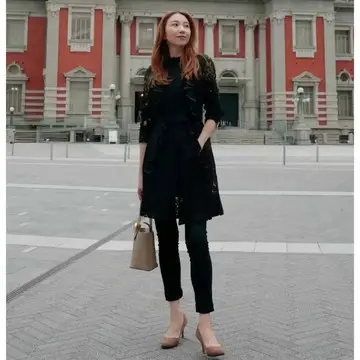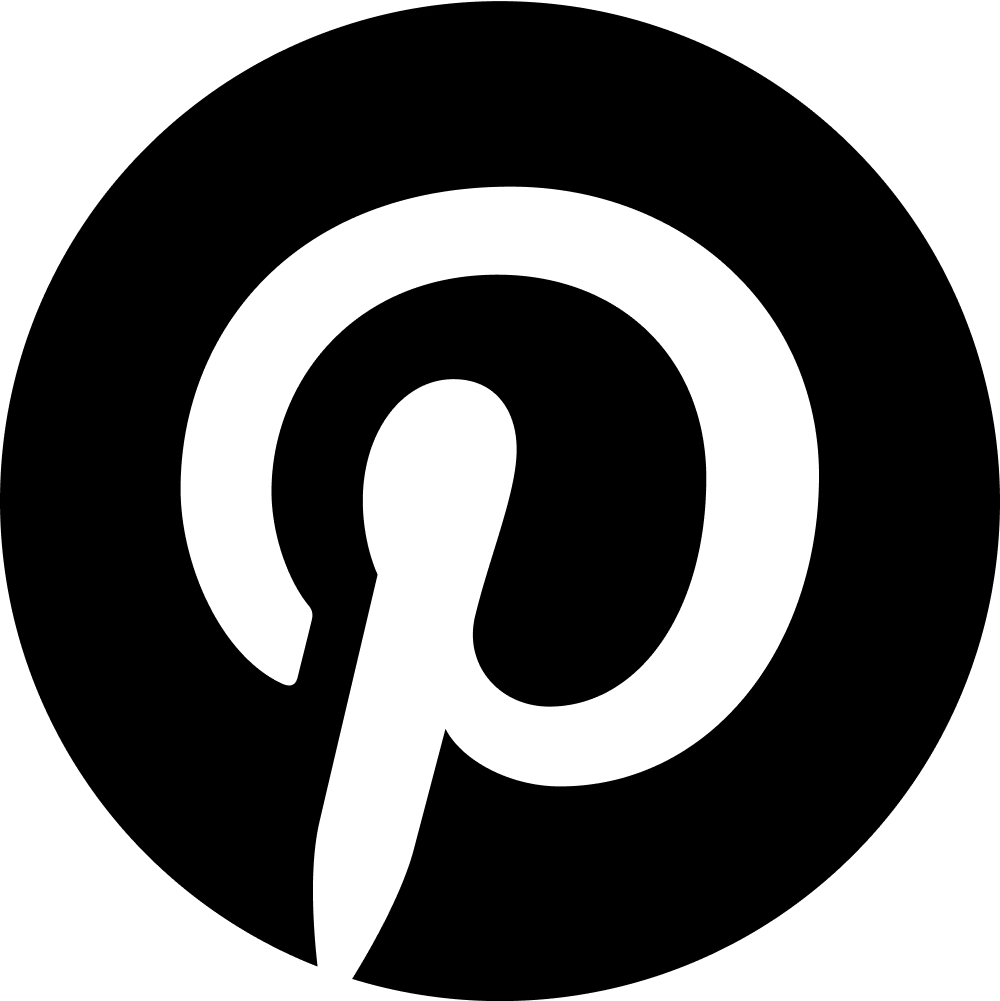テレビ局で働く人々の平凡な人生を物語る業界小説
砂嵐と聞いて「テレビ番組終了後のザーッていう画面のこと」と理解するのは、何歳くらいまでの人だろうか。
一穂ミチ『砂嵐に星屑』は大阪の民放テレビ局を舞台にした連作短編集である。かつては花形産業だったテレビ局もネットに押されて今や斜陽。そのせいもあってか、収録された4作品の主人公は皆、仕事への情熱を失っている。
「〈春〉資料室の幽霊」の主人公・三木邑子は43歳のアナウンサー。10年前、上司だった局の看板アナウンサー・村雲清司との不倫が原因で東京に異動になり、このほど大阪に戻ってきた。昨年の春に定年退職した村雲が、暮れに病死したためと思われた。露骨すぎる人事。邑子はため息をつく。
〈十年で街はこんなに変わったのに、わたしはただ年を取り、老いへと下っていっただけ。積み重ねた財産も身につけた武器も見当たらないまま、若さという唯一の取り柄さえ失ってしまった〉
かといって局をやめ、フリーになるという選択肢も彼女にはない。フリーで華々しく活躍できるのは東京の、それもひと握りのスター的な女子アナだけ。〈どこかの事務所に所属し、ナレーションやイベントの司会をこなす──その都度オーディションを受け、若い子と比較されながら? 運よく仕事にありつけたとしても、おそらく収入は今の半分以下になる〉。そんな冒険はとてもできない。
一方、第2話「〈夏〉泥舟のモラトリアム」の主人公・中島は52歳。報道部のデスクである。入社時には30人ほどいた同期も今は20人いるかどうか。ことに50歳の坂を越えたころから、退職金の上乗せもあって早期退職する者が増えはじめた。〈斜陽著しいマスコミ業界に六十歳までしがみつくのか、ここで転機を図るのか〉の瀬戸際に彼らは立っている。
〈「ほんま、試されるお年頃やで」/「泥舟から逃げ出すねずみみたいなもんやろうな」と中島は答えた。/「中島は逃げへんのか?」/「逃げたとて、次のアテなんかあらへん」〉。/〈「娘もまだ大学二年生やし、冒険も隠居も無理や」〉
これが中島の現実だ。しかも彼はマスメディアへの反発を隠さない娘と冷戦状態を続けていた。
アラフォー、アラフィーの会社員に襲いかかるアイデンティティの危機! テレビ局ではなくっても、よくある話かもしれない。
とはいえ『砂嵐に星屑』という書名どおり、小説は一見しょぼくれた登場人物の平凡な仕事ぶりの中に一条の光を見出していく。
死んだ村雲の幽霊が資料室に出るという噂から、過去と向き合わざるをえなくなる三木邑子。「マスゴミ」と罵(ののし)られても黙々と災害報道を続けて、娘との関係改善にいたる中島。派手さがまるでないという意味で、出色の業界小説だ。