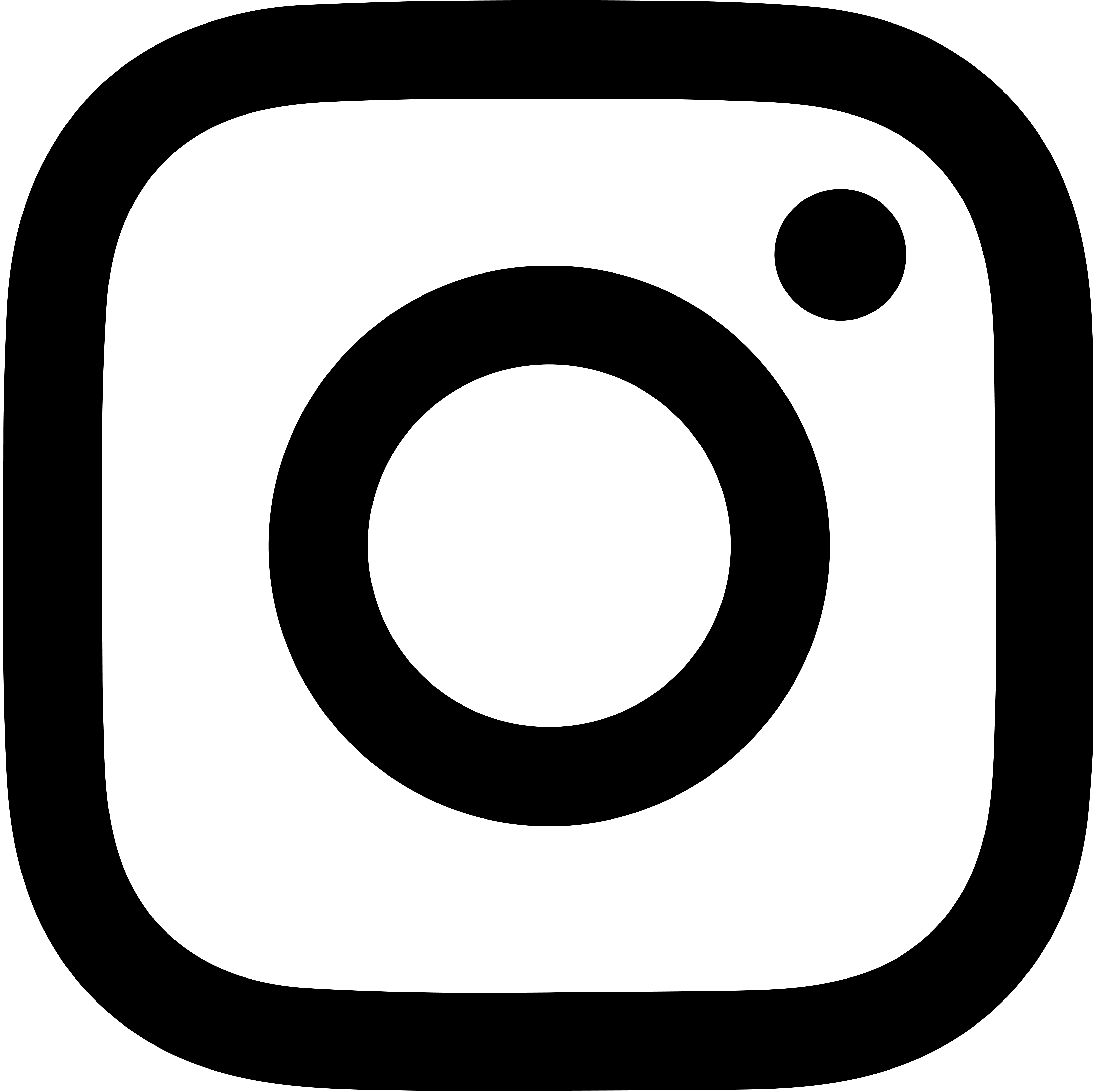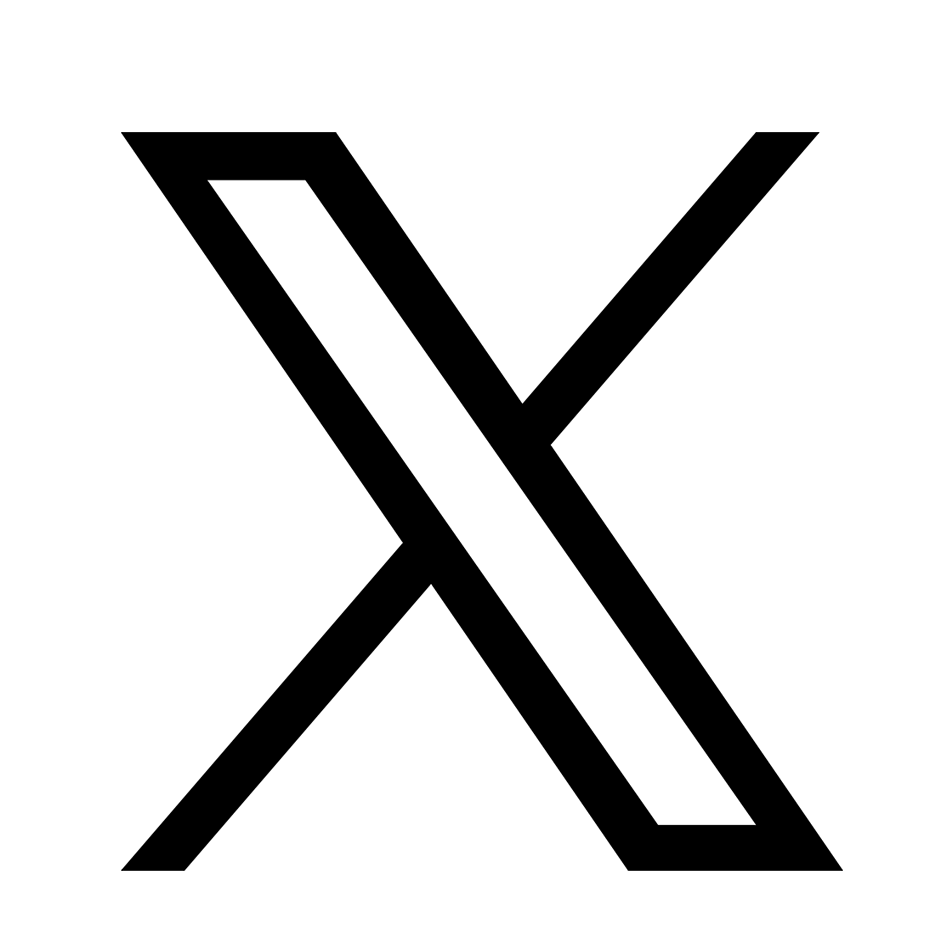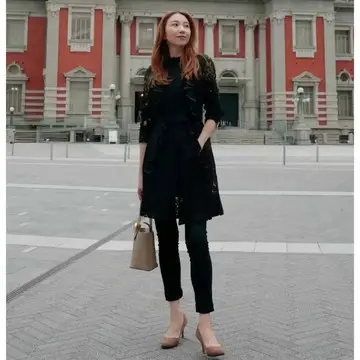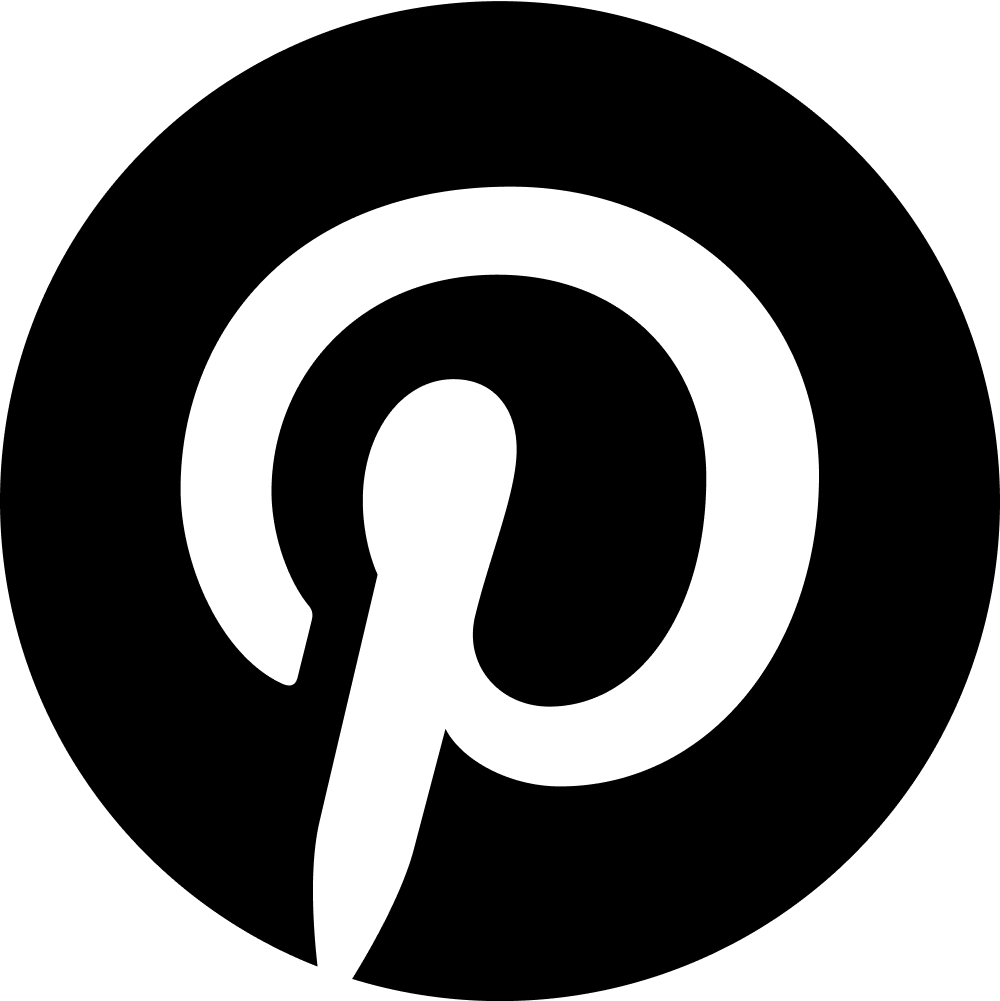新型コロナウイルス感染症の発生から丸3年が経過した。今年5月には感染症法上の位置づけがインフルエンザなどと同じ5類に移行し、終息とはいえぬまでももとの日常が戻ってきた。あの3年間は何だったの?と思っている人もきっといますよね。
フィクションの世界でも「コロナ小説」が続々と生まれている。
桜庭一樹『彼女が言わなかったすべてのこと』は壮大な仕掛けを凝らした異色のコロナ小説だ。
’19年9月、主人公の小林波間(32歳)は、通り魔殺人の現場で大学時代の同級生・中川君と偶然再会した。ふたりはLINEを交換してまた会おうと約束するが、なぜか以降は、同じ場所にいるはずなのに会うことができない。どうやらふたりは別々の東京で暮らしており、LINEでしかつながれないらしい。そう、これはパラレルワールドものなのだ!
年が明けて’20年、中川君から切迫したLINEが次々に送られてきた。〈小林。そっちの世界でも、中国でやばめの感染症が広がってるってニュースを聞くか?〉〈コンサート、演劇。中止、延期。怒濤のニュース。つぎつぎ。急にびっくりだよ!〉〈こっちさー、東京オリンピック延期かも……?〉
波間はどう応じてよいかわからない。彼女が住む「こちらの世界」ではコロナ禍は発生していないし、オリンピックに向けた準備も着々と進んでいたからだ。
が、そうこうするうち中川君とは連絡がとれなくなり、いくらLINEをしても既読がつかない。最後に送られてきたLINEでは中川君は発熱で苦しんでいるようだった。〈体調悪い。熱もあってだるい。発熱外来も混んでて。それに陽性ってわかっても治療受けられないだろうし〉。中川君は大丈夫なのだろうか。
’20年から’21年(第1波から第4波)のころまでの緊迫した状況がまざまざと蘇る。と同時にパンデミックを「外」から見たらこんなふうに現実感がなかったのだろうなとも思う。あの時期はやっぱりいろいろ異常だったのだ。
とはいえ、波間にとっても「向こうの世界」は他人事ではなかった。彼女自身も悪性腫瘍があると診断され、半年間の点滴治療のあとで摘出手術を受け、さらに数年にわたるホルモン治療が必要という、闘病生活の中にいたからだ。
集団的な感染症と個人の病。状況は違っても、ふたりが立ち向かっている現実はともに厳しい。とかく緊急事態宣言下での不自由な生活にフォーカスしがちなコロナ禍を原点である病の問題としてとらえた佳編。波間のいる世界ではコロナによる死者は出ていない。それを知った中川君がふと呟(つぶや)く〈パラレルワールドってさ、あの世みたいだな。こうなってみるとさ〉という言葉が印象的だ。