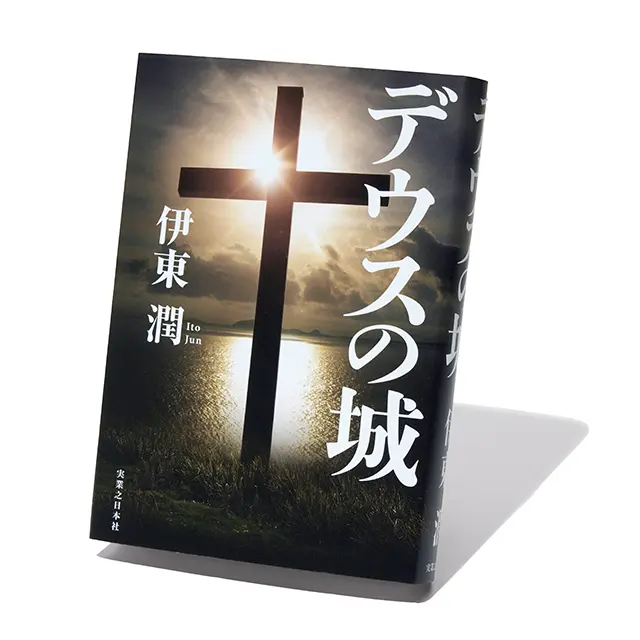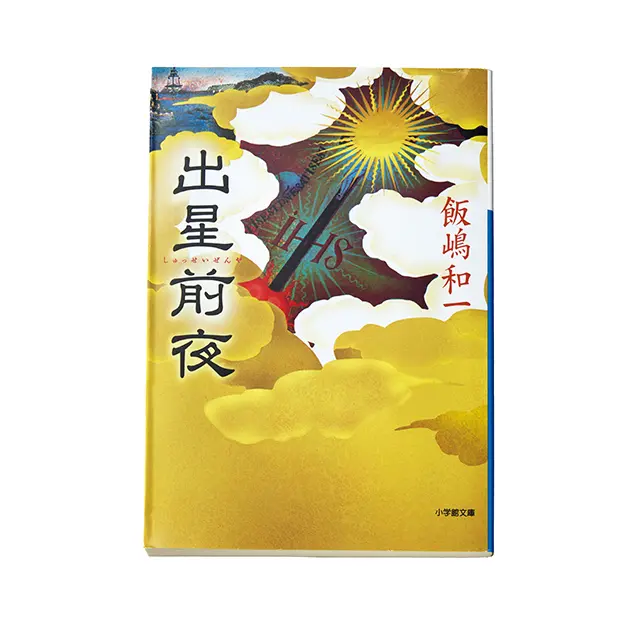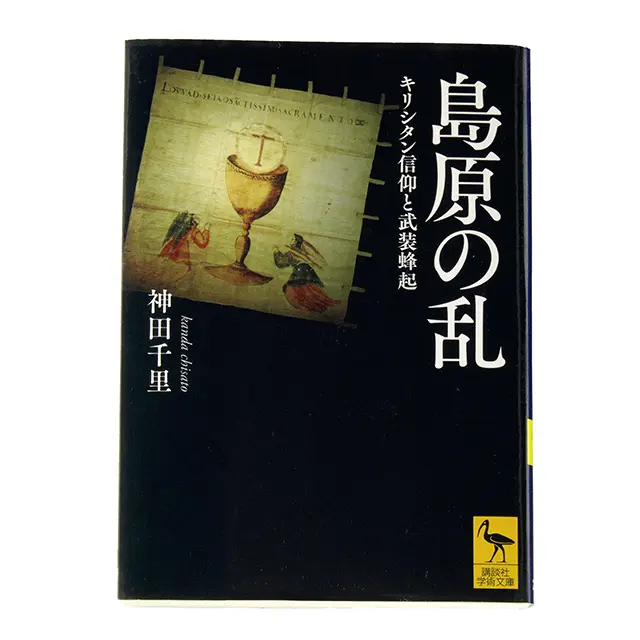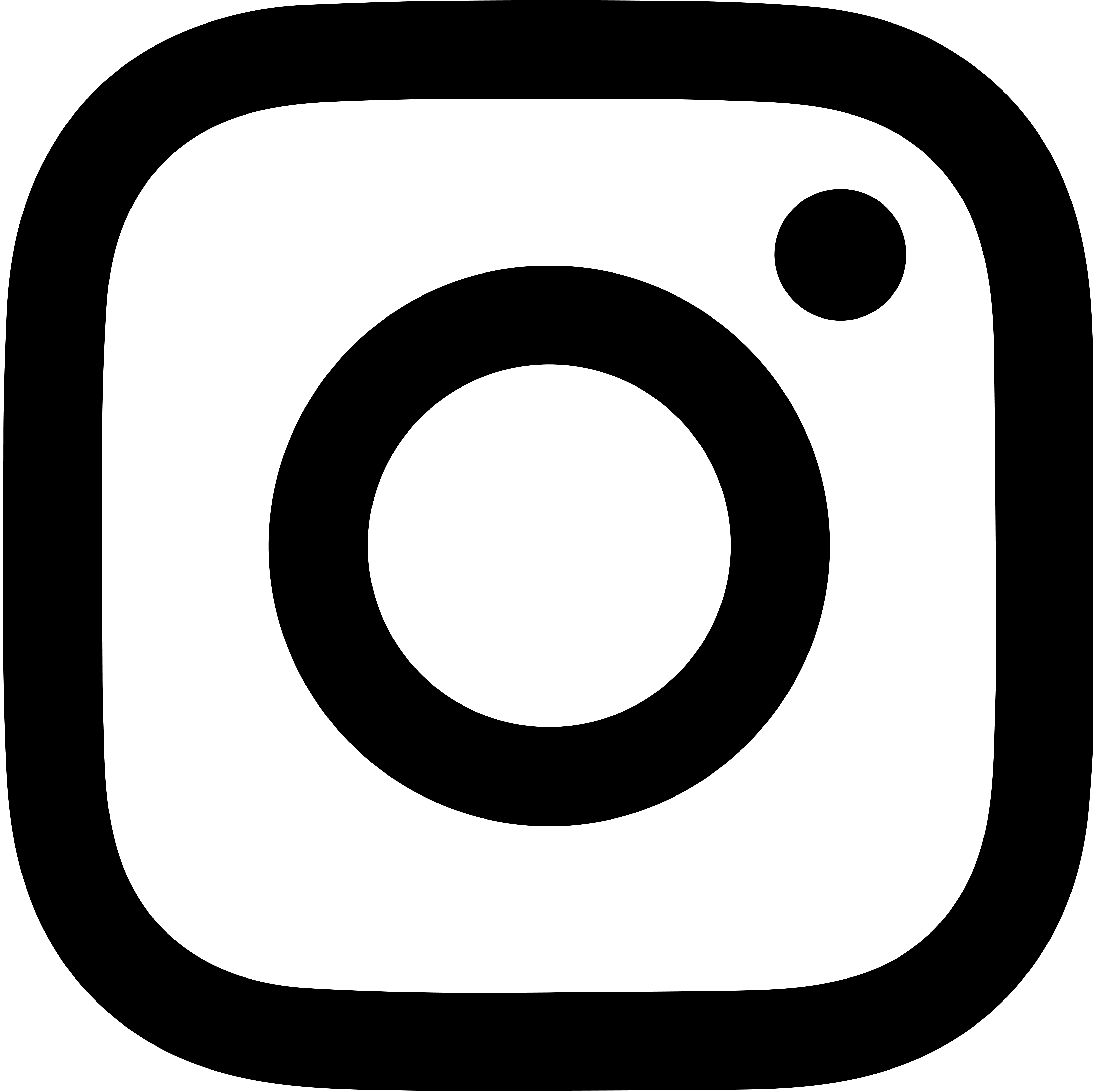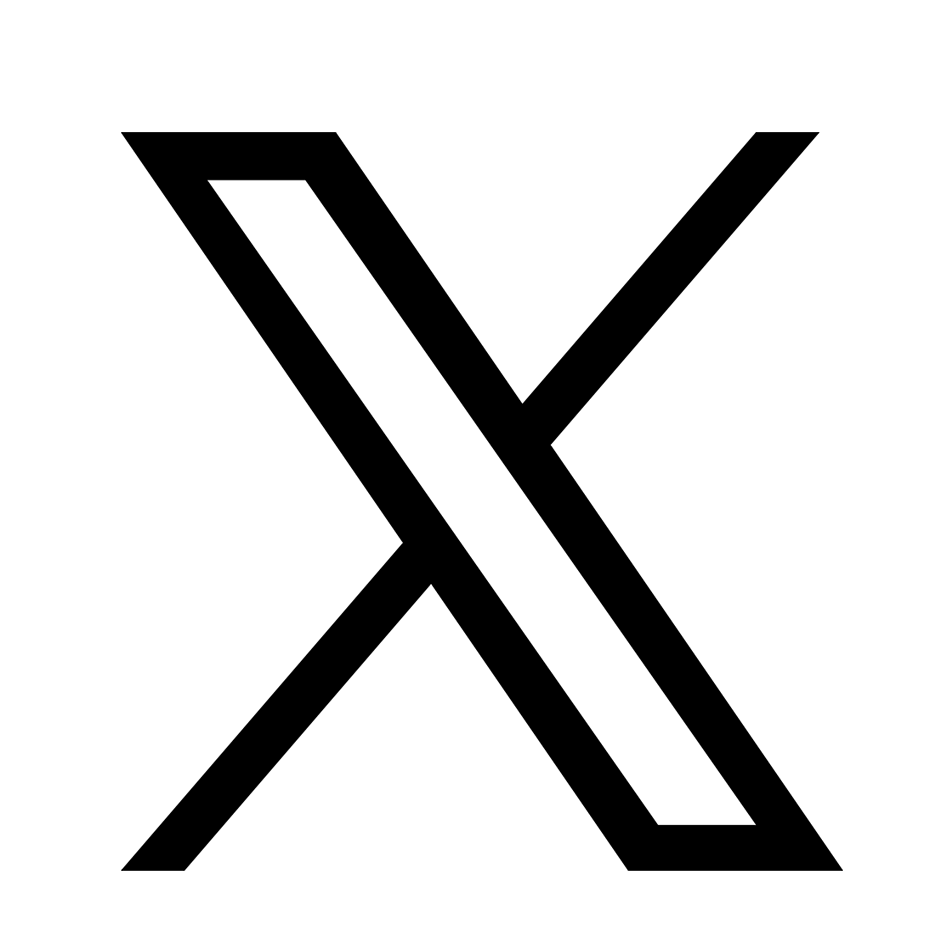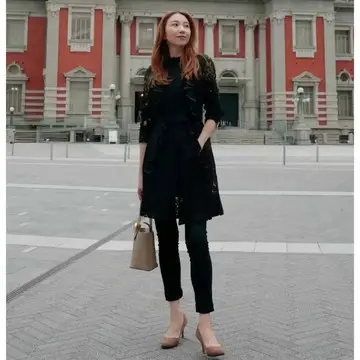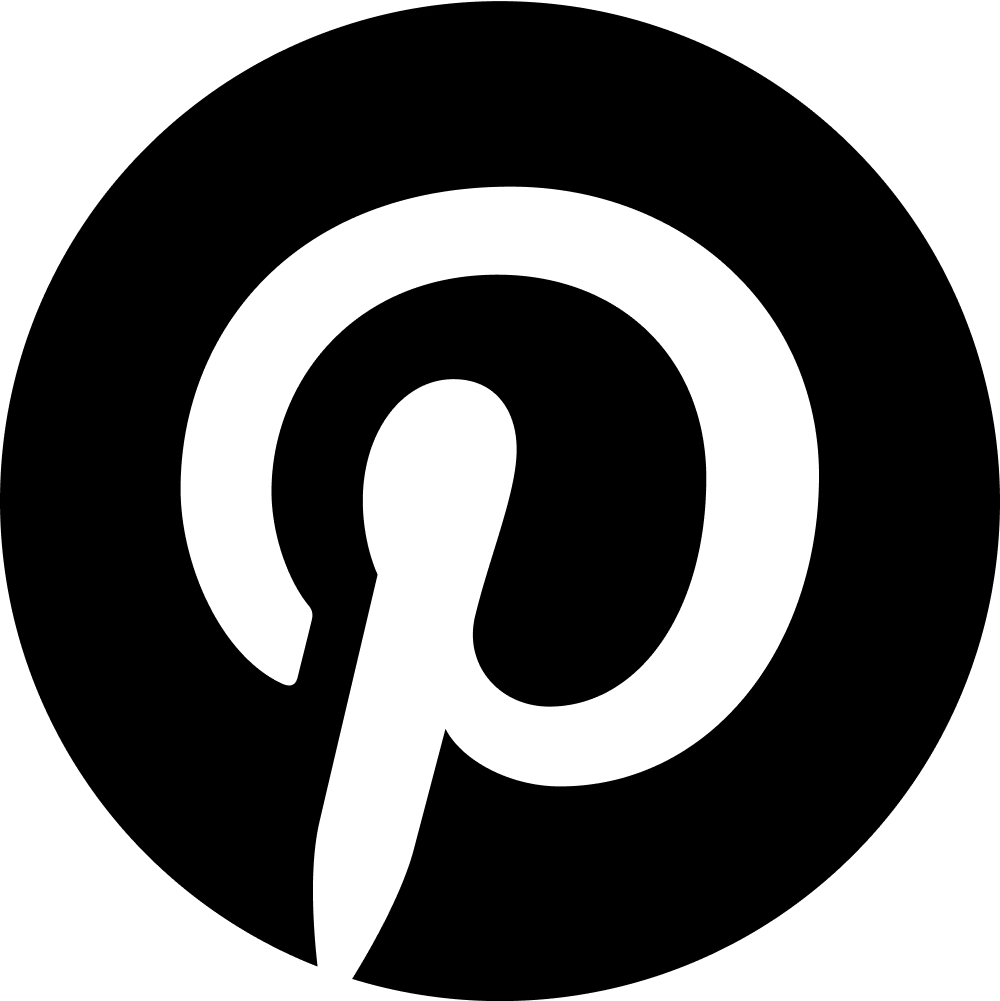2018年に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界文化遺産に登録されて、がぜん注目度が上がった「島原・天草一揆」(別名「島原の乱」。1637年)。この戦いは領民側3万7千人、幕府側も1万3千人の死者を出した日本史上最大規模の内戦だった。
伊東潤『デウスの城』はこの一揆を題材にした最新の長編小説だ。
主人公はキリシタン大名・小西行長の家臣だった3人の若者だ。宇土(うと)城下の教会で洗礼を受け、そろってキリシタンとなった幼なじみの3人は、関ヶ原の戦に破れて主を失ったあと、別々の道を歩みはじめる。長崎に行き、イルマン(助祭)となって布教に生きる道を見出す彦九郎(ひこくろう)。加藤清正に仕官し、のちに棄教してキリシタン狩りの先頭に立つ佐平次(さへいじ)。臨済宗の高僧・金地院崇伝(こんちいんすうでん)のもとで禅僧になり、形だけでも棄教しろとキリシタンたちに説いてまわる善大夫(ぜんだゆう)。
まさに三者三様! 関ヶ原の戦の際には15歳の少年だったこの3人が37年後、50歳を過ぎて一揆の場で再会するのだ。ドラマティックにならないはずがない。
もっともこの小説がスリリングなのは、宗教とは何かという問いに彼らが直面する点にある。
ある集会場で神の教えを説いていた彦九郎は参加していた武士の鋭い質問を受ける。〈では聞くが、キリシタン信仰など知らずに死んでいった者たちは、皆地獄にいるのか〉。〈はい。地獄で業火に焼かれています〉と答えるしかない彦九郎。〈では、ここにいる者たちのご先祖様は今、地獄の業火に焼かれているというのだな〉。問答の末に相手は言い放つ。〈異教徒として死んでいった者たちの供養を禁じ、寺社や祖先の墓を破壊し、位牌を焼く宗教が救いの光だと。馬鹿も休み休み言え!〉。
まことに正論である。ほかの宗教となぜ共存できないのかと彦九郎は悩み、やがて殉教を是(ぜ)とする思想にも疑問をもちはじめる。
それは棄教した佐平次や善大夫にしても同じで、それぞれの正義に従って働きつつも、自分たちのやっていることは正しいのかと問い返さずにはいられない。
パレスチナやイスラムの紛争を思い出せばわかるように、宗教的な対立は時に多くの犠牲者を出す。これは過去の話ではない。と思わせるのは、3人の主人公が現代人とそう違わぬ合理的な精神の持ち主として描かれているためだろう。カリスマ的なリーダーと伝えられる天草四郎の人物像も思いっきり現代的で、思わず膝を打つ。
重い問いを含みながらも物語はテンポよく進み、若手人気俳優をそろえて映像化したらヒットしそうだ。歴史の教科書で漠然と知る程度だった400年前の事件が急に身近になる時代小説。読書の醍醐味を味わえることうけあい。