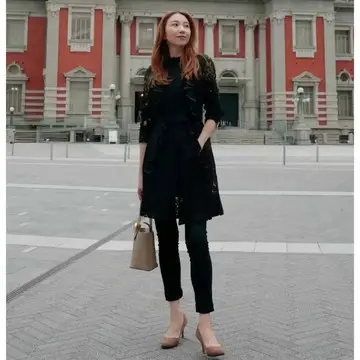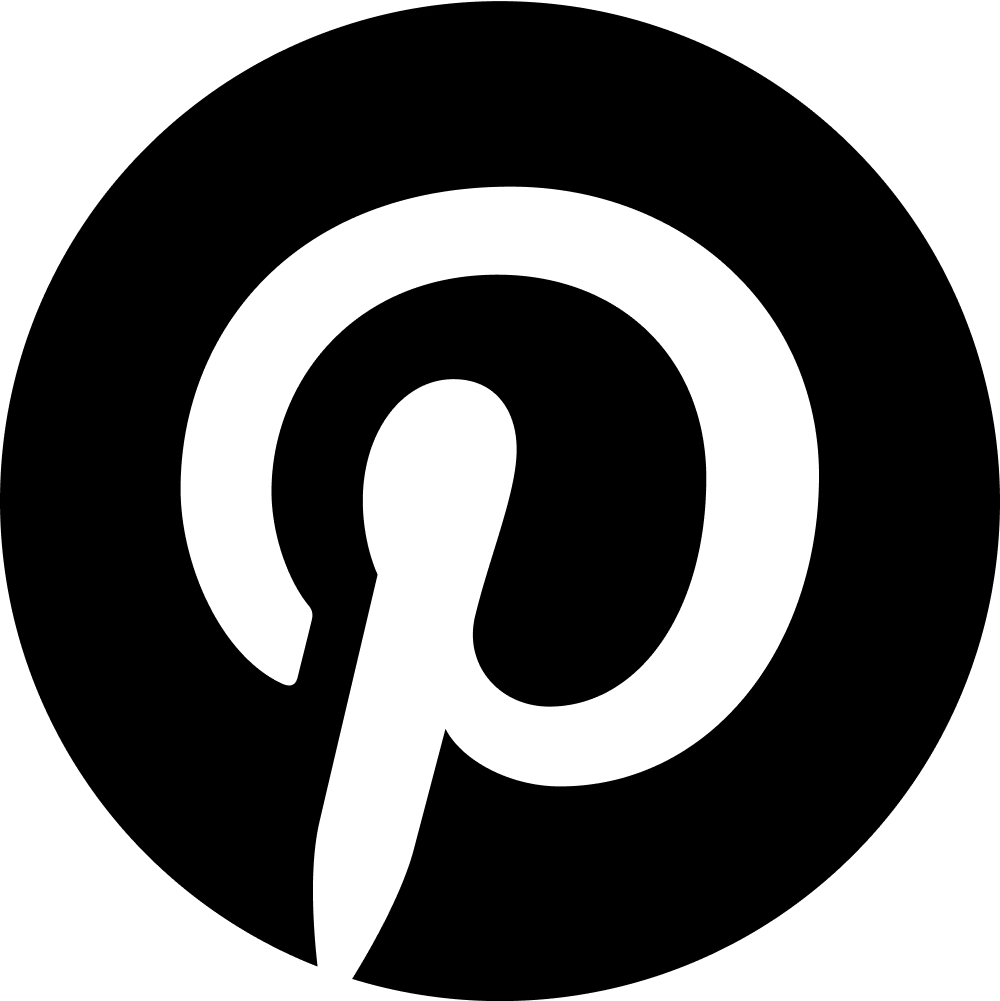少女を主人公にした小説は戦後のジュニア小説やコバルト文庫の時代から多々あった。とはいえ今日、この種の少女ものは文学界を席巻(せっけん)している感があり、物語内容も多岐にわたる。
一例が’21年の「女による女のためのR-18文学賞」を受賞した『成瀬は天下を取りにいく』だろう。主人公は中学生で、しかし夢中になった大人は多かった。
平戸萌『私が鳥のときは』は’22年の「氷室冴子青春文学賞」大賞受賞作である。同賞は氷室冴子氏の出身地・北海道岩見沢市のNPO法人が主催する賞で、’23年で5回目。『成瀬は〜』同様、こちらの主人公も中学生だ。
物語は夏休みのある日、母がパートの元同僚を家に連れてきたところから始まる。〈さらってきちゃった〉と母はいい、〈さらわれてきちゃった〉とその人はいった。彼女の名前はバナミさん。それが本名で、余命3カ月と宣告された病人であるという。
〈あんたたちに迷惑はかけないわよ〉〈ただ和室を貸しただけじゃない〉と母はいうが、中学3年生の蒼子は怒りを隠せない。〈だってあたし受験生なんだよ〉〈だってお母さん看病なんかできないでしょ、素人なんだし〉。
しかし抵抗虚しくバナミはこの家で暮らしはじめ、入れ替わりに父と弟は祖母の家に一時移転した。蒼子は塾友だちのヒナちゃんに愚痴らずにいられない。〈はあー、まじ憂鬱〉〈ふつう夫の人とか迎えに来るよね〉〈息子だっているんだよ。死にかけた母親がひとんちにさらわれても知らん顔ってどうなの。家族でしょ〉。
いささか無理のある設定とはいえる。だが物語はこのあと、思いがけない展開を見せるのだ。
バナミさんが実は蒼子の同級生の母だったこと。彼女が息子を産んだのは15歳のときで、今の夫とは19歳のときに知り合ったこと。しかも彼女は(余命宣告されているというのに)息子と一緒に高校受験がしたいという。
蒼子自身も実は秘密を抱えていた。彼女はクラスの中で孤立して1年前から不登校を続けていたのだ。成績優秀で塾ではトップのヒナちゃんも家では虐待されていた。それやこれやで3人はヒナちゃんを家庭教師役に勉強を始めるのだが、ヒナちゃんの体に異変を察知した日、蒼子は彼女を家に連れて帰り、そしていったのだ。〈……さらってきちゃった〉。
女性だけの共生を描いた小説は最近の流行であるとはいえ、世代も境遇も異なる4人が足りない部分を補い合い、しかも受験勉強を始めるというのは異色。この家はいうならば避難所なのだ。
停滞した共同体に異質な要素が入ることで起きる波紋。変化を受け入れれば新しい可能性が開けるというメッセージにも思える。





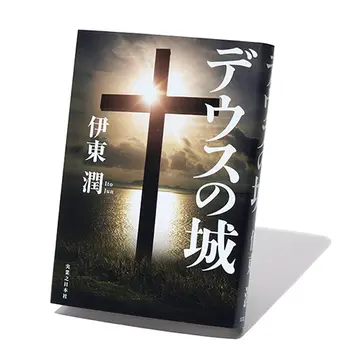



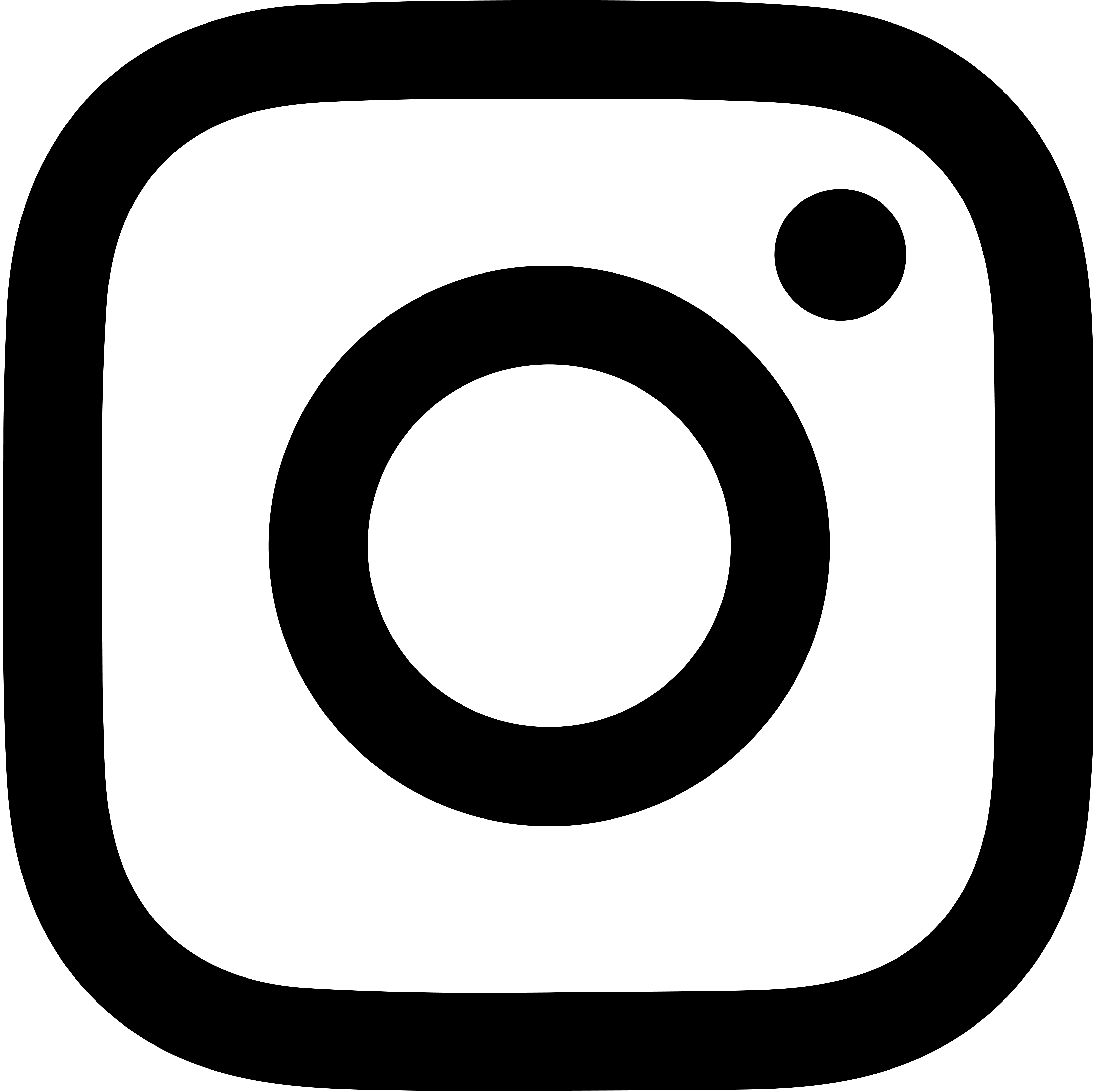

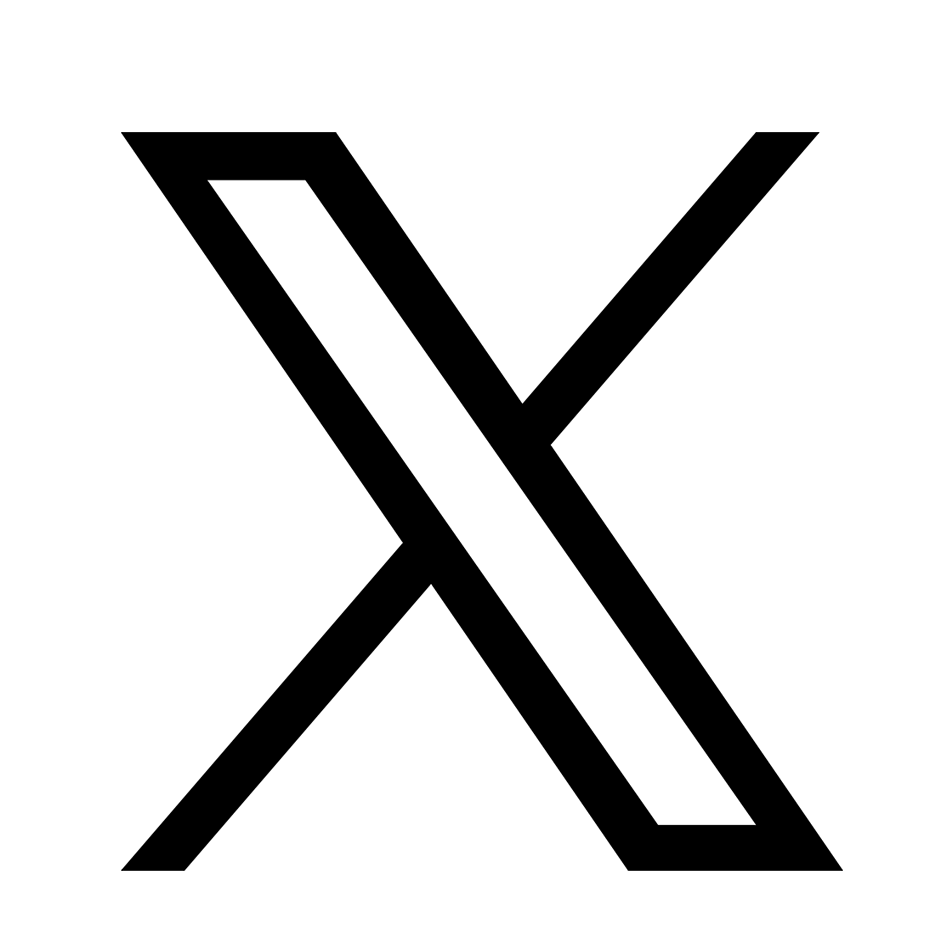


![【舘ひろし×柴田恭兵インタビュー[前編]】『あぶない刑事』8年ぶりのカムバック、タカとユージの現在地](https://image-hp.hpplus.jp/q=75,f=webp:auto/sqr/a0/a03bda8a49ba8afe1d716c371fbdc8f1_500x500_w.jpg)