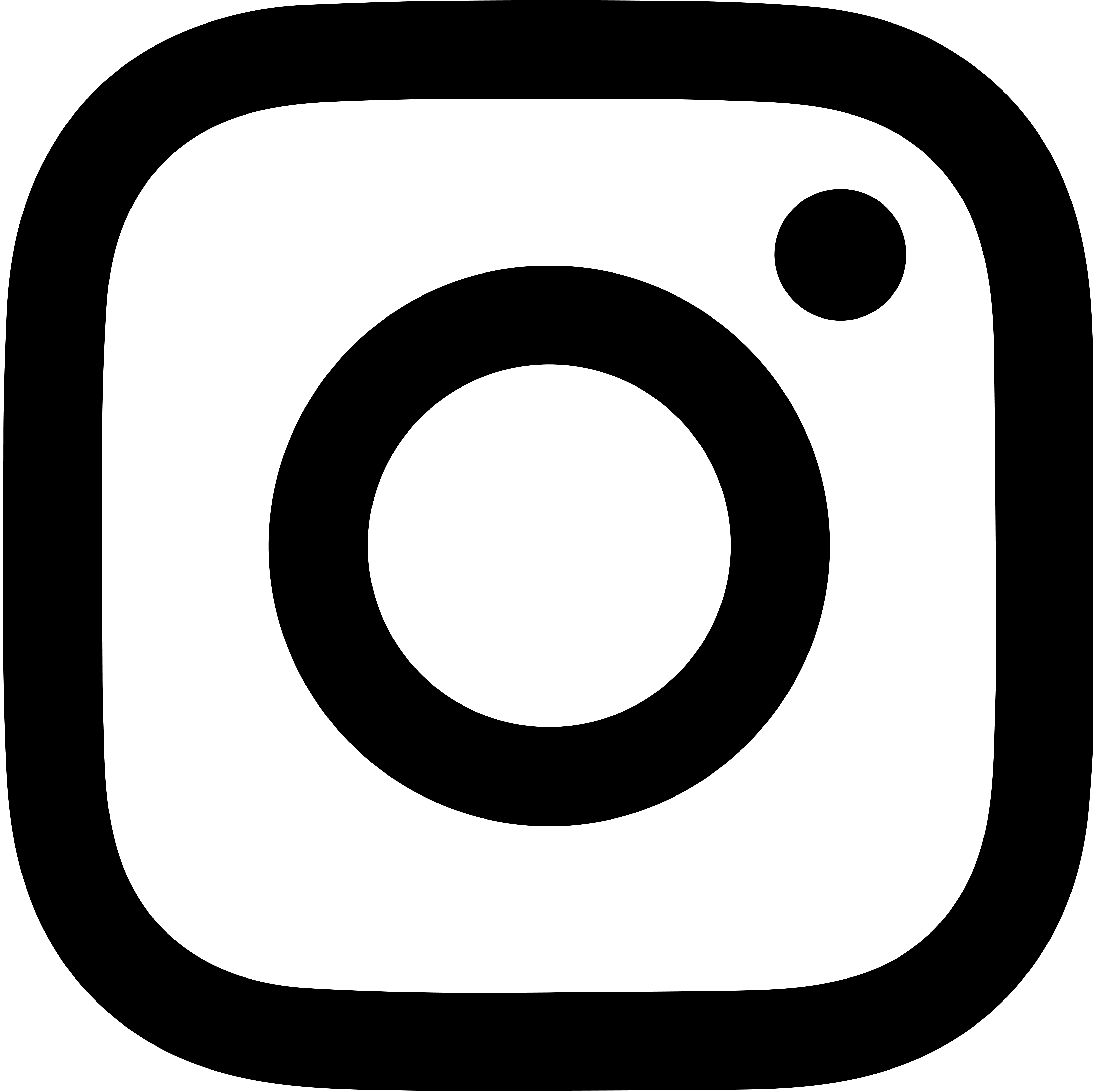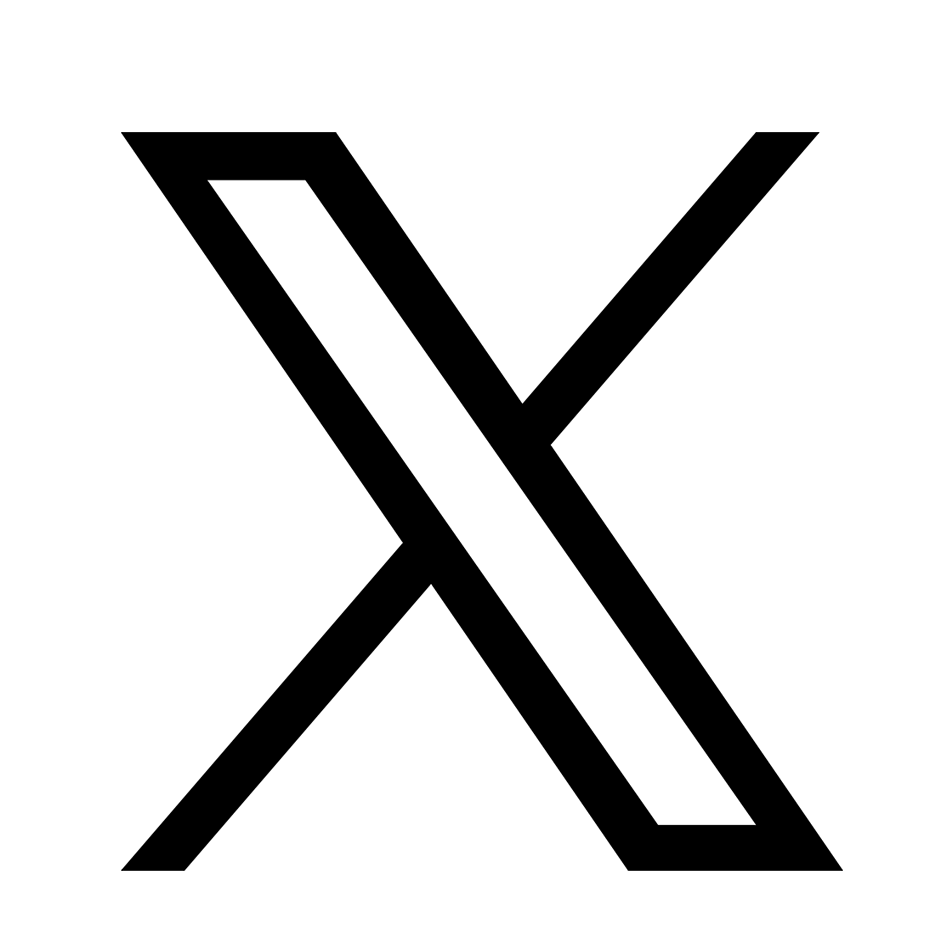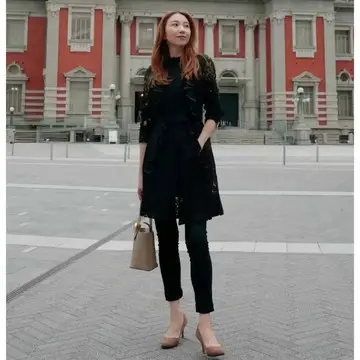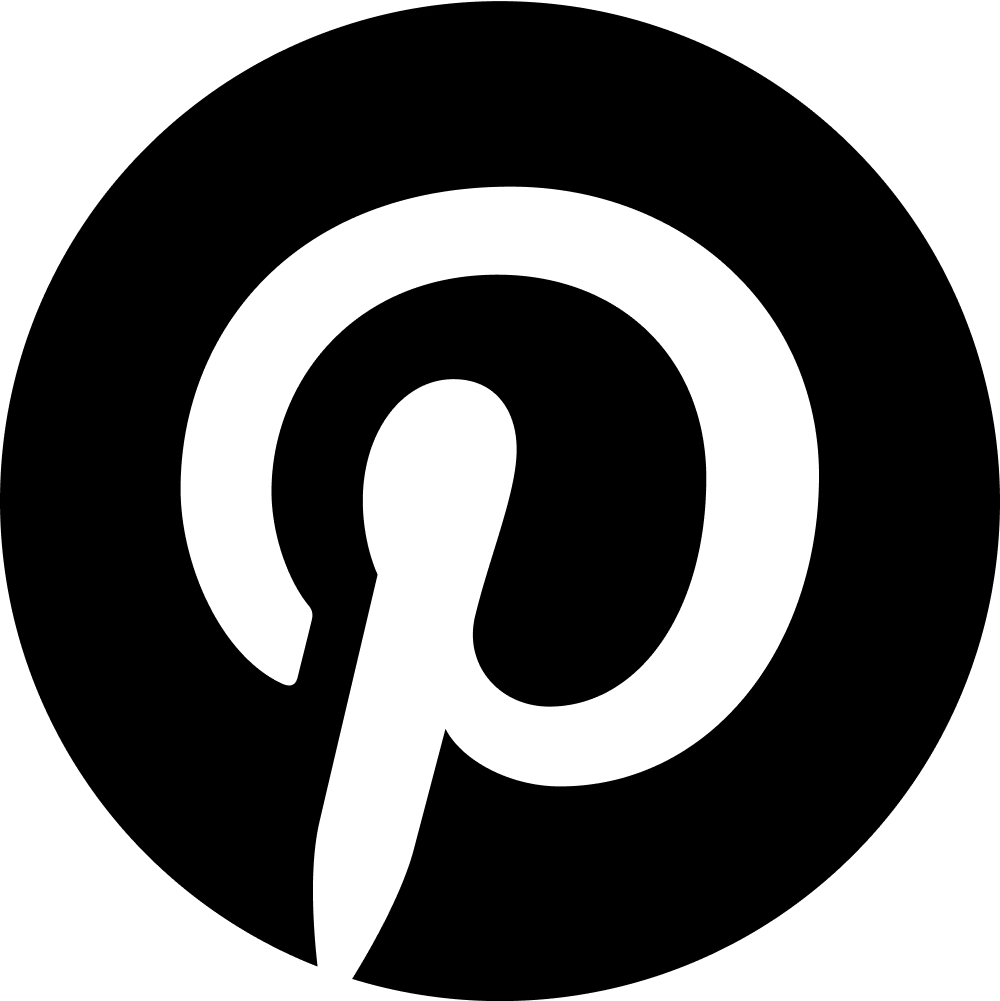新聞でふと目にとまった記事が気になって、いつまでも頭の隅に残り続ける。新聞ではなく、今はネットニュースかもしれませんけどね。恩田陸『灰の劇場』はそんなひとつの新聞記事から始まるスリリングな小説だ。
それは年配の女性ふたりが橋の上から飛び降りて自殺したという記事だった。作家の「私」はその記事が気になり、いつか小説にと思いながら二十数年がたった。
編集者が見つけ出してきた記事は1994年4月のもので、見出しは「飛び降り?2女性死傷 奥多摩町の橋/東京」。9月に出た続報によると、ふたりは大学時代の友人同士で同じマンションで同居していたという。間違いない、これだ! ただしてっきり60代と思い込んでいたふたりの年齢は45歳と44歳。その年をとっくに超えた「私」は意外の念に打たれる。そんなに若かったの?
かくて彼女は、このふたりがどんな関係で、何ゆえ同居していたかを考えはじめ、時には妄想に悩まされるほどになるのである。
と同時に小説では「私」の頭が考えたふたりの姿がリアルに描き出される。のちに意外な結末を迎えることになるふたりはTとM。
Tはマイペースのお嬢さんタイプで男子学生に人気があった。大学を出たあと、大手有名家電メーカーにコネで就職した。女性の職能は「花嫁候補」、仕事は「腰かけ」とされていた時代である。Tはそれでいいと思っていた。自分は家庭的だし結婚向きだ。だから3年もたたぬうちにハイスペックな男性と結婚した。永久就職だ。
結婚式場の「新婦友人」席で、Mは親友のTを不思議な感覚で見ていた。こうやって人はからめとられていく。小さな貿易会社に就職して、自分はやっと人生が始まったばかりなのに、Tはもう人生を下りて家庭に入るのか。
こうして別々の道を歩みはじめたふたりが再び接点をもったのは30代の半ばだった。幸せそうだったTは離婚していたのである。
ああでもないこうでもないと想像をめぐらす作家の創作現場と、その結果生み出されたTとMという人物がひとつの世界で共存し、交錯さえするのが本書の魅力。
話を劇的なほうへ、物語的なほうへともっていきたくなる〈エンターテインメント作家の性〉を超えて彼女は考える。〈人は、意外に「気分」で死ぬ。/発作的に。衝動的に。なんとなく〉〈おのれが死を選んだ理由を、その本人も最後までよく分かっていないこともあるのではないだろうか〉。
恩田陸がデビューして、やがて30年。旺盛な筆力で多くの読者を魅了しつづけてきた作家の70作目の作品。探偵でも警察でもなく小説家が想像した女性ふたりの「死の真相」は静かで平凡で、それだけによけいリアルで哀しい。