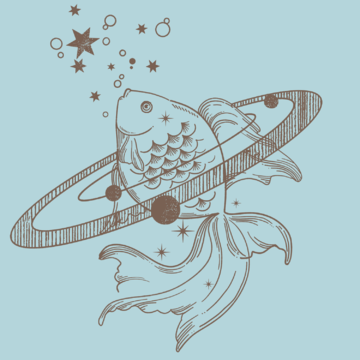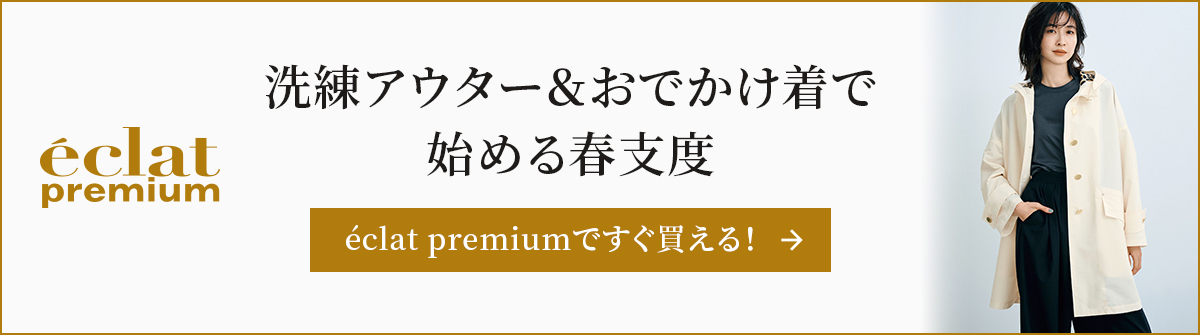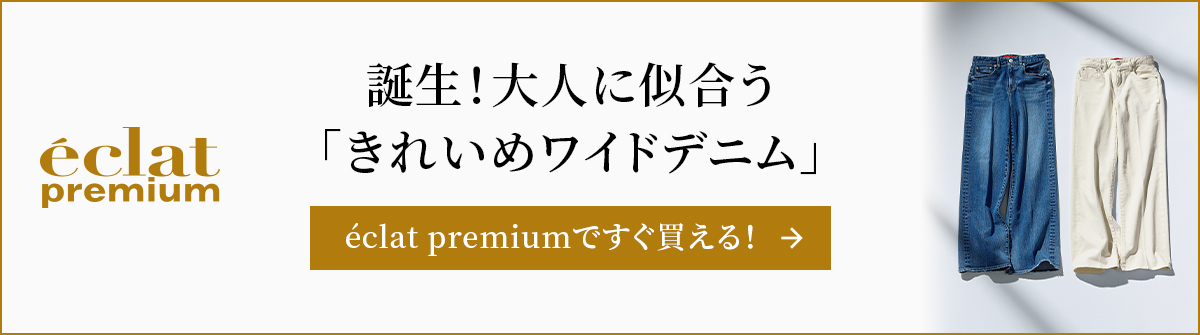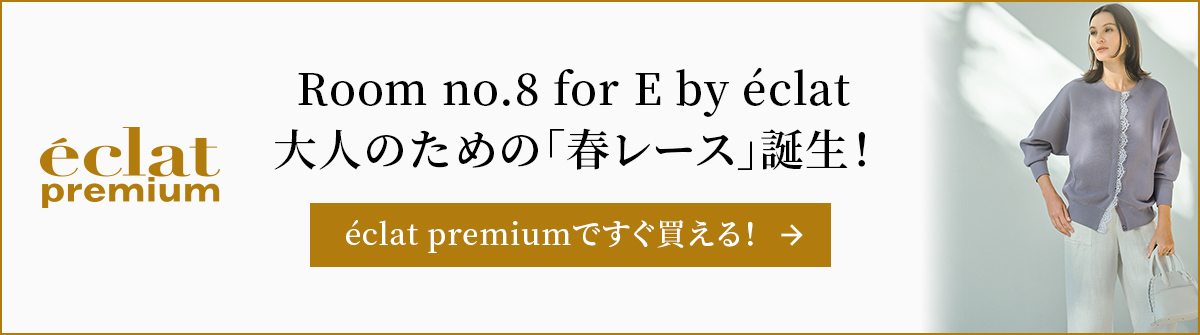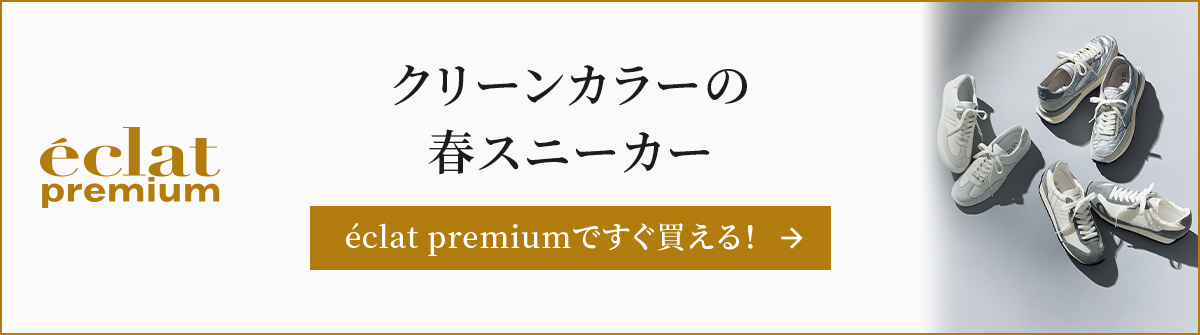アラフィー女性に読んでほしいおすすめ本を、文芸評論家・斎藤美奈子さんがピックアップ。今回は地方都市を舞台にした『まっとうな人生』とほか2冊をご紹介。
さいとう みなこ●文芸評論家。編集者を経て’94年『妊娠小説』でデビュー。その後、新聞や雑誌での文芸評論や書評などを執筆。『名作うしろ読み』『ニッポン沈没』『文庫解説ワンダーランド』『中古典のすすめ』『忖度しません』『挑発する少女小説』ほか著書多数。

富山県を舞台にした外出自粛期の微妙な人間模様
地方都市を舞台にした小説はなべておもしろい。土地の風習やお国言葉を含む地域の多様性そのものが興味深く、地域性が深掘りされればされるほどテンションが上がるのはなぜ?
絲山秋子『まっとうな人生』は『逃亡くそたわけ』(2005年)の17年ぶりの続編である。
語り手の「あたし」こと花ちゃん(花田しずか)と、名古屋生まれのなごやん(蓬田司)。若いふたりが福岡の病院を抜け出して鹿児島までを走り抜ける『逃亡くそたわけ』は、九州を舞台にした爽快なロードノベルだった。
それから十数年後、花ちゃんとなごやんは富山にいた。30代後半になったふたりはそれぞれに家庭をもち、花ちゃんは夫の実家が、なごやんは妻の実家がある富山に移住してきたのだった。農機具の会社に勤める夫と10歳になる娘の佳音と花ちゃんは富山市内に住み、なごやんは高岡市の妻の実家でパソコン教室を開いている。偶然再会したふたりは家族ぐるみの付き合いを始めるが……。
危なっかしかった若者がすっかり大人になり、ちゃんとしたママやパパをやっている。それだけでも成長したわが子を見るような胸キュン感があるのだが、故郷を離れ、習慣の異なる新天地で暮らす彼女の心境がまた身にしみる。
〈よそ者のことを、富山では「たびのひと」と言う。何十年住んでいても出身が違うだけでそう言う〉。生まれ育った福岡を彼女は〈今はもう滅びてしまった遠い国のように感じるときがあって、心に冷たい金属をきゅうっと押し当てられたような気分になる〉。それは夫とも娘とも共有できない感覚だ。なにしろ〈あたしに富山弁が話せないように、佳音は博多弁が話せない〉のだ。
それでも彼女はまあまあ元気に暮らしており、時には黒部市にある夫の実家へも行き来して、富山の生活を楽しんでいた。
ところがそこに、予期せぬ事態が勃発した。コロナ禍である。
富山にはウイルスがまだ到達していないころから、彼女の頭の中では警笛が鳴った。〈なりふりかまわず家族を守れ!〉〈食べ物を確保せよ!〉〈清潔を保て!〉。
コロナ第1波当時の緊張感と不安が蘇る。コロナ禍はそれまでは意識しなかった地域の排他性もあぶり出す。県外ナンバーの車を嫌う妻の言葉になごやんも傷ついていた。〈俺だって「たびのひと」だもの。そういうところから差別って始まるじゃん〉。
2019年4月から’21年10月までの2年半にわたる物語。
日本中の家族が体験したであろう「あのころ」の気分をなぞりつつ、北陸の一都市への関心もかきたてる佳編。男女間の友情を描かせたらピカイチの絲山秋子にしか書けない世界である。
『まっとうな人生』
絲山秋子 河出書房新社 ¥1,892
旅行者とも出身者ともちがう移住者という微妙な立場で暮らす「あたし」。持病の双極性障害(古い名称は躁うつ病)も小康状態を保ち、まあまあ元気に家庭生活を営んでいたが、そこにコロナ禍到来。覚醒した「あたし」は臨戦態勢に入るも、それは躁うつの躁状態に近かった。しかも福岡の実家では家族が倒れ……。大変な事態を深刻すぎない筆致で描いた最新のコロナ文学。富山の風物をたっぷり盛り込んだご当地文学としても秀逸。
あわせて読みたい!

『逃亡くそたわけ』
絲山秋子 講談社文庫 ¥440
福岡の精神科病棟に入院していた大学生の「あたし」は躁状態の中で「21歳の夏は一度しか来ない」と思いたち、入院仲間で3歳上の「なごやん」と車で逃亡。福岡から大分を経由して阿蘇に寄り道し、宮崎、そして鹿児島までの長い旅の結末は?

『富山のトリセツ』
昭文社編集部/編 昭文社¥1,980
ご当地文学は地図と一緒に読むのがおすすめだ。地形や気候から交通、歴史、文化、産業までを一冊で網羅した「トリセツ」シリーズは観光ガイド本より深い、県別の地域ガイド。富山湾の向こうに立山連峰がそびえる富山の魅力が堪能できる。