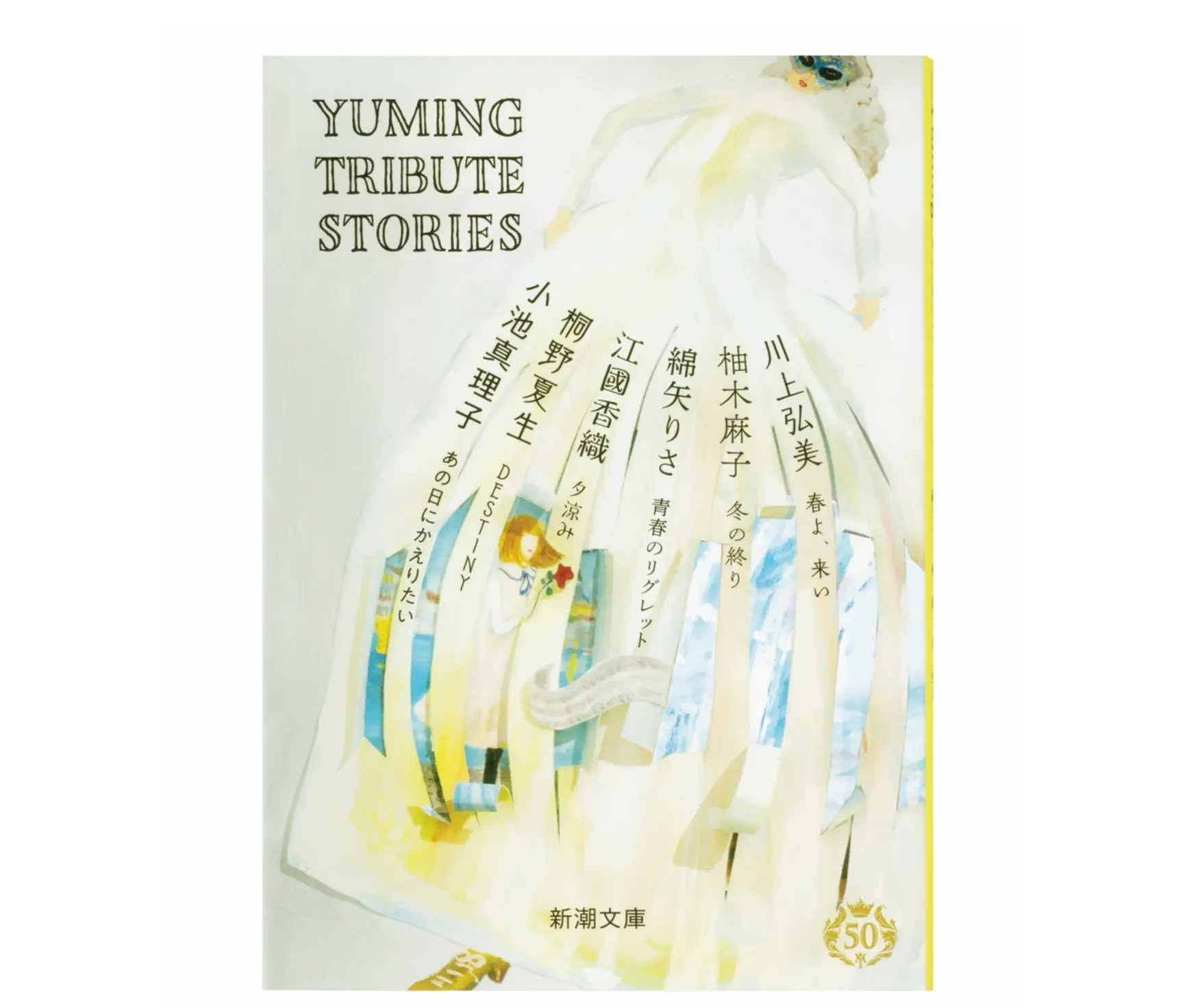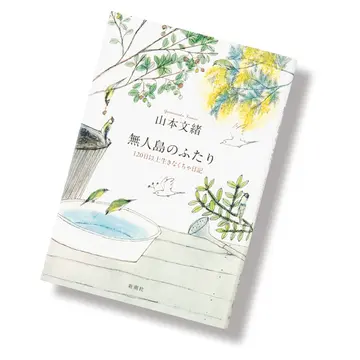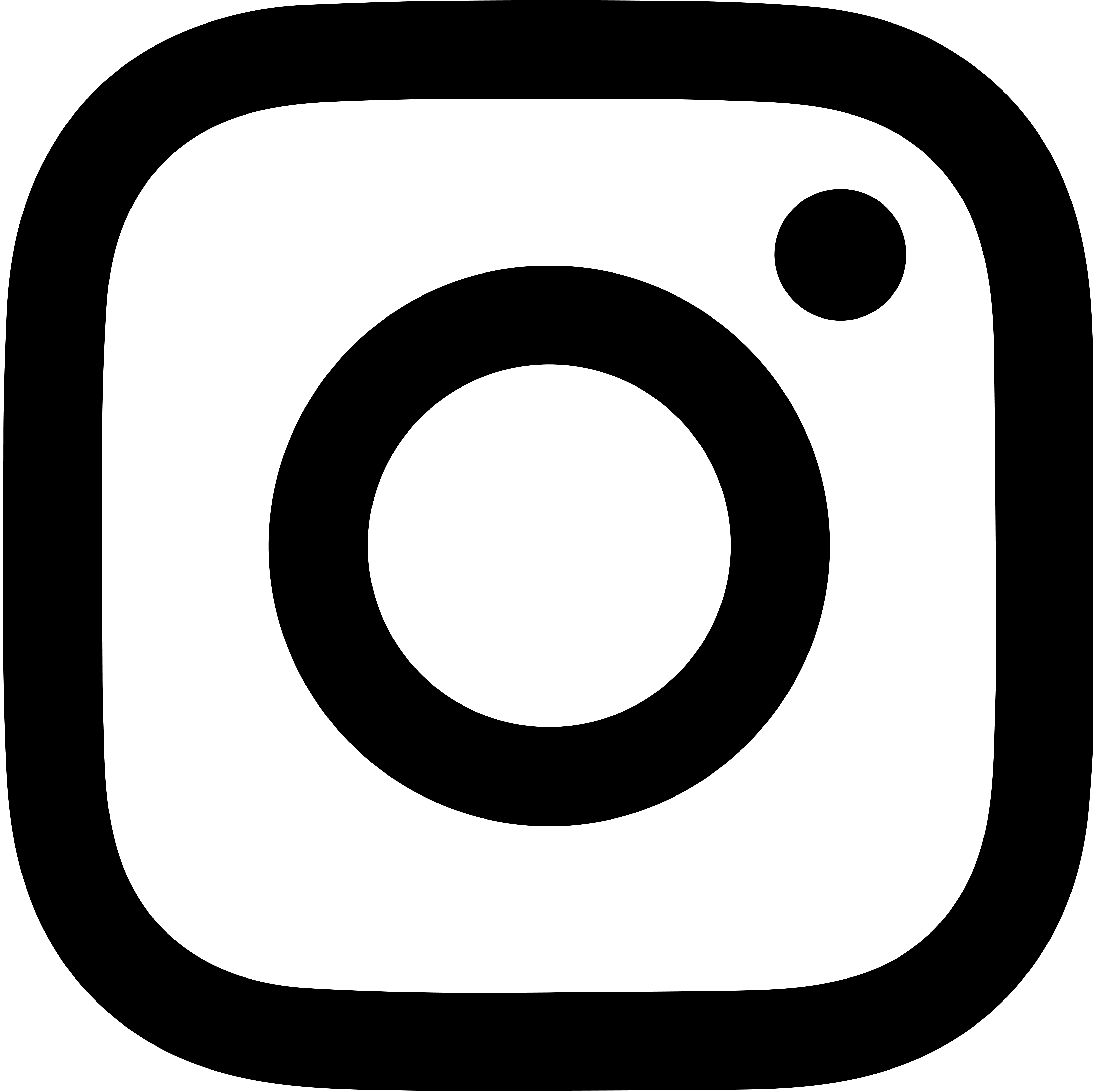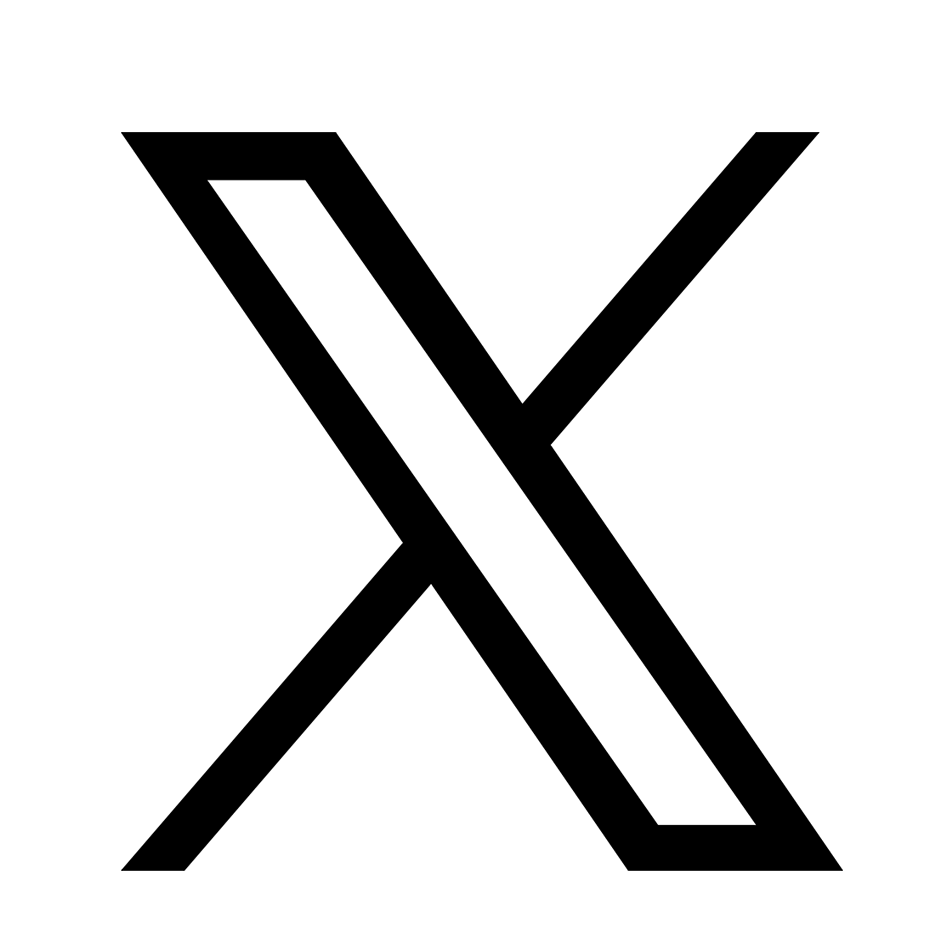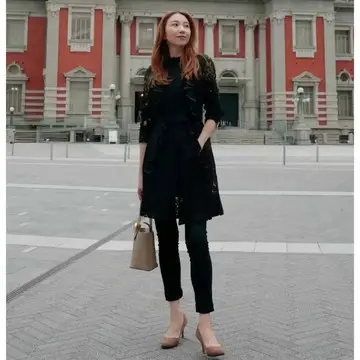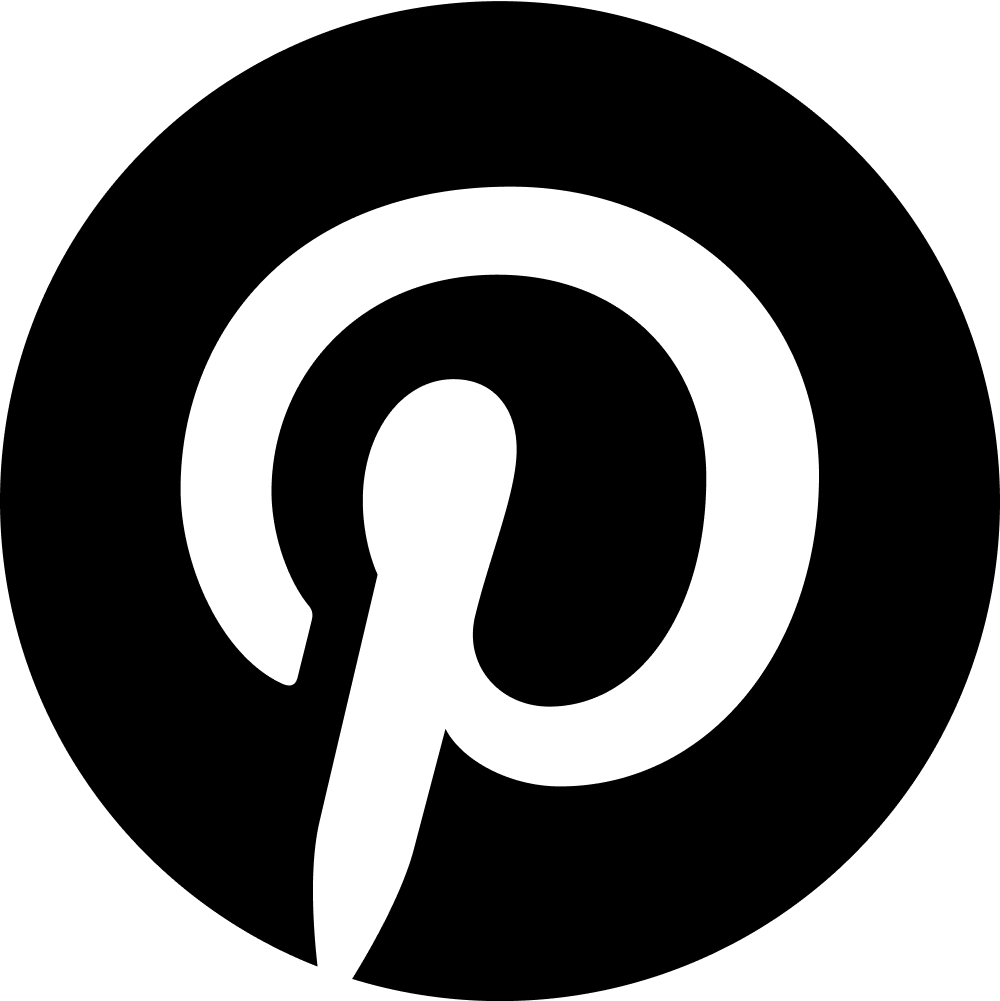昨年はユーミンこと松任谷由実さんのデビュー50周年だった。現在の30代から60代まで、人生のさまざまな局面でユーミンの曲がそばにあったという人は少なくないだろう。
記念書籍も続々出版。山内マリコ『すべてのことはメッセージ』の副題は「小説ユーミン」。八王子の由実ちゃんこと荒井由実が、シンガーソングライター・ユーミンになるまでの物語である。
東京郊外の八王子は「桑都(そうと)」と呼ばれる養蚕や織物の産地であり、絹糸の集散地として江戸期から商人でにぎわう町だった。ここで店を構える荒井呉服店は戦後、創業者の与三が引退、娘の芳枝夫妻に代がわりしていた。芳枝すなわち由実の母は女学校や家政学院で学んだ元モダンガール。新しい文化に敏感な先取的な人だった。
1954年1月、由実はこの家の次女として生まれた。4人きょうだいの下から2番目。カトリック系の幼稚園で西洋文化の風を受け、大勢の人が働く家では純和風。姉のゆうこと違い、由実は芳枝の趣味にたっぷり付き合わされて育った。映画、歌舞伎、宝塚歌劇。習い事はピアノと清元。
地元の小学校を出て中学受験をし、姉のゆうこも通う立教女学院に進学した由実は、13歳で音楽との運命的な出会いをする。学校の教会で聞いたパイプオルガンと、グループ・サウンズ(GS)である。タイガースやテンプターズが一世を風靡する中、由実のお気に入りはややマイナーなビーバーズとフィンガーズだった……。
この本の特徴は、八王子の歴史から説き起こし、’50年代から’70年代までの大きな時代の流れの中で、この時代に育った一少女の物語を浮かび上がらせている点である。主人公は荒井由実その人であるにしても、作者の巧みな構成力に乗せられて、読者は当時のカルチャーを強烈に思い出し、過去に飛ぶ感覚を味わうだろう。一種の群像劇といってもいい。
由実の早熟ぶりはしかし、やはり群を抜いていた。新宿のジャズ喫茶に通い、立川の米軍基地に出入りして最先端の音楽に触れるうち、彼女は大きな発見をする。〈わたしにも曲は作れる!〉
プロコル・ハルムの『青い影』とバッハの『G線上のアリア』が同じコード進行だと気づいたのがキッカケだった。日常の中でふと湧き上がるメロディ。中学3年生の由実は考えた。〈わたしは天才なんだ。自分の作品を作るアーティストになるんだ。いつか自分が作った歌を、世に出すんだ。/わたしは、作曲家になりたい〉
ここから彼女が18歳でデビューするまでにはもうひと波乱あるのだけれど、半生記というより青春譜。刻苦奮闘、艱難(かんなん)辛苦の成功物語とはひと味もふた味も違った展開なのがユーミンらしい。