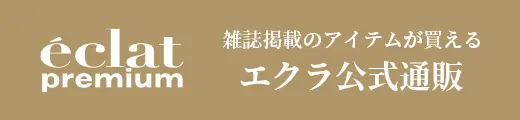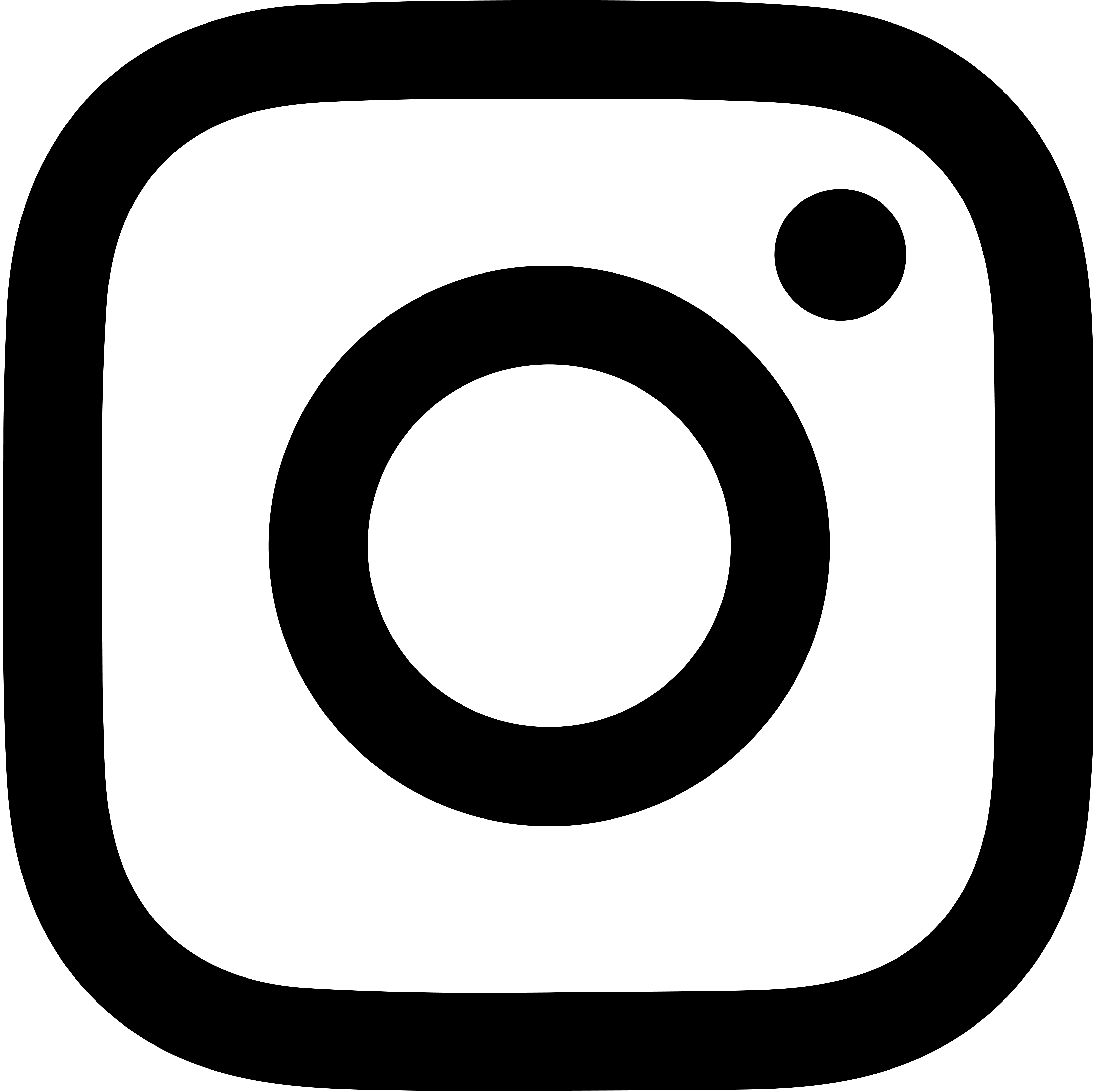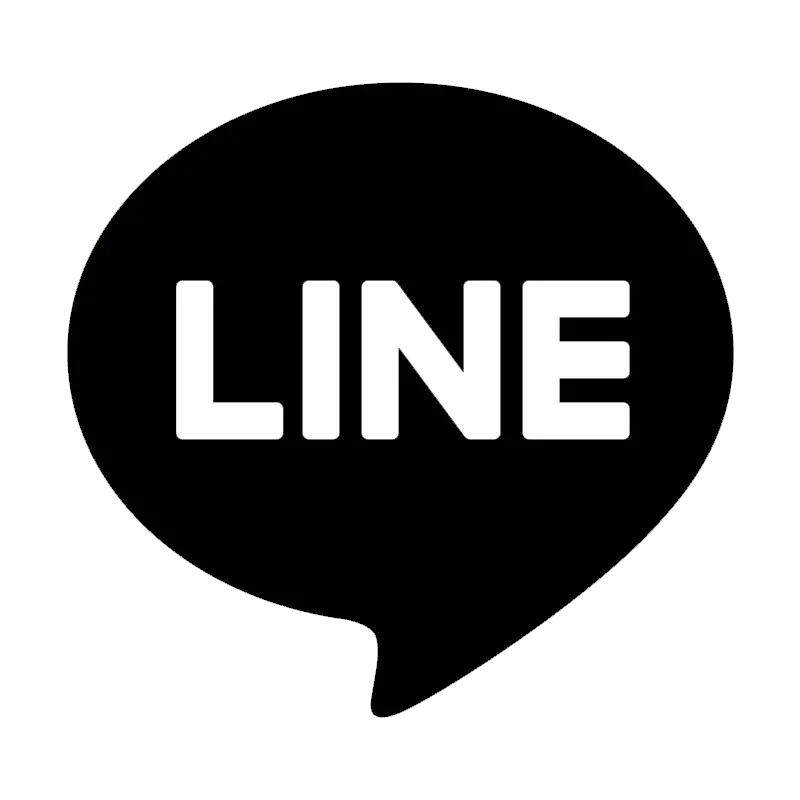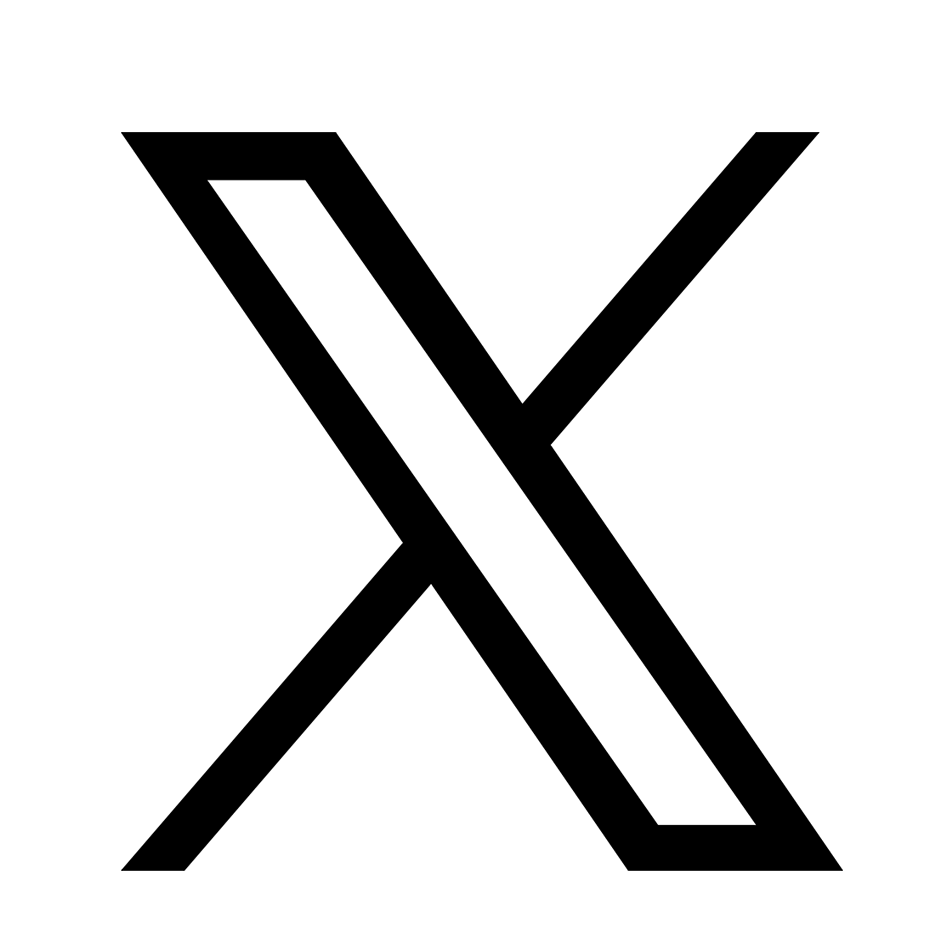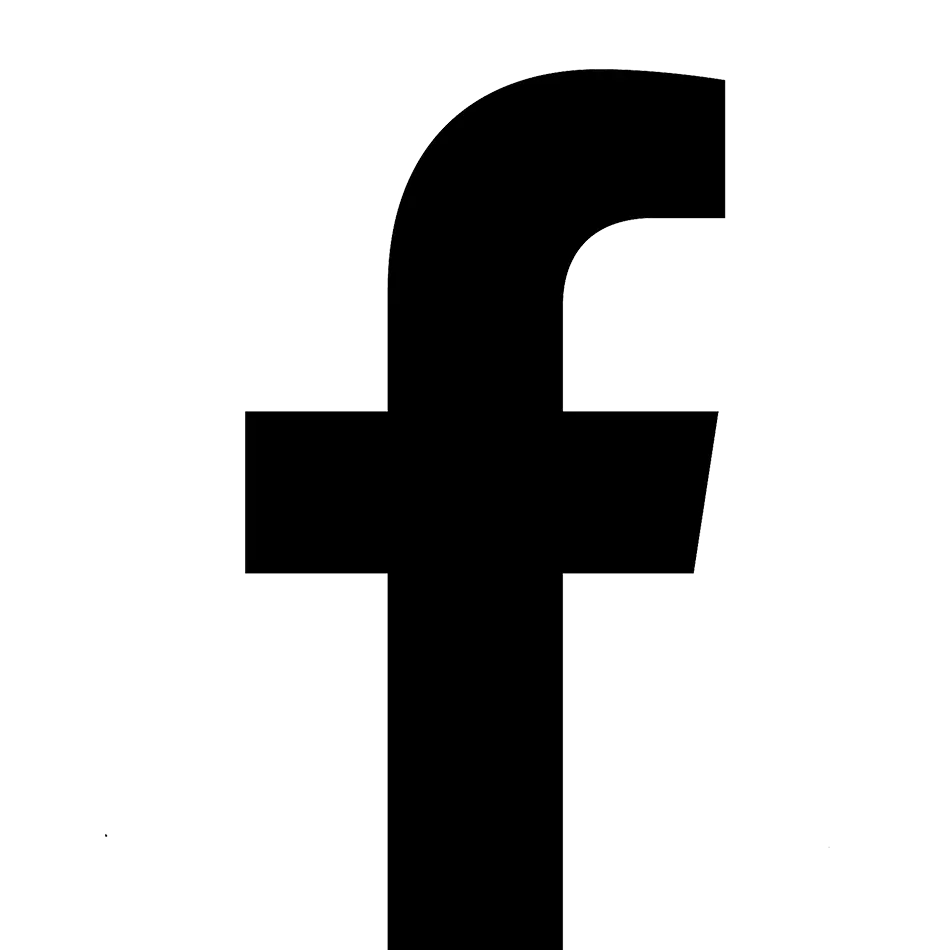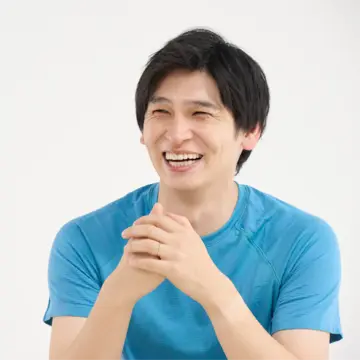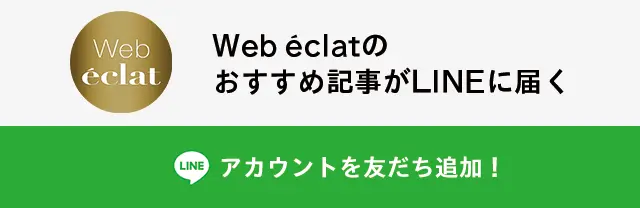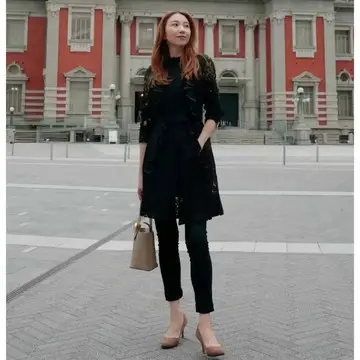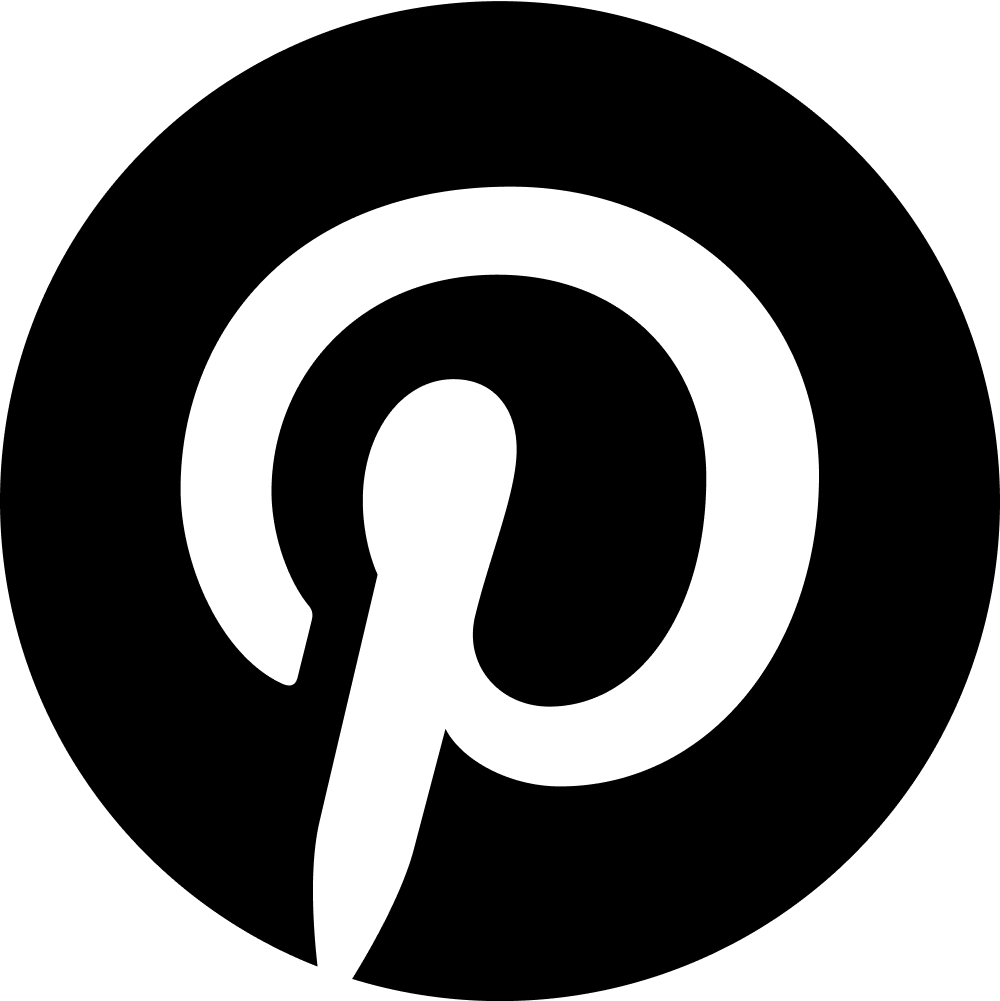-
【神崎恵さんのさびない食生活】“発酵食品”&“タンパク質”をしっかりと。一生動きのいい体づくりを目ざして
エクラ世代は、日々の内側からのメンテナンスが大切。美容家・神崎恵さんが、体力に不安を感じた時に有効な“発酵食品”&“タンパク質”が取れるヌードル&プロテインをご紹介。
【50代からの「筋活」】どう始めたらいい?失敗しない「プロテイン」生活
プロテインって、そもそも何?
プロテインの主成分はタンパク質。語源はギリシャ語で「欠かせないもの」を意味する「プロテウス」。その名のとおり皮膚や髪の毛、内臓、筋肉など体のあらゆる部分をつくるのに必要な成分。牛乳や大豆のタンパク質を粉末などに加工して、手軽に摂取できるようにしたものが、いわゆる「プロテイン」商品。

どんな成分のものがある?
一般的なプロテインは大きく3種類。牛乳のタンパク質から作られる「ホエイプロテイン」、同じく牛乳から作られる「カゼインプロテイン」、そして大豆タンパク質から作られる「ソイプロテイン」。ホエイとカゼインは主に吸収速度の違いで、前者は早く後者はゆっくり。ソイプロテインの吸収はその中間で、かつ大豆イソフラボンの効果で皮膚や骨の強化、血流改善などが期待できる。
いつ飲むのがよい?
タンパク質は体内で合成と分解を繰り返して各器官を維持しているため、材料となるタンパク質のストックが常に体内にある状態が望ましい。3度の食事ではタンパク質を意識してとり、間食でプロテインをプラス、というのが◎。就寝中はタンパク質が体の中にない状態が長く続くため、夜寝る前と朝起きてからのタンパク質摂取は特に重要。

適量はどのぐらい?
厚生労働省の基準では、体重1kg当たり1日0.9gが推奨量。つまり体重50kgの人は45g/日が望ましい。ただし加齢に伴ってタンパク質の吸収・利用効率が下がっていくため、アラフィーになったら体重1kg当たり1.2~1.4gに増やしたい。
必要十分なタンパク質をとるにはプロテインが重宝
教えてくれたのは

パーソナルトレーナー・管理栄養士 河村玲子さん
筋トレをするならプロテイン、とはよく聞くけれど、やっぱりとらないとダメ?「ダメではないけれど、とるほうが確実に筋肉を増やすことはできます」と河村さん。
「筋肉の材料はタンパク質、つまりプロテインです。最近は方々で『タンパク質をしっかりとろう』といわれますが、実は今の日本人の平均的な食生活からするとタンパク質が不足しているということはありません。ただ、年齢が上がるにつれてタンパク質の吸収・利用効率は下がります。また食品によっては吸収しづらいタンパク質も。そうしたことから考えて、エクラ世代では厚労省の提示する量よりもやや多め、体重1kg当たり1.4gくらいでもいい。これは体重50kgのかたなら一日に70gのタンパク質をとる計算になります。70gは卵や大豆食品、肉や魚などの食品からだけとろうとするとなかなかむずかしい量。なので、手軽に取り入れられるプロテインが重宝します。特に筋トレをして筋肉の分解合成が行われるときには、その材料となるプロテインが十分に体内にあることで筋肉を効率的に増やすことができます」
-
渡辺満里奈さんも実感!前田昌希さんのエクササイズで50代からの「筋活」
素敵だなと思う人って、体づくりしていることが多くないですか? どんなことを、どのくらいの頻度で? 本当に効いたトレーニングは? 渡辺満里奈さん&前田昌希さんに「筋活」について聞いた。
-
【50代からの「筋活」】何歳からでも筋肉は裏切らない!50代からの筋トレ覚書
50代ならではの筋トレ方法を、順天堂大学スポーツ運動科学部教授 谷本道哉さんが指南! 筋トレの負荷や頻度、おすすめのストレッチをチェックして。
What's New
-
絶対に風邪をひけない時に! Me Todayのマヌカハニーでお守りケア【更年期・50代編集者の養生ダイアリー】
以前より風邪をひきやすくなった、季節の変わり目に調子をくずしやすい――これも「40代・50代あるある」のひとつ。こんなはずじゃなかったと後悔する前に、毎日コツコツ、おいしく続けられる“体調管理はちみつ”を。朝イチのエネルギーチャージにも、帰宅後ののどケアにも。とにかく、季節の変わり目の体調ケアにおすすめです!
ヘルスケア
2026年1月16日
-
【ボディワーカー森拓郎さんが指南 正月太りをすっきりリセット vol.3】 3週間でウエスト-4cm! Jマダムがリセットプログラムに3週間トライ
年末年始の食べ過ぎて、体重が増えてしまった……! そんなときのリセット法を、ボディワーカーの森拓郎さんに教えていただく連載。3回目は、Jマダム2人がリセットプログラムに3週間トライ。その結果は……着実に効果が出ました!
ヘルスケア
2026年1月7日
-
【ボディワーカー森拓郎さんが指南 正月太りをすっきりリセットvol.2 】 動画つき! リセットのため、太りにくい体を作るためにおすすめの運動は?
年末年始に食べ過ぎてしまって体重が増加! 素早く元に戻すには? そんな方法を、ボディワーカーの森拓郎さんに教えていただく連載。前回は、食事でのリセット法を教えていただきましたが、今回は、体重・体型を元に戻して、太りにくい体を作るための運動編です。
ヘルスケア
2026年1月6日
-
【ボディワーカー森拓郎さんが指南 正月太りをすっきりリセット vol.1】 正月太りの正体とは? まずは食事の見直しがマスト
お正月を過ぎたこの時期、気になり始めるのが体重の増加。特にエクラ世代になると、いったん太るとなかなか元に戻りにくいものです。 そこで今回は、“正月太り”をリセットするための食事や運動について、ボディワーカーでピラティス指導者の森拓郎さんにうかがいました。1回目は、食事によるリセット法をご紹介します。
ヘルスケア
2026年1月5日
-
ガンコな大人の便秘に。『FTC』水溶性食物繊維のすすめ【更年期・50代編集者の養生ダイアリー】
エクラ世代のエディターが、自分のエイジング&更年期のお悩み解決に役立ったおすすめアイテムをご紹介。第1回は、年々エスカレートしていく「便秘」悩みをやわらげてくれた機能性表示食品。君島十和子さんのブランド『FTC』の妥協なきインナーケアです。
ヘルスケア
2025年12月27日
-
-
-
-
-
-
カジュアルすぎないのが正解!冬はきれいめに着こなす「50代のデニム」スタイル
デニムは好きだけれど、ラフに見えすぎるのは避けたい。そんな大人の冬に頼れるのが、ニットやジャケットを合わせたきれいめデニムコーデ。無理なく今っぽく、品よく見せる大人の着こなし6選。
Magazine
-
大人の品格まとうシチズンの限定ウオッチ
シチズンから洗練されたデザインの限定ウオッチが新登場!
-
新しくなったドモホルンリンクルに注目
主力製品の[基本4点]が大きくリニューアル。その実力のは?
-
松井陽子の「エクラ ゴルフ部へようこそ!」
松井陽子さんが50代におすすめのゴルフウェアやゴルフの楽しみ方をご紹介。
-
一度は泊まりたい!高級ホテル・旅館
日常を忘れて至福のときが過ごせる極上の旅へ
-
エクラ公式通販の人気アイテムランキング
もう迷わない!50代が買うべき秋の服
-
年齢を重ねるごとに、自信がもてる肌へ!
無料お試しセットで、新生ドモホルンリンクルのお手入れを体験
-
50代におすすめのトレンドアイテム
人気ファッションアイテムを厳選してご紹介
-
大人のためのヘアスタイル・髪型カタログ
髪のお悩み解決!若々しく見えるヘアスタイル
-
読者モデル 華組のユニクロ・GUコーデ
真似したい!50代ファッションブロガーの着こなし集
-
あの「アミコラ」に注目成分NMNがプラス
味がなく料理や飲み物に溶かすだけだから習慣にしやすい
-
読者モデル 華組のZARAコーデ
50代はどう着こなす?ファッションブロガーコーデ集
-
【40代・50代におすすめ髪型カタログ】髪型で若見え!おばさんぽくならないショート・ボブ・ミディアム・ロング別ヘアスタイル
40代・50代はどんなヘアスタイルがおすすめ?今回は髪のうねりや薄毛、白髪など気になる髪悩みを解消するおすすめヘアスタイルをご紹介。ショート、ボブ、ミディアム、ロング別ヘアスタイルから知っておきたい最新…
-
【40代・50代「ユニクロ・GU」冬コーデ】寒い冬の心強い味方!ニットや暖パンなど"あったかアイテム”が人気
老若男女問わず、さまざまな世代の人から愛されているブランド「ユニクロ」。40代・50代のおしゃれ好きな女性からの人気も絶大!そこで今回は「ユニクロ・GU」のアイテムを使った、おしゃれな40代・50代のコーデを…
-
50代に人気上昇中!上品な華やかさ「冬のミディアムヘア」52選
冬の空気に似合うのは、品よく華やかで、ほんのり女らしさを感じるミディアムヘア。50代の女性に人気上昇中のスタイルは、髪悩みや顔まわりの悩みをカバーしながら、印象をぐっと明るく見せてくれるスタイル。
-
まぶたが重くなった目元がくっきり!目力アップを叶える「40代・50代におすすめのアイメイク」
まぶたが重くなってきた...、アイラインが上手く描けない...、そんな目元のお悩みはちょっとしたコツで見違える!アイライン・アイシャドウ・マスカラの3つで仕上げる、上品で若々しい“簡単アイメイク”をご紹介。
-
【40代・50代に人気のショートヘア60選】おばさんにならない!大人かっこいい若見えショートヘア
ヘアスタイルに気を遣っているかで印象が大きく違ってくる40代・50代。そこで今回は大人のかっこよさと上品な雰囲気を引き出し、若見え効果も叶う冬にぴったりのショートヘアをご紹介。白髪や薄毛、うねりのお悩み…